中学受験国語|記述問題対策の勉強法とポイント
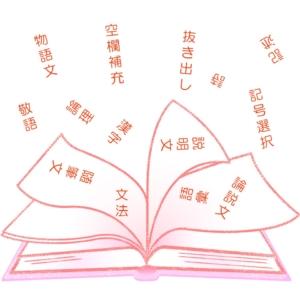
中学受験の国語、とりわけ「記述問題」に悩むご家庭は多いです。模試や過去問を解かせてみると、「字数は埋まったけど点数がもらえない」、「何を書けばいいかわからず手が止まる」といった声は珍しくありません。
実は、国語の記述はセンスではなく型と準備の習慣で伸びていきます。今回は、塾や家庭学習で今すぐ取り入れられる「シンプルな考え方」と「取り組み方の工夫」をまとめました。
記述が点にならないのは「書く前」に原因あり
「もっと丁寧に書こう」「とにかく字数を埋めよう」と指導してもうまくいかないのは、答案を書く前の準備不足が原因です。本文の根拠をどこから持ってくるのか、どの型で書くのかを決めないまま筆を進めてしまうと、最後に「まとまりのない長文」が残るだけ。
逆に、型を決めて→根拠を拾って→要素をまとめてから書くという流れを習慣にすると、答案の安定感は一気に変わります。
子どもでも使える「3つの型」
国語の記述にはさまざまな設問形式がありますが、まずは次の3つを押さえるだけで十分です。
- 理由型:「なぜ…か」に答える
- 対比型:「AとBの違いは?」に答える
- 要約型:「本文の主張をまとめよ」に答える
この「万能三型」に当てはめれば、少なくとも「白紙で終わる」ことはなくなります。家庭で声かけをする際も、「これって理由? 対比?」と問いかけるだけで、子どもは答えの方向性をつかみやすくなります。
根拠を拾うときのちょっとしたコツ
記述問題の得点は、本文の根拠をいかに正確に拾えるかで決まります。おすすめは「接続語・指示語・段落端」に注目すること。
- 接続語(しかし・だから)の後は要点になりやすい
- 指示語(それ・この)は具体的に言い換える
- 段落の最初と最後には主張がまとまりやすい
こうした「目印探し」を意識させるだけで、根拠探しの精度が上がり、答案の説得力も増していきます。
家でできる練習サイクル
毎日長い記述を解く必要はありません。塾の授業で扱った題材について、授業を受けて満足するのではなく、解説された内容を振り返り、しっかり次に繋げるのが良いです。
「次の授業までにわすれてしまう!」など、もしも追加でというご家庭でも、ただ解くのではなく、前回の授業で学んだことや記述の型を意識しながら、以下のうちから1つ2つ選ぶくらいで十分です。
- 新しい問題を解く日:型を意識して一文でまとめる
- 復習の日:1~2週間前に解いた問題から記述1問に再挑戦
- ミニ練習:本文の言葉を別の言葉に置き換える「言い換え遊び」
この繰り返しが、安定して点が取れる答案につながっていきます。
親ができるサポートの工夫
「書きなさい」「もっと丁寧に!」では、子どもはますます苦手意識を強めてしまいます。おすすめは、添削を「ダメ出し」ではなく「タグ付け」に変えること。
たとえば「根拠が薄い」「字数オーバー」とシンプルに書き残しておき、次回解く前に「前は『字数オーバー』がついたね。今日は意識してみよう」と伝える。これなら子どもも前向きに取り組みやすく、改善のポイントも明確になります。
まとめ:記述は「型と習慣」で怖くなくなる
国語の記述は、「センスがある子だけができる特別な力」ではありません。問いの型を決めて、根拠を拾い、短くまとめる習慣を持つこと。これだけで答案は見違えるように変わります。
もちろん、本格的な練習には塾のテキストや過去問が必要ですが、家庭でもできる工夫を積み重ねれば、苦手意識は必ず薄れていきます。まずは「書く前の準備」を一緒に習慣化していきましょう。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)








