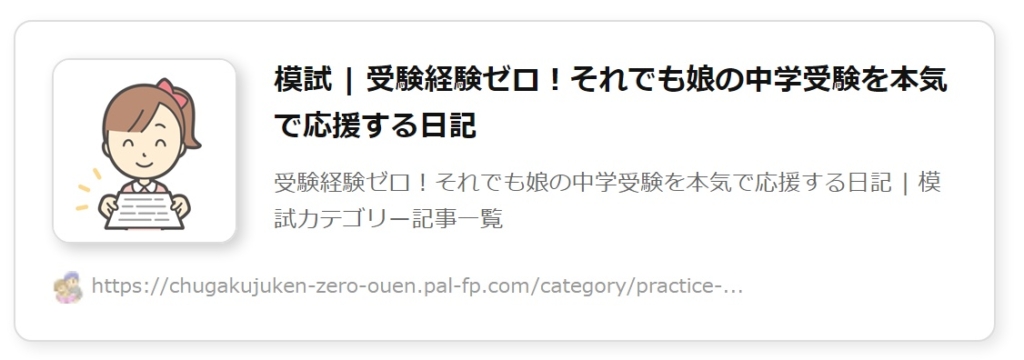中学受験 四谷大塚の偏差値は高い?合格の目安と他塾との比較ポイント

四谷大塚の偏差値って、実際どのくらいなの?サピックスや日能研の偏差値とは何が違うの?これは中学受験を考える多くの保護者が、最初につまずく疑問の一つだと思います。
最初は偏差値の見方がよく分からず、模試の結果を見ても「この数字って良いの?悪いの?」と不安になることもあると思います。でも、色々と調べたり、他のご家庭と情報交換をしていく中で、「四谷大塚の偏差値」には独特の仕組みと見方があることが分かります。



この記事では、四谷大塚の偏差値の特徴・合格の目安・他塾との比較ポイントなどを、保護者目線で丁寧に解説していきます。
四谷大塚の偏差値とは?基本を押さえよう
四谷大塚の偏差値の仕組み
四谷大塚の偏差値は、主に「組分けテスト」や「合不合判定テスト」などの模試をベースに算出されます。このテストには、四谷大塚生だけでなく提携塾の生徒や外部受験生も多く参加し、受験者数が非常に多いため、偏差値の信頼性が高いとされています。
特に合不合判定テストは比較的オープンな仕組みで、毎年の偏差値一覧が公開されている点も特徴的です。
合格者偏差値と進学者偏差値の違い
四谷大塚の偏差値には、「合格可能性80%ラインの合格者偏差値」と「合格可能性50%ラインの合格者偏差値」とがあります。前者は「安全圏ライン」とも言われ、実際の入試で受かる可能性が高いとされる基準です。
ただし、合格したからと言って、全ての子が進学するわけではないことには注意が必要と思っています。同じような偏差値の中学校について、それらの大学進学実績を比べてみると、大きな違いがあることがあります。私も、「偏差値が高いのになぜ?」と混乱しましたが、これは併願校の兼ね合いや滑り止め戦略が影響していることが多いようです。
年度ごとのばらつきに注意
年度によって偏差値は微妙に変動します。特に首都圏では人気校の倍率上昇による偏差値上昇も珍しくありません。毎年の最新データを見ることが大切です。
他塾との偏差値を比較するときの注意点
塾ごとに偏差値の基準が違う
「サピックスの偏差値50」と「四谷の偏差値50」は同じ意味ではありません。これは、母集団の違いやテストの出題傾向の違いがあるからです。
たとえば、SAPIXは記述式問題が多く思考力を問う傾向が強いですし、そもそもサピックス生は優秀な子たちが多いので、偏差値分布がやや偏るといわれています。一方で四谷は標準的な選択式・記述式を組み合わせたバランス型の出題が多く、受験者も幅広くなっています。
長女もサピックスのオープンテストを受けたことがあり、たまたまほぼ変わらない偏差値でしたが、塾をまたいだ単純比較は危険だと思いながら見るようにしていました。
併用するなら偏差値換算表を活用
「塾間の偏差値換算」にはいろいろな方法が出回っています。「サピックス偏差値=四谷大塚偏差値+10」のような方法ですが、どの方法でも絶対値として信頼しすぎず、目安として活用するのが良いと感じています。
以下は、超ざっくりの偏差値換算表で、「〇〇はこんなんじゃない!」「私の体感と違う!」な意見があるだろうと思いつつも、少し整理してみました。いずれにしても、塾間偏差値の違いを把握したいなら、換算表に頼るのではなく、直接複数の模試を受けて傾向を見ることの方が、わが子の学力を客観的に見る材料になると思います。
- 四谷大塚・日能研・SAPIX・首都圏模試 偏差値換算表(目安)
| SAPIX偏差値 | 四谷大塚偏差値 | 日能研偏差値 | 首都圏模試偏差値 |
|---|---|---|---|
| 70 | 72〜74 | 72〜73 | 80〜82 |
| 65 | 67〜69 | 68〜70 | 75〜78 |
| 60 | 62〜64 | 64〜66 | 70〜73 |
| 55 | 57〜59 | 60〜62 | 65〜68 |
| 50 | 52〜54 | 56〜58 | 60〜63 |
| 45 | 47〜49 | 52〜54 | 55〜58 |
| 40 | 42〜44 | 48〜50 | 50〜53 |
四谷大塚の偏差値で見る合格の目安と志望校対策
偏差値で見る志望校レベルの目安
一般的に、四谷大塚偏差値で
-
65〜70以上:御三家(開成・桜蔭など)
-
60〜65前後:早慶附属・難関国私立
-
50〜60前後:中堅〜上位私立
-
40〜50前後:公立一貫校・中堅私立
が一つの目安になります。ただ、これはあくまで統計上のデータで、合格者には偏差値40台でも成功例があるようです。実際、娘の友人には偏差値52〜54あたりでも、しっかり過去問対策して早慶附属に合格したお子さんもいます。
志望校別に見る合格者偏差値と進学者偏差値のギャップ
たとえば、ある中学で
-
合格者偏差値:63
-
進学者偏差値:57
というように、合格したけれど進学しなかった層の偏差値が高めで、実際に通う生徒の層はやや下がるという傾向があると考えられます。
この場合、進学後に「授業が物足りない」と感じたり、逆に「周囲のレベルが意外と高い」と感じることがあるようです。また、中学受験のときは難関校の1つだったのに、大学受験合格実績では難関公立とあまり変わらないような・・ということも考えられます。
入試の直前期に必要な偏差値の見方
1月〜2月の直前期には、偏差値の伸び悩みに焦る保護者も多いと思います。ただ、合格は偏差値だけで決まるわけではないと改めて感じます。
合不合判定テストのような6年生の志望校判定模試は、良くも悪くもいろいろな問題を扱う最大公約数的なテストです。中学校ごとの入試問題の傾向はまた異なるはずで、過去問で合格ラインを超えていたら、偏差値が多少届いていなくても「受けてみる価値はある」と考えることもできます。
家庭でできる偏差値対策と模試の活用法
模試の位置づけを明確に
模試は「成績を測るもの」ではなく、「学習の確認材料」と捉える方が良いと思います。娘も最初のころは「結果が悪かったら落ち込む」タイプでしたが、「復習して改善できればOKだよ」と伝え続けてきました。
模試の目的を、
-
苦手単元の洗い出し
-
得点パターンの分析
-
試験慣れ
とすることで、偏差値に一喜一憂しすぎない姿勢が保てるようになりました。
家庭での見直し方法
模試の直後は、点数よりも「解き直し」重視。娘と一緒に「なぜ間違えたか」「別の考え方はなかったか」と会話するようにしています。
また、過去の模試をファイリングして、出題傾向やミスの傾向を振り返ることも続けました。
偏差値UPのための学習戦略
偏差値を上げるには、「正答率が高い問題を確実に取る」戦略が重要です。意外とミスが多いのは、国語で言えば漢字や語彙、算数で言えば計算、理社で言えば語句などの基礎問題。ここを落とすと偏差値が地味に下がります。
このあたりの取れるべき問題を取れるようにするように、「毎日の基礎+週末の見直し」などを習慣にしたいところです。
中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に
集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。
中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。
例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。
どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
個別指導・オンライン指導を検討している場合
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
家庭教師を検討している場合
一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。
講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。
各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。
中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】
無料の資料請求ページへ
![]()
確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。
ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。
少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。
まとめ
四谷大塚の偏差値は、中学受験において非常に参考になる指標ですが、それだけで志望校選びを判断するのは危険です。
-
偏差値は塾ごとに意味が違う
-
合格者偏差値と進学者偏差値の違いに注意
-
模試は「点数」より「復習の質」が大切
-
偏差値UPには「基礎の徹底」と「正しい戦略」が鍵
偏差値はあくまで「目安」であり、受験本番に向けた準備の一要素にすぎません。お子さんの性格や得意・不得意、志望校の傾向を踏まえた上で、ご家庭なりのペースで進めていくことが、最終的な成功につながるのではないかと私は感じています。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は参考記事です。