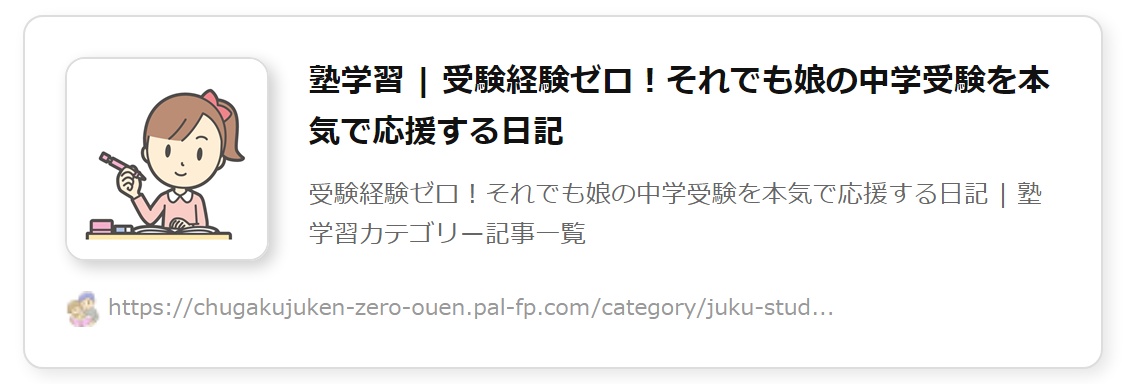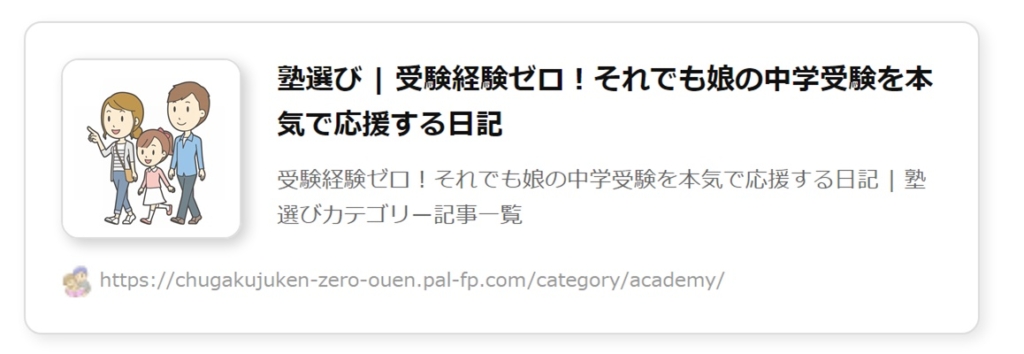中学受験の夏期講習は必要?学年別の目的・費用・選び方を徹底解説

夏の暑さが本格化する頃、塾から続々と届く「夏期講習のご案内」。初めての中学受験を控えた我が家も、4年生の夏から講習に参加するべきか、かなり悩みました。「みんな受けている」と言われる中学受験の夏期講習ですが、内容や費用、必要性はご家庭ごとに大きく異なります。



この記事では、中学受験における夏期講習の位置づけや、学年ごとの目的、費用感、選び方のポイントなどを具体的に解説していきます。私自身の体験も交えながら、夏をどう過ごすかお悩みの保護者の方に少しでも参考になればと思います。
中学受験における夏期講習の役割とは?
なぜ多くの子が参加するのか
夏期講習は、学校の授業がない夏休み期間を活かして、集中的に学力を高める機会です。中学受験を目指す家庭では、学年が上がるほどに講習の重要度も増していきます。
学校の学習と塾の学習の違い
小学校の授業では扱わない範囲も多く、塾のカリキュラムは中学受験専用に設計されています。夏期講習では、これまでに習った単元の総復習や、次学期の先取りなどが行われます。
復習?それとも先取り?
塾によって違いはありますが、「復習型」と「先取り型」のカリキュラムに大別されることが多いです。早稲田アカデミーや四谷大塚は復習と先取りのハイブリッド、SAPIXは全体カリキュラムに含まれていて先取り型と言えます。
学年別に見る夏期講習の目的と注意点
小学4年生:中学受験の土台づくり
この時期はまだ本格的な受験学年ではありませんが、学習習慣を定着させるための大切なタイミングです。ただ、復習部分は範囲も広くなく、自分の子供の苦手分野にピンポイントにフィットしているわけでもありません。結局、悩みはしましたが、私の娘は4年生の夏に夏期講習には参加しませんでした。
小学5年生:差がつき始める時期
この学年は学習内容が一気に難化し、積み残しが致命傷になる時期。夏期講習では、苦手単元の補強がカギとなります。小5の後期は、各教科で特に難しくなっていくと言われており、算数を筆頭に過酷な学習が始まるので、出遅れ分野があるならある程度埋めておく必要があります。ただし、その出遅れ分野が夏期講習で扱われるかは、よく確認しておく必要があります。
小学6年生:受験に直結する実戦強化
6年生は「演習」と「志望校別対策」が主軸。夏期講習だけで数十時間というケースも珍しくありません。特に、8月にはSAPIXの「夏期集中志望校錬成特訓」や、早稲田アカデミーの「NN夏期集中特訓」のような志望校別コースが組まれている塾では、講習をペースメーカーに受験勉強が進む構造になっています。
夏期講習の費用相場と内容の違い
講習費は塾や学年によって異なる
費用は大手塾で4年生が3〜5万円、6年生になると10万円以上になることも。時間数やカリキュラム構成によって大きく異なります。
日数・時間が違うため単純比較できない
例えば、4年生は10日間程度、6年生は20日以上のこともあります。一方で、塾によって日数や1コマあたりの時間も異なるため、表面の金額だけで高い安いは判断できません。
受講するか迷ったときの判断軸
塾のカリキュラム進度を確認する
サピックスのように、塾によっては「夏でカリキュラムが大きく進む」場合もあるので、欠席はそのまま差になってしまいます。進度が早い塾の場合、休むリスクが大きくなります。一方で、早稲田アカデミーや四谷大塚の先取りは部分的であるため、親が指導できるなど状況が許せば、夏期講習の欠席は選択肢の1つとなります。
実際に、私は全生徒に対応しているかのような最大公約数的な復習部分の講義が娘にとっては無駄に感じたため、予習部分は家庭で対応し、復習部分は家で娘の苦手に特化した学習にカスタマイズすることができました。
家庭の予定とのバランス
帰省や旅行などとの兼ね合いも重要です。小学4年生や小学5年生であれば、長期旅行などはまだまだ可能です。学習を無理なく続けられるかはとても大切です。
体力や精神面の余裕も見てあげる
夏は集中力が途切れやすく、疲労もたまりやすい時期。特に高学年になるとスケジュールが過密になりがちなので、体調管理は最優先です。
以前、以下の記事で「参加する?しない?」を考察していますので、参考になれば幸いです。
夏期講習を最大限に活かすための工夫
事前に「目標」を決める
ただ通うだけではなく、「計算を速くする」「理科の暗記を固める」など目的を明確にしておくと成果が出やすいです。そして、それらが夏期講習できちんと達成できそうなのか、それとも家庭でプラス学習が必要なのか、見極めがとても大切です。
講習後の「復習時間」を確保
受けっぱなしにせず、その日の内容をその日のうちに軽く振り返ることが理解定着に直結します。翌日には新しい範囲を扱いますので、溜めてしまうとやっかいです。
保護者の関与の仕方も大事
子どもに受けっぱなしにさせるのではなく、親が興味を持って関わるのは、夏期講習だけではなく、いつもの授業でも大事なポイントだと思います。夏期講習の期間中、毎日チェックするのは大変ですが、子どもがどんなことをやったか話を聞いてあげるだけでも、モチベーションが変わります。
まとめ
夏期講習は、中学受験において学力の底上げや苦手克服の貴重なチャンスです。ですが、すべての家庭にとって「必須」とは限りません。お子さんの性格や学習状況、塾の進度、家庭の予定などを踏まえながら、「わが家にとって意味のある夏」にできるよう、柔軟に選択していきたいですね。
無理をしすぎず、でも必要な負荷はしっかりとかける。そんな「ちょうどいい夏」を見つけることが、受験成功への第一歩になると私は思います。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。