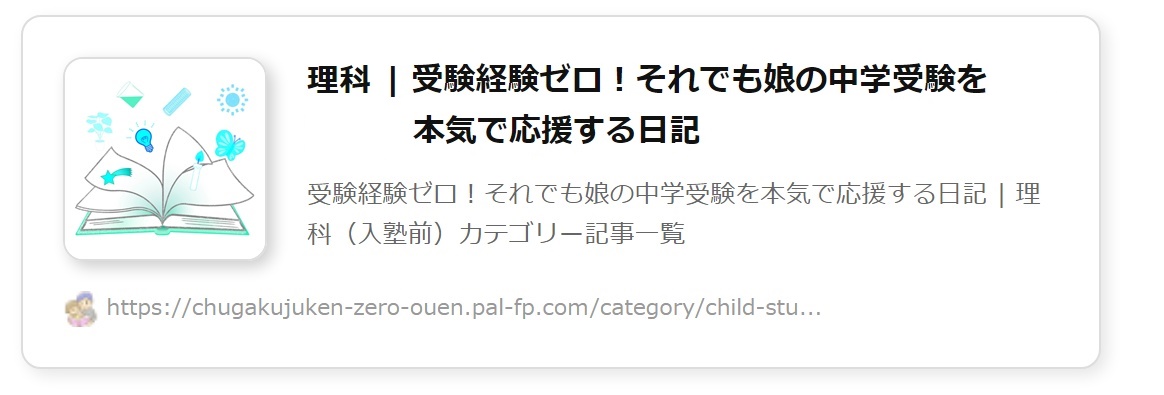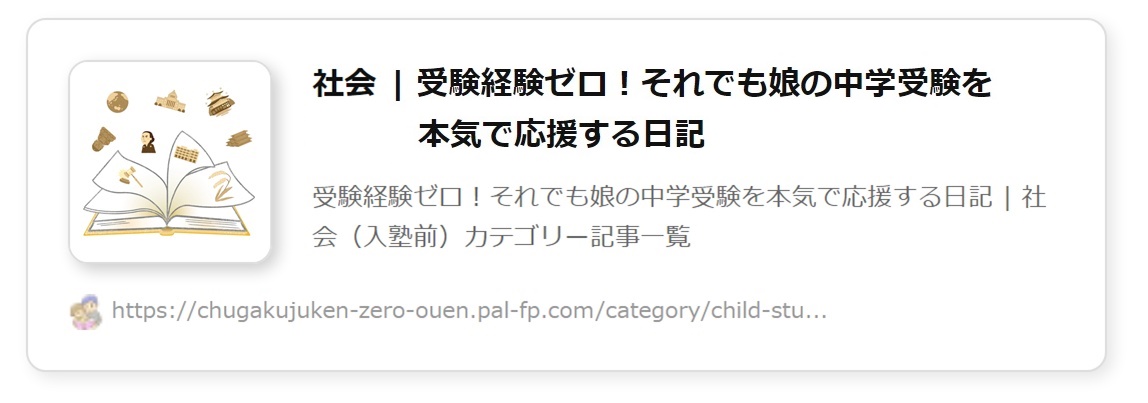6年生から始める“差がつく”理科と社会の復習スケジュール
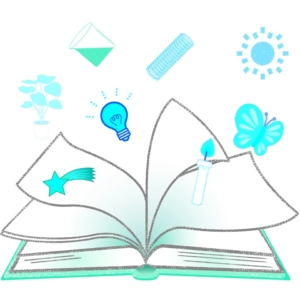
中学受験を意識して学習を進める6年生の家庭にとって、理科と社会の復習スケジュールは合否を左右する重要な鍵になります。「算数や国語に時間をかけすぎて、気づけば理科と社会が手つかずだった…」という声も耳にします。だからこそ、6年生からの理科・社会の学習には“差がつく工夫”が必要です。
この時期から無理なく着実に得点力を伸ばすためのスケジュールづくりのコツを、わが家の体験をもとにまとめてみました。
理社は「後回し」になりやすい理由と向き合う
暗記量が多く、後回しになりがち
理科と社会はどうしても「覚えることが多い」という印象が強く、後回しにされがちです。記述や計算が必要な算数・国語に比べて優先順位が下がってしまうのは自然なこと。でもこの“差”が大きな差になります。
テスト範囲が広く、何から手をつけてよいかわからない
6年生になると模試や演習も増え、「どこから手をつければよいのか」迷ってしまう家庭も少なくありません。範囲が広いからこそ、戦略的な復習計画が重要です。
理社の点数は伸びやすく、差がつきやすい
実は、理科・社会は短期間で得点が上がる科目でもあります。覚えれば点が取れるという特徴を活かせば、十分に逆転が狙えます。
週ごとの復習スケジュールを立てる
1週間単位で「単元」を決める
理科・社会は1日で全範囲を復習するのは無理です。1週間ごとにテーマを決めて、少しずつ取り組むことで無理なく進められます。たとえば「理科:植物の分類」「社会:江戸時代」など、絞って集中するのがコツです。
短時間でも毎日触れる工夫
週末にまとめて勉強するより、平日15~20分でも毎日触れるほうが記憶の定着は高まります。朝の時間や夕食後など、短時間でもルーティンにするのがおすすめです。
確認テストを「週末」に入れる
1週間の復習が終わったら、土日には小テストを行うのがおすすめ。理解度のチェックにもなりますし、「1週間やってきたことが身についている」と実感できて、やる気も上がります。サピックスから市販されている「コアプラス」などの一問一答問題集を使って知識のメンテナンスを図るのもよいですね。
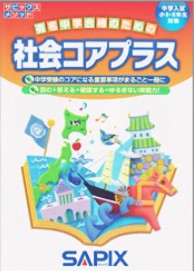 |
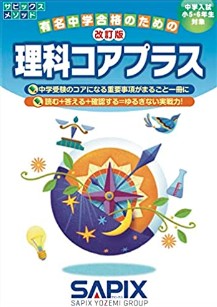 |
暗記だけで終わらせない工夫を取り入れる
問題演習と組み合わせる
暗記だけに頼らず、テキストや問題集の演習を組み合わせることで理解が深まります。特に理科は計算問題や実験問題があるので、演習を通じて「使える知識」に変えることが大切です。
ノートまとめを子どもに任せすぎない
ノートまとめは勉強した気になりやすい落とし穴です。時間だけかかって中身が薄いこともあるため、保護者が時々チェックすることが大切です。色ペンの使いすぎや無意味な装飾には注意。我が家では、親が代わりにまとめを行うこともありましたね。
「説明できるか」をゴールにする
ただ覚えるだけでなく、「この単元は説明できる?」と聞いてみると、記憶があいまいな部分がすぐに見えてきます。家庭での会話を使ってアウトプットの場をつくってあげましょう。
春から夏は秋に向けて「総復習」より「絞り込み」
苦手分野のリストアップをする
すべてを満遍なく復習するのではなく、まずは苦手な単元をリストアップすることが大切です。得点に直結する単元を優先すれば、効率的に対策できます。
出題頻度の高い単元を優先
入試でよく出る単元は、塾のテキストや模試でも何度も登場しています。出題頻度が高い分野から復習することで、得点の安定につながります。
やり直しノートで「復習の軸」をつくる
一度間違えた問題は二度とミスしないように、やり直しノートをつくっておくと便利です。自分だけの「弱点克服帳」があると、直前期の見直しにも使えます。
秋以降は「入試対策」として本格化
過去問分析で傾向をつかむ
秋以降は志望校の過去問を活用し、出題傾向やパターンを分析することが大事です。理社は「傾向の読み取り」が得点力につながります。
時間配分の練習も忘れずに
過去問を使った実戦演習では、時間配分の感覚を身につけることも必要です。特に社会は情報量が多いため、速読・速解の練習が有効です。
一問一答形式で直前対策
直前期は、一問一答形式の暗記アイテムが力を発揮します。スキマ時間に活用し、知識の抜けをなくすための総仕上げとして使いましょう。特に難関校を目指す場合には、サピックスでカリキュラムに含まれているために、サピックス生であれば間違いなく正解してくるコアプラスに掲載されている問題をカンペキにしておくことは、他塾生でも重要と考えられます。
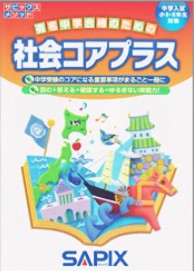 |
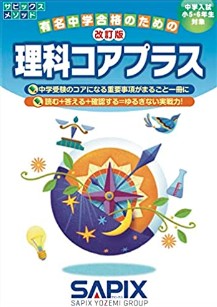 |
まとめ
理科と社会は「後回しにされやすい科目」ですが、だからこそ対策次第で大きな差がつきます。週ごとの計画、毎日のルーティン、出題傾向の分析など、6年生のこの時期から着実に積み上げていくことが合格への近道です。
家庭でできるサポートは「環境」と「声かけ」。お子さんが安心して前に進めるよう、横でしっかり支えていきたいですね。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は、関連記事です。