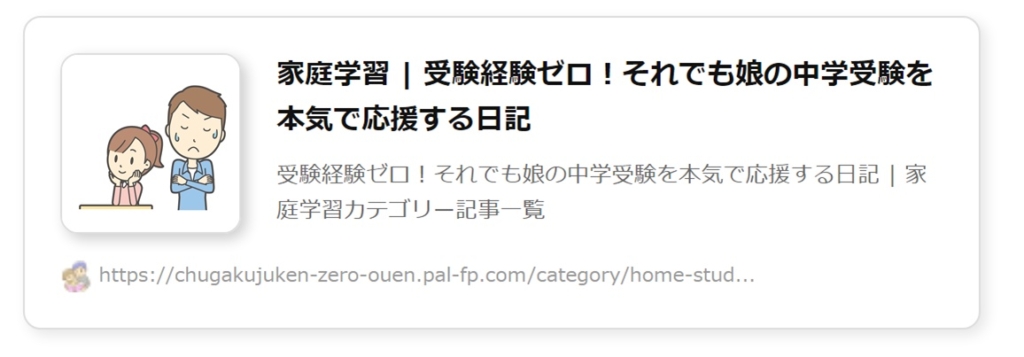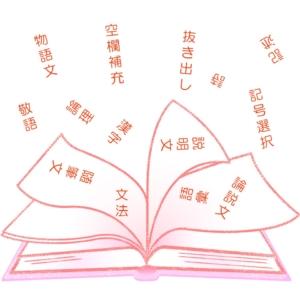中学受験の暗記カード活用法|作り方から使い方まで、家庭でできる効率学習の工夫

中学受験の勉強を進めていくなかで、「暗記」に苦労するご家庭は多いと思います。特に「理科」や「社会」などの知識系科目は、理解よりもまず「覚える」ことが先になってしまうこともありますよね。我が家でも、娘が歴史の年号や地理の県庁所在地に苦戦していたことがありました。
そんなときに役立ったのが、「暗記カード」でした。書店で売られているものもありますし、最近ではアプリやPDFなどのデジタル教材も充実していますが、手作りの暗記カードにも大きなメリットがあります。



この記事では、中学受験における暗記カードというテーマで、作り方・使い方・注意点などを保護者目線で解説していきます。中学受験を目指すご家庭にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
暗記カードとは何か?その特徴とメリット
短時間でも繰り返せる「記憶定着ツール」
暗記カードとは、1枚ごとに1つの情報を記載して繰り返し確認するためのツールです。表に問い、裏に答えを書く形式が一般的です。1枚1枚が独立しているため、苦手なカードだけを重点的に復習することができます。
「作る過程」も学習になる?
自分でカードを作る過程こそが記憶の助けになるという考え方があります。書いているうちに「覚えちゃったかも」ということですね。一方で、作るのは単なる「作業」であり、1枚作る間に、作ってあるものを5枚は見ることができるかもしれず、時間がかかりすぎるのも問題です。
隙間時間の活用に最適
暗記カードのもう一つの魅力は、移動中や待ち時間などの細切れ時間でも使えることです。アプリでも良いのですが、紙のカードのほうが「目が疲れにくい」「手でめくる感覚が記憶に残る」と感じました。
暗記カードの効果的な作り方
ポイントは「1枚1情報」の原則
1枚にたくさんの情報を詰め込みすぎると、逆に覚えにくくなります。「問い」と「答え」がはっきりしたシンプルな構成を意識しましょう。たとえば、「明治維新が起きた年は?」→「1868年」という形です。
カラーとイラストで記憶の補助
視覚情報を追加することで、記憶のフックが増えます。たとえば、「植物の分類」のカードには葉の絵を描いておくと、後で思い出しやすくなります。カラーペンやシールを使って、お子さんと一緒に作るのもおすすめです。一方で、やはり作るのに時間がかかりすぎることには注意が必要です。
項目のグループ化も意識して
理科や社会では、同じジャンルの情報を近いカードにまとめることで知識が体系的に整理されます。たとえば「星座の名前」「季節ごとの星座」など、カード同士のつながりを持たせる工夫も有効です。
サイズと紙質にも注意
カードが小さすぎると文字が書きづらく、大きすぎると持ち運びに不便です。おすすめは好みや何の分野の単語帳を作ろうとしてるかによります。必要十分な大きさがベストで、少し厚めの用紙を使うと、長く使えます。
暗記カードの上手な使い方と習慣化のコツ
毎日の「ルーティン」に組み込む
1日の中で決まった時間にカードを使う習慣を作ると、自然と勉強のペースが安定してきます。我が家では、スキマ時間を使ったり、学習時間を割り当てて暗記タイムとしていました。ルールを決めると、親子ともに継続しやすくなります。
シャッフルと反復で記憶を強化
いつも同じ順番でカードを見ると、順番で覚えてしまうこともあります。ときどきシャッフルして順序を変えながら、「本当に覚えているか?」をチェックすることが重要です。
「できたカード」を分けて自信に
正解できたカードは別の束に分けておくと、子どもが自分の成長を実感できます。これは意外に効果があって、「増えてる!」と嬉しそうにしていました。
家族でクイズ形式にしても楽しい
暗記カードを使って、親子でクイズ形式にすると学習が楽しくなります。お風呂タイムや就寝前に軽く出題し合うだけでも、意外と記憶に残るものです。
暗記カードを使うときの注意点
目的が「作ること」にならないように
熱心に作りすぎて、いつの間にか「カードを作ること」が目的になってしまうことがあります。本来は「覚えるための道具」だということを忘れず、使い方を見直すことが大切です。
書きすぎて小さくなりすぎないように
あれもこれもと書き込みたくなりますが、読みづらいカードは使われなくなってしまいます。字が小さすぎないように、お子さんの視点で見やすさを優先しましょう。
苦手分野を可視化する工夫を
「間違えたカード」には印をつけて、後から集中して復習できるようにしましょう。苦手分野を「見える化」することは、学習の効率を大きく上げます。
教科別の使い分けも大切
社会や理科ではとても効果的な暗記カードですが、国語や算数ではやや使いづらい場合もあります。教科ごとの特性に合わせて、使い方を工夫することがポイントです。
市販・無料・アプリ…暗記カードの選択肢
市販の教材を活用する
市販の「ズバピタ暗記カード」などは、コンパクトで完成度も高く、すぐに使えるのが利点です。ただし、網羅性が十分でなかったり、子どもの苦手に合っていないこともあるので、市販品は「補助的」に使うのがよさそうです。
無料のダウンロード素材も便利
「中学受験 暗記カード ダウンロード」と検索すると、無料で印刷して使える教材も見つかります。ただ、我が家では帯に短したすきに長しな印象で、自作することが多かったですね。
アプリとの組み合わせで効率アップ
最近では、暗記カードアプリも多く出てきています。フラッシュカード形式でテンポよく確認できるものもあり、移動中などには便利です。紙とアプリを併用すると、学習の幅が広がります。一番有名なのは「Anki」でしょう。我が家でも愛用しています。
手作りと既成品のバランスをとる
全てを手作りにするのは大変ですが、「苦手なところは手作り」「得意なところは既製品で確認」というように、家庭でバランスよく使うと効率的です。
中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に
集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。
中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。
例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。
どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
個別指導・オンライン指導を検討している場合
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
家庭教師を検討している場合
一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。
講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。
各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。
中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】
無料の資料請求ページへ
![]()
確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。
ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。
少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。
まとめ
暗記カードは、中学受験に向けて「知識を定着させる」ためのとても強力なツールです。ただ、使い方や作り方を工夫しないと、かえって時間を取られるだけになってしまいます。
私たちもいろいろと試行錯誤をしてきましたが、最終的には「苦手を見える化できる」「自信につながる」「隙間時間を有効活用できる」など、多くのメリットを感じるようになりました。
ぜひ、ご家庭に合ったスタイルで、暗記カードをうまく活用してみてください。子どもの得意・不得意に応じたカスタマイズが、受験勉強の効率を大きく変えてくれると思います。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)