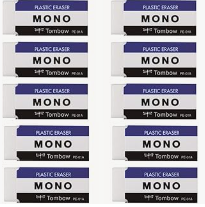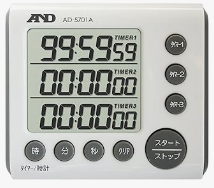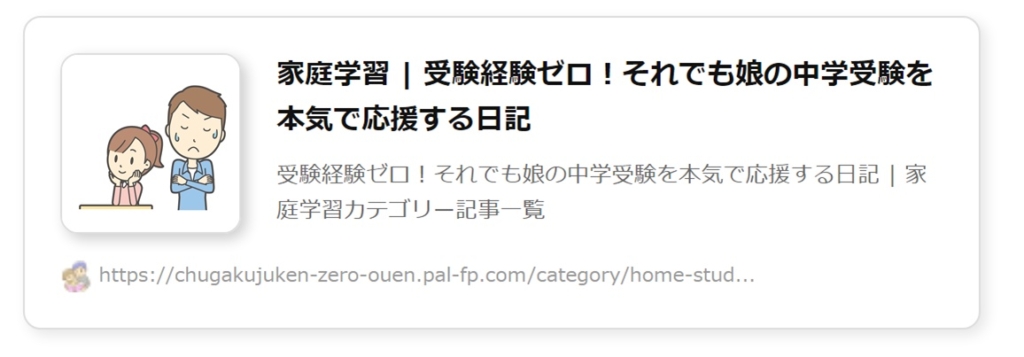中学受験で使える文房具まとめ|えんぴつ派?シャーペン派?我が家の選択とおすすめアイテム

中学受験を本格的に意識し始めたとき、意外と気になるのが「どんな文房具を使えばいいのか?」ということ。日々の学習に使うものだからこそ、子どもの好みや性格、学習スタイルに合ったものを選ぶことが大切だと感じます。



私自身も、娘の中学受験準備を通していろいろな文房具を試しました。「これでなきゃダメ!」という正解はないものの、選び方のコツやよく使われている定番アイテムを知っておくことで、無駄な買い物を減らすことができたように思います。
以下では、中学受験を考えるご家庭にとって役立つ文房具の選び方と、実際に人気のアイテムについてご紹介します。
えんぴつ?シャーペン?中学受験での筆記具事情
小学校では「えんぴつ」が基本。でも塾では?
中学受験の準備が本格化する前は、学校の指導に従って「えんぴつ」一択でした。しかし、塾ではシャーペンを使っている子も多く見かけます。実際、娘も家での家庭学習と塾での学習では、ずっとシャーペンを使っていました。
「二月の勝者」でも言及された、えんぴつ推奨の理由
漫画「二月の勝者」では、「えんぴつで書く方が筆圧がつきやすく、字がしっかり書ける」という理由で推奨されていました。確かに、えんぴつの方がしっかりした文字を書きやすく、記述が多い社会や理科にも向いていると感じます。
シャーペンにもメリットはある
一方で、シャーペンの「芯を削る手間がない」「細かい字が書きやすい」という利点も大きく、計算が中心の算数にはシャーペンが向いているように思います。筆圧が弱いお子さんや、消しゴムで強くこすって破れることが多い場合も、シャーペンの方が扱いやすいでしょう。
結論:お子さんの「使いやすさ」が一番
最終的には、「本人が書きやすい」と思える筆記具を使うのが一番。我が家では、「学校ではえんぴつ、家や塾ではシャーペン」という使い分けに落ち着きました。
消しゴム・定規・付箋…サブ文房具も見直しを
消しゴムは「消えやすさ+力加減」で選ぶ
「消しゴムはどれも一緒」と思われがちですが、力加減や筆圧によって使いやすさが全然違います。試しに手に取ってみるとわかるのですが、硬さが商品によってかなり変わってきます。消しゴムがうまく使えないと、プリントが破れてストレスになるので、子どもに合ったものを探すことは意外と重要です。
定規は図形対策で出番あり
算数の図形問題では、基本的に定規なしのフリーハンドで正確な線を引くことが求められるため、定規の出番は多くはありません。でも、最初からできるわけではないので、それまでは定規の出番もありますね。透明で見やすいものが便利です。
付箋・インデックスは「復習ノート」にも使える
社会や理科の暗記項目では、付箋を活用して目立たせる工夫が効果的です。私は、苦手問題や「明日はここから」の印をつけるのにも活用していました。
文房具ケース・収納も学習効率に影響する?
整理されていないと探す時間がムダになる
意外と侮れないのが、「文房具の収納」問題。毎回、シャーペンや消しゴムを探すところから始まっていては時間のロスが大きいです。
筆箱は「大きすぎず、小さすぎず」
多機能な筆箱が話題になりますが、必要なものをすぐ取り出せるコンパクトなタイプが学習向きだと感じました。娘は、立てられるタイプの布製筆箱を使っていました。
家での収納グッズにもひと工夫
リビング学習をしているご家庭では、文房具をひとまとめにできる収納ボックスやトレーが便利です。100均でも十分使えるものが多くあります。
人気の文房具・買ってよかったアイテム実例
シャープペン:低重心で書きやすいモデルが人気
「デルガード」「クルトガ」「オレンズ」「ドクターグリップ」などが人気です。うちは「デルガード」を愛用していて、芯が折れにくく、グリップ付きのものが使いやすいと娘も言っていました。
消しゴム:MONO vs AIR-IN vs radar
定番の「MONO」「AIR-IN」「Radar」はやはり人気。どちらもよく消えるので、あとは好み次第という印象です。うちでは、子どもによって好みが違うので、それぞれ気に入った「MONO」「AIR-IN」を与えています。
ノート:罫線・方眼どちらがいい?
うちでは、算数も国語も方眼でしたが、科目によって「方眼ノート」と「横罫ノート」を使い分ける選択もありますね。方眼は文字の大きさを揃えやすく、重宝しました。ちなみに、うちでは定番のノートではなくルーズリーフを使っていました。
スケジュール管理:タイマーやTODOメモ
「集中タイマー」や「やることメモ」も意外と役立ちます。特に算数では1問ごとに時間を図って理解度を確認するのにタイマー・ストップウォッチは欠かせませんでした。我が家では、ボタンが大きいタイプと、学習時間+休憩時間の管理に3連タイマーを重用していました。毎日の学習習慣づくりに、可視化できるツールがあると便利です。
我が家の試行錯誤から伝えたいこと
中学受験は、小さな工夫の積み重ねがとても大切だと痛感します。文房具もその一つで、「何を使うか」より「どう使うか」が重要になる場面も多いです。
文房具は、塾の費用や教材の費用に比べれば、数百円で購入できるので、経済面では誤差のようなものです。
私の場合、娘と一緒に試しながらベストを探していく過程が、結果的に親子の信頼にもつながったと感じています。
まとめ
中学受験において、文房具選びは学習環境を整える第一歩です。えんぴつかシャーペンか、消しゴムやノート、収納に至るまで、子ども自身が「使いやすい」と感じるものを選び、学習をサポートしていくことが大切だと実感しました。
実際には、子どもによって合うアイテムは違うので、「みんなが使っているから」ではなく、「うちの子に合っているか」で選ぶ視点が必要です。
限られた時間と集中力を最大限に活かすためにも、文房具選びを「こだわりすぎず、でも丁寧に」行っていくことをおすすめします。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)