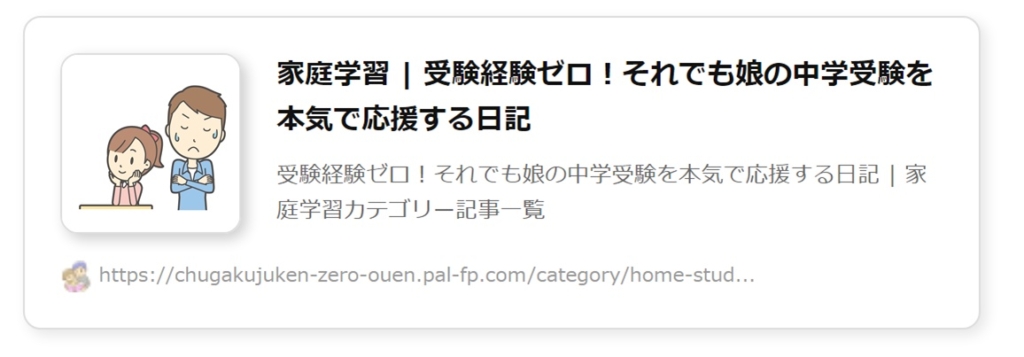小学生から始める!「医者になりたい」夢を叶えるための勉強量と習慣とは?

医師を目指すには相当な努力が必要、というのは誰もが知っていることだと思います。でも「そのスタートって、どこから?」と考えたとき、私自身、娘が「ケーキ屋さんになる!」「お医者さんになる!」「画家になる!」と言い始めた頃から、ないと思うけど一応頭に入れておくか・・・ちょっとずつ調べるようになりました。



正直なところ、小学生から「医者になりたい」と思っていても、それが本当に必要な努力の量に結びつくとは限らない。でもだからこそ、親が知っておくことでサポートの形も変わってくると思います。
今回は、「医者になるにはどのくらいの勉強量が必要なのか?」を小学生の段階から考え、実際にどのような取り組みが求められるのか、調べたことをまとめてみました。ちなみに、中学受験を終えた娘は、無事に「医師になりたい!」な気持ちは綺麗サッパリなくなっているようです。
医師を目指すために必要なステップとは?
医学部入試は何を求めているのか?
医学部の入試は全国的に見ても難関で、偏差値が高く、求められる学力レベルは最上位です。受験科目には理系科目が多く、「数学」「理科(二科目)」「英語」などが必須です。
つまり、中学・高校でこれらの科目をしっかり身につけておく必要がある。そのためには、「中学受験で進学校に入る」というのが、ある意味、医師への第一歩とも言えます。
小学生の時点で何を意識すべき?
小学生の段階では、勉強量そのものよりも「習慣」と「基礎の定着」がポイントになります。「毎日勉強することが当たり前」という生活を自然に身につけられるかどうかが、のちの学習を大きく左右します。
中学受験を視野に入れた準備
中学受験を目指す場合、小学4年生頃から1日2〜3時間程度の勉強が必要とされています。もちろん、学校の宿題に加えての時間です。医学部進学を本気で考えるなら、「中堅以上の私立中学への進学」も視野に入れておきたいところです。
小学生が必要とする「勉強量」の目安
学年ごとの勉強時間の平均
文部科学省などの調査をもとにすると、学年ごとの1日の勉強時間は以下のようになります。
- 小学1〜2年生:30分〜1時間
- 小学3〜4年生:1〜2時間
- 小学5〜6年生:2〜3時間
ただし、医学部を目指す家庭は、平均よりやや多めの学習時間を確保している傾向があるようです。医学部に入るためというよりも、自然と難関校・超難関校を目指す家庭が多くなり、勉強時間も長めとなるということかなと思います。
中学受験塾に通う場合の学習量
進学塾に通っている場合、学年にもよりますが授業だけで週2〜3日・1日3時間前後、宿題や復習を入れると、週20時間以上が標準です。さらに、医学部を意識するなら、この負荷に耐えられる学習体力を小学生のうちから作っておくことがカギです。中学受験で燃え尽きているようでは話にならず、中学生になってからも学校の勉強以上が求められることは間違いありません。
モチベーションを維持するコツ
「目標がある」ことの強さ
小学生にとって「お医者さんになりたい」というのは、強いモチベーションになります。大人が「そんなの無理」とか「今からじゃ遅い」と言ってしまうと、せっかくのやる気を削いでしまいます。
興味を持たせる環境づくり
我が家では、子ども向けの医学図鑑や人体模型のキットを用意しました。「これが体の中なんだ!」と興味を持ち始めてから、理科の学習もスムーズになった気がします。
「ごっこ遊び」から本気に変わる瞬間
お医者さんセットで遊んでいた娘が、ある日「血ってなにでできてるの?」と聞いてきたとき、「この子、本気で知りたいんだな」と感じました。遊びの中から生まれる知的好奇心を、うまく学習につなげてあげるのが親の役目かもしれません。
医者になるにはどんな力が求められる?
暗記力だけでなく「論理的思考力」
医学部入試では、膨大な知識を正確に暗記する力と同時に、それを活用する「論理的思考力」や「記述力」も求められます。これは小学生時代から「説明する練習」などで身につけることができます。
継続する力=習慣化の力
毎日コツコツ続ける力は、医学部に合格する生徒に共通している特徴です。習慣化の力は一朝一夕では身につかず、小学生の頃からの積み重ねが重要です。
家庭でできる訓練とは?
- 毎朝の復習
- 簡単な日記で文章力アップ
- 家族で「なぜそうなるのか」を話す時間を持つ
など、小さな習慣の積み重ねが大きな差になります。
医師になる夢を支える家庭の役割
無理をさせすぎないことも大切
小学生の段階では、「勉強=嫌なもの」になってしまうと逆効果です。ゲーム感覚で取り組めるドリルやアプリの活用もおすすめです。
中学・高校の情報収集は早めに
娘の「お医者さんになる!」発言を真に受けて、私も中学・高校・大学受験の情報をざっくり調べました。小学生の親だからこそ、全体の流れを把握しておくことで、無駄な焦りが減ります。
勉強以外の力も育てる
「人の話をよく聞く力」「やり抜く力」「感情のコントロール」なども、医師には欠かせない要素です。お手伝いやボランティア、読書の習慣などでバランス良く育てたいと思っています。
オンラインでもできる、中学受験向けの立て直し
地方在住や送迎の都合で通塾の選択肢が限られる場合でも、オンラインで中学受験対策を進めることは可能です。
塾フォロー型の個別指導(オンライン対応)という選択肢があります。
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中で公式情報や条件を確認した限り、候補の1つとして比較対象に入れやすい印象で、資料を取り寄せておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
SS-1では無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
例えば、成績が伸び悩んでいる・苦手がいつまでも苦手なまま…などの悩みが出始めているなら、個別指導を検討し始めてもよいかもしれません。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
体験談も参考になりますが、私自身はまず公式資料を正しく理解することが大切だと考えています。
子どもが頑張っているからこそ、親も判断材料を集めるという形で一歩進めておくと安心です。
まとめ
医師になるための道のりは長く、厳しいものです。でも、小学生のうちから意識しておくことで、その準備は着実に始められると思います。大切なのは、「勉強量」そのものよりも、それを無理なく積み重ねられる習慣と環境づくりです。
我が家でも、娘の発言をきっかけにいろいろ調べるようになりましたが、今は「その夢を応援する方法」を少しずつ見つけている段階です。これから医師を目指すお子さんと保護者の方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)