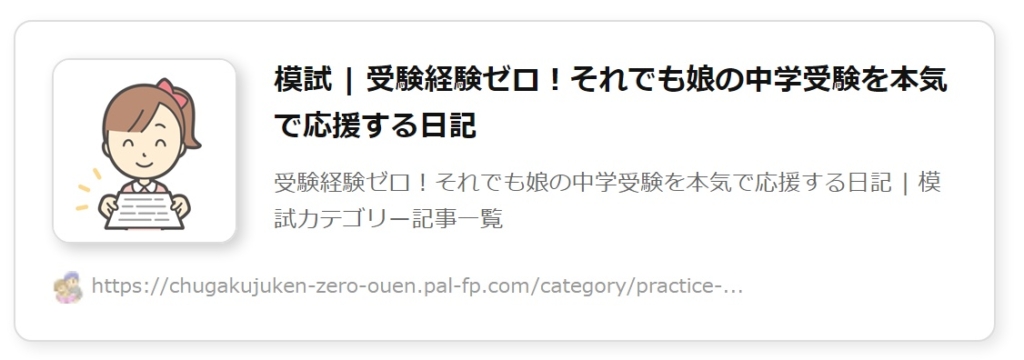組分けテスト後の正しい復習法|成績アップにつながる見直しポイント!

組分けテストの結果が返ってくると、つい「良かった」「悪かった」と一喜一憂してしまいがちです。でも、本当に大切なのは、その後どう行動するか。結果を受け止めて、正しく復習し、次につなげることができれば、着実に成績アップにつながります。



ここでは、親目線でできるサポートも含めて、具体的な復習方法をご紹介します。
組分けテスト後の復習が重要な理由
本番に向けた実力を確実に積み上げるため
テストは単なる通過点。結果よりも、「できなかったことをどう克服するか」が成績アップの鍵になります。
苦手分野を客観的に把握できる
できなかった問題を振り返ることで、「何がわかっていなかったのか」がはっきりと見えてきます。これを見逃さないことが大切です。
テスト慣れとメンタル強化にもつながる
テストを受けるたびに適切な振り返りをすることで、本番に向けて精神的にもタフになっていきます。
復習のタイミングと進め方
テスト翌日までにざっくり振り返る
受けた直後の記憶が新しいうちに、「できた問題」「できなかった問題」を大まかに整理しておきましょう。
正答率の低い単元から優先的に
科目ごとの成績表を見ながら、特に間違いが目立った単元から集中して復習するのが効果的です。
完璧主義にならずポイントを絞る
すべてをやり直そうとすると挫折しやすいので、「特に大事な単元」「よく出る分野」に絞って復習を進めましょう。また、時間には限りがあるもの。お子さまの現状の成績と目標、そして正答率を参考にしながら、復習するポイントを絞りましょう。
科目別・効果的な見直しポイント
算数は「なぜ間違えたか」の分析が命
計算ミスか、解法の理解不足か、間違えた原因を具体的に分析し、それぞれに合った対策を立てることが重要です。ミスなのか、典型問題に対応できていないのか、それとも思考力問題で落とすのか、対策はそれぞれ異なります。
国語は設問ごとに読み取りミスを検証
記述問題や選択肢問題での間違いを見直し、「問題文のどこを読み違えたのか」をしっかり確認しましょう。国語で点を取れない場合、問題にかかわらず、そもそも本文をまともに読めていないことが多々あります。
理科・社会は知識の抜けを補う
用語を覚えていなかった、内容をあいまいに理解していた、など、知識の不足を補う勉強を優先しましょう。ゆくゆくは大事になってきますが、考える力の前に知識の不足を何とかする必要があります。
間違えた問題の扱い方
その場で必ずやり直す
間違えた問題は放置せず、必ず一度自力で解き直しをして、理解できたか確認しましょう。
間違いノートを活用する
間違えた問題をノートにまとめ、「どこでつまずいたか」「どうすればできたか」を書き込んでいくと、後の復習に役立ちます。
\ 毎月、新たに多くの方が復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
同じ単元の別問題に挑戦する
理解が不十分だった単元については、他の問題集やテキストで追加演習をすることで、より知識が定着します。
親ができるサポートとは?
結果よりもプロセスを重視して声かけする
「点数が悪かったね」ではなく、「どこが難しかった?一緒に見直してみよう」と前向きな声かけを意識しましょう。
復習の計画を一緒に立てる
子ども任せにせず、「今週は算数のこの単元を復習しよう」と具体的に計画を立ててあげると、取り組みやすくなります。
落ち込んだ気持ちを受け止める
テストの結果にショックを受ける子も多いもの。感情を否定せず、「次に活かそうね」と寄り添う姿勢が大切です。
まとめ
組分けテスト後の復習は、成績アップのために欠かせないプロセスです。ただの「やり直し」で終わらせず、「なぜ間違えたのか」「どうすればできるようになるか」に向き合うことで、大きな成長につながります。親としては、子どもが前向きに振り返りに取り組めるよう、温かくサポートしていきたいですね。小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな自信に変わります。
\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は参考記事です。