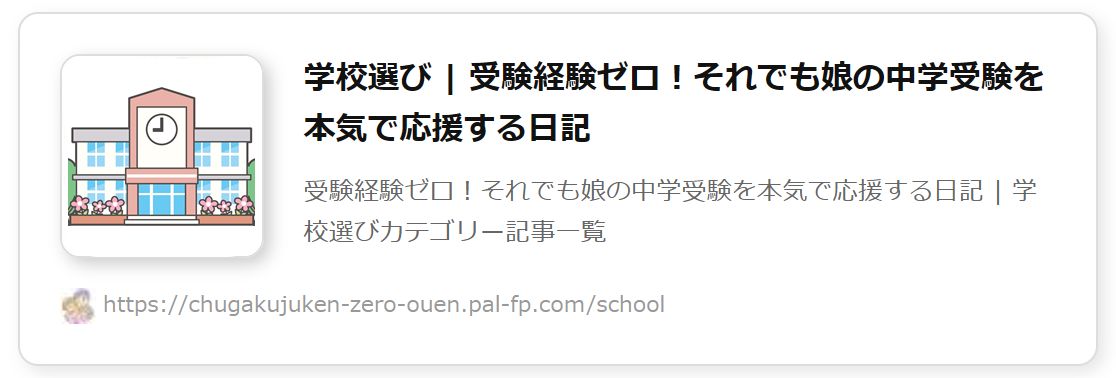中学受験の志望校はどう決める?失敗しない決め方と親子で考える5つの基準

中学受験を考え始めたとき、多くのご家庭が最初に悩むのが「志望校の決め方」です。私も娘が小4の頃、塾に通い始めてしばらくは「どこの学校が向いているんだろう?」と、具体的なイメージが湧かずに悩んでいました。偏差値や進学実績だけを見て選ぶのは不安だけれど、全く無視してもいいのか? そんなふうに、バランスの取り方が難しいと感じている方は多いと思います。



この記事では、「中学受験 志望校 決め方」をテーマに、親としてどのような視点を持ち、子どもと一緒にどう話し合いながら進めていくべきかを、実体験も交えながら詳しく解説していきます。
志望校選びの基本的な考え方
志望校選びはいつ始める?
志望校選びは、小4~小5の間に少しずつスタートするのが一般的です。いきなり「この学校にしよう!」と決める必要はなく、まずは複数の学校を知ることが大切です。文化祭や説明会に足を運び、校舎の雰囲気や生徒の様子を見て、「この学校、いいな」と感じる感覚を親子で共有しましょう。
偏差値だけで選ばない
偏差値は、あくまで「目安」でしかありません。もちろん入試対策や合格可能性の判断には必要ですが、それだけで決めると「入学後のミスマッチ」に繋がることも。「偏差値が高いからすごい」と思っていた学校に実際に行ってみたところ、「雰囲気が合わない」と感じて、候補から外しました・・・という話もよくあることです。
将来の進学実績や教育方針も確認
将来の進路を見据えて、高校・大学の進学実績もチェックするのは重要です。一部の中学校を除いて、合格者偏差値と進学者偏差値の乖離から、偏差値ほど大学進学実績がよくないように見える、ということはよくあります。
また、「中高一貫の一貫教育」「英語教育重視」「探究型授業」など、各校の教育方針が子どもの性格や興味に合うかどうかを見ておくと、ミスマッチを防げます。
志望校を決めるときの5つの基準
① 校風と子どもの性格の相性
「自由な校風」「厳しめの校則」「のびのび系」など、学校の空気感はさまざまです。大人が見てよい学校でも、子どもにとって合わない場合があります。実際に足を運んで、生徒の様子や授業の雰囲気を見て判断しましょう。
② 通学時間・通学手段
毎日の通学は、意外と大きな負担になります。1時間以上かかると、朝の起床時間や帰宅後の勉強・生活リズムにも影響します。電車の乗り換え回数や混雑具合も含めて、「6年間通えるか」をしっかり考えておくことが大切です。
③ 入試傾向や出題形式の相性
学校によって、「記述力重視」「計算スピード重視」「応用力重視」など入試傾向が異なります。塾の模試や過去問を通じて、子どもが得意とするタイプの出題かどうかを見て、受けやすい学校を選ぶことも一つの戦略です。
④ 家庭の教育方針と一致しているか
学校ごとに「自立支援型」や「管理型」など、教育方針に違いがあります。家庭で大切にしている価値観と学校の指導方針が合っているかどうかも、長い目で見たときに重要になります。
⑤ 費用面や兄弟関係
私立中は特に入学金や授業料の負担が大きくなります。また兄弟姉妹とのバランスや、将来的な教育費も見越して、無理のない選択を心がけることが必要です。経済的な継続性も志望校選びの一部だと思います。
志望校リストの作り方と見直しのタイミング
「本命」「実力相応」「安全校」を分けて考える
1校だけでなく、「チャレンジ校」「実力相応校」「安全校」のバランスを取って複数リスト化しましょう。模試の成績や判定も活用して、現実的な合格可能性を見極めることが大切です。
模試結果や塾面談を活かす
模試結果や塾との三者面談では、客観的なデータやアドバイスを得られます。「合格判定」だけでなく、志望校に合った学習法や弱点の分析もできるので、志望校選びの参考になります。
定期的に志望校を見直す
子どもの成長や学力の変化によって、志望校も変わっていきます。長女のとき、小5の終わりから小6のはじめにかけて、志望校を変更しました。最初の印象で決めたままにせず、半年ごとに見直すくらいの柔軟さがあってもよいと思います。
志望校選びでよくある失敗とその回避法
親の希望だけで決めてしまう
「親の母校だから」「進学実績がいいから」など、親の意向だけで決めると、子どもとの温度差が生まれます。最終的に通うのは子どもなので、「子どもがどう感じたか」を一番大事にしたいですね。
他人と比較しすぎてしまう
「〇〇ちゃんは〇〇中に合格した」など、周囲の情報に流されて志望校を決めるのもNG。大切なのは「自分の子どもにとってベストな学校かどうか」です。他人と比較せず、自分たちの軸で判断しましょう。
志望校に固執しすぎて視野が狭くなる
1校だけに絞ってしまうと、仮に不合格になったときのダメージが大きくなります。本命校があるのはよいことですが、セーフティネットとして複数校を受けることを前提に動いておくと、心にも余裕ができます。
まとめ
「志望校の決め方」は、正解が一つではないからこそ難しいと感じるものです。偏差値や進学実績などの「数字」も大切ですが、最終的には「その学校に通って子どもがどう成長できるか」を重視する視点が欠かせないと思います。
私自身も、初めての中学受験で迷いながら進めてきましたが、何度も話し合い、見学に行き、少しずつ見えてきたものがありました。ぜひ焦らず、子どもの性格や成長に寄り添いながら、最適な志望校選びをしていきましょう。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)