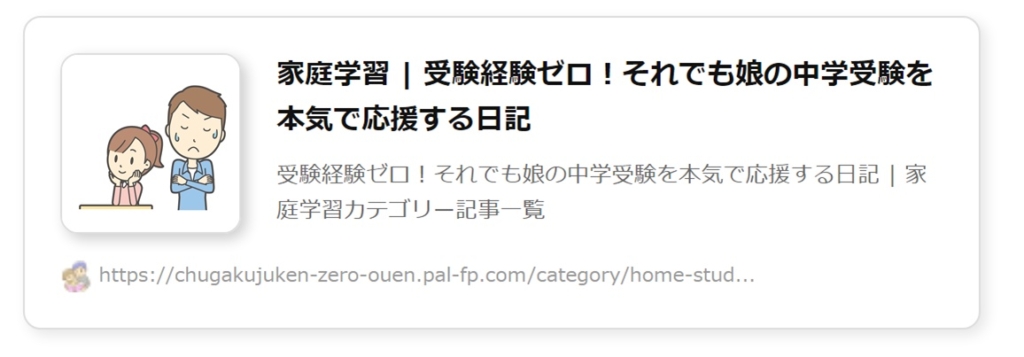中学受験の勉強スケジュールはどう立てる?親の関わり方のリアルな実例つきガイド

中学受験を目指すとき、避けて通れないのが「勉強スケジュール管理」です。志望校に向けてやるべきことは山のようにありますが、それらをいつ、どのように進めるのかを計画するのは、思っている以上に難しいものです。
ネットや本では「自立学習」「自走型」といったキーワードが目立ちますが、小学生が自分で全体のスケジュールを立てて、柔軟に修正しながら進めるのは、正直ほぼ不可能だと思います。
実際、我が家では、長女のときは親である私がすべて管理していました。6年生から手放してみたこともありましたが、一部の教科で成績が大きく落ちてしまい、結局また全面的に伴走することに戻しました。結果的には、それでやむを得なかったと思っています。



この記事では、中学受験における勉強スケジュールの立て方の基本と、年間・月間・週間の具体的な例、さらに親がどこまで関わるかという現実的なラインまで、実体験ベースで詳しく紹介します。
中学受験のスケジュール管理がなぜ重要なのか
学習内容が膨大だからこそ、計画が必要
中学受験では、算数・国語・理科・社会の4教科をそれぞれ深く学ぶ必要があり、塾の進度に合わせて家庭学習もこなさなければなりません。その量は学校の勉強とは比較になりません。
計画なしでは、抜け漏れが出たり、直前期にパニックになってしまう可能性が高いです。
計画を立てることで親も子も安心できる
見通しが立つと、子どもは「今やっていることがどこにつながっているか」がわかり、モチベーションも維持しやすくなります。親としても、「今週はどこをフォローすればいいか」が明確になります。
私自身、スケジュールを「見える化」してから、娘との会話や勉強の進捗確認がぐっと楽になりました。
「自走」への道筋としても計画は有効
6年生になると、「そろそろ自分で管理を…」と思いがちですが、いきなり全部を任せてしまうと、逆に混乱してしまうケースもあります。最初は親が管理し、徐々に役割を子どもに移すことが、結果的には自立への近道だと感じています。
私の場合、冒頭で紹介したとおり、長女任せにしたら一部の教科の成績が下がってしまいました。そこで、6年生の1年間は、自立してもらうのではなく、中学生になったら自立できるように、計画の立て方などを説明するようにしました。
年間スケジュール:受験までの大きな流れをつかむ
4年生:学習習慣の定着と基礎の徹底
塾に通い始める家庭が多い4年生。この時期は「基礎を楽しく続ける」「生活リズムを整える」ことが目標です。詰め込みすぎず、学校と塾の両立を意識しましょう。
年間スケジュール表では、夏休み・冬休みの「学習強化ゾーン」と日常の「学習習慣ゾーン」に分けて整理すると、親も管理しやすくなります。
この時期から、年間計画を月間・週間レベルまでブレイクダウンしておくと、学年が上がってからも慌てずにすみます。
5年生:各教科の基礎応用をバランスよく
ボリュームが増える5年生。算数は特に重要単元が多く、積み上げ式なので年間で抜けが出ないよう要注意です。社会や理科も暗記だけではなく「理解」を重視。
4年生は1回の学習範囲も広くなく、また、難易度もそこまで高くないため、細かい計画を立てなくても成り行きでスムーズに学習を進めることは可能かもしれません。しかしながら、この時期から月間・週間レベルを考えるようにしていかないと、学習を進めることが厳しくなってくるのではと思います。。
6年生:演習・過去問・志望校対策の総仕上げ
いよいよ勝負の年。年間の前半は弱点補強と演習、夏休み以降は過去問演習と志望校対策に全振りすることになります。
我が家でも、6年生の年間計画は大きな模造紙に書き出し、冷蔵庫に貼って管理していました。「今はここをやってる」と一目でわかることで、娘も前向きに取り組めていました。
月間スケジュール:塾のペースと家庭の予定を調整
塾のカリキュラムと模試日程をまず書き出す
中学受験の塾は、非常にスピーディに単元が進みます。まずは塾のテキスト・テスト範囲・模試スケジュールを1ヶ月単位で書き出しましょう。
我が家では、塾からもらった年間スケジュールをもとに、毎月「月間計画表」をエクセルで作成していました。
家庭行事・体調管理も月単位で見通す
意外と見落としがちなのが、家族旅行・学校行事・習い事の発表会などのイベント。事前に把握しておけば、学習量の調整ができます。
また、疲れやすい時期(特に梅雨や冬)は「ゆとり週」を意図的に設ける」のもおすすめです。ある程度マージンをもたせるようにしないと、体調不良で勉強できない日ができた瞬間に計画が破綻しかねません。
月の「重点教科」を明確にする
すべての教科を毎月同じ熱量でやるのは難しいので、今月は算数を厚く、来月は理科を強化…などと重点教科を決めると効率的です。
私は、「過去の模試結果+塾の先生のコメント+親目線」で、毎月の重点を決めていました。
週間スケジュール:習慣と効率のバランスを
「塾のある日」と「ない日」で構成を分ける
週の中で、塾がある日・ない日・復習日に分けて、曜日別にルーティン化すると、子どもも混乱しにくくなります。特に、塾の翌日は「復習重視の日」にする」ことで定着が良くなりました。
1週間単位で「何を終わらせるか」を具体化
抽象的な予定よりも、「算数プリント3枚」「社会の一問一答100問」などの具体的なタスクに落とし込むことが、実行率アップのコツです。
娘にも「今日のToDo」として見せていましたが、チェックリスト形式にするとゲーム感覚で進めてくれました。
日曜に1週間の振り返り&次週の調整
スケジュールは「立てっぱなし」では意味がなく、日曜日に5~10分で簡単に振り返りをして、次週に微調整する習慣がカギです。
私たちの場合、「1週間のがんばりを確認する時間」を作っていましたが、本人の自己肯定感アップにもつながっていたと思います。
親の関わり方:どこまで伴走するかのリアル
小学生が自走するのは、正直難しい
中学受験に関する書籍では、「自立」「自走」がキーワードになっていますが、現実的には親の伴走なしではスケジュール管理は破綻すると私は思っています。
特に、習い事・体調・学校行事なども絡む中で、子どもがすべてを見通すのは無理があります。
伴走しすぎのリスクもある
とはいえ、親がすべて決めすぎてしまうと、中学生以降の「自分で考えて動く力」が育ちにくいのも事実です。うちも、6年生から娘に任せてみましたが、成績が急落した科目もあり、反省しました。
その後は「中学受験中は親が管理する」と割り切りましたが、中学に入ってから半年ほどで、自然と自走できるようになってきたので、段階的な移行が大切だと感じています。
家庭ごとに「伴走ライン」を決める
最も重要なのは、家庭ごとの方針を明確にしてブレないことです。スケジュール管理だけは親がやるのか、一部任せるのか、最終判断は家庭内で調整しましょう。
まとめ
中学受験の成功は、単なる努力だけではなく、「計画的なスケジュール管理」と「親の適度な伴走」があってこそ成立すると感じます。
特に、小学生が自分で勉強をコントロールするのはハードルが高いため、保護者の支援が不可欠です。ただし、子どもの成長段階に応じて少しずつ手放していく視点も持ちながら、柔軟に対応していくことが求められます。
年間・月間・週間のスケジュールを見える化し、家庭全体で共通認識を持つことが、受験期のストレス軽減にもつながると実感しています。
それぞれの家庭にとって「ちょうどいい」計画と関わり方を、少しずつ見つけていきましょう。
\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介し始めました。
Follow @zeropapa_jukenTweets by zeropapa_juken