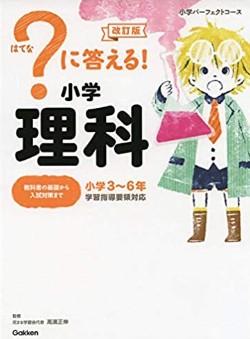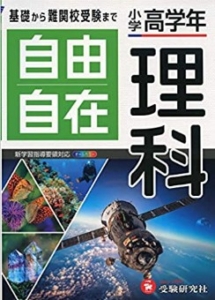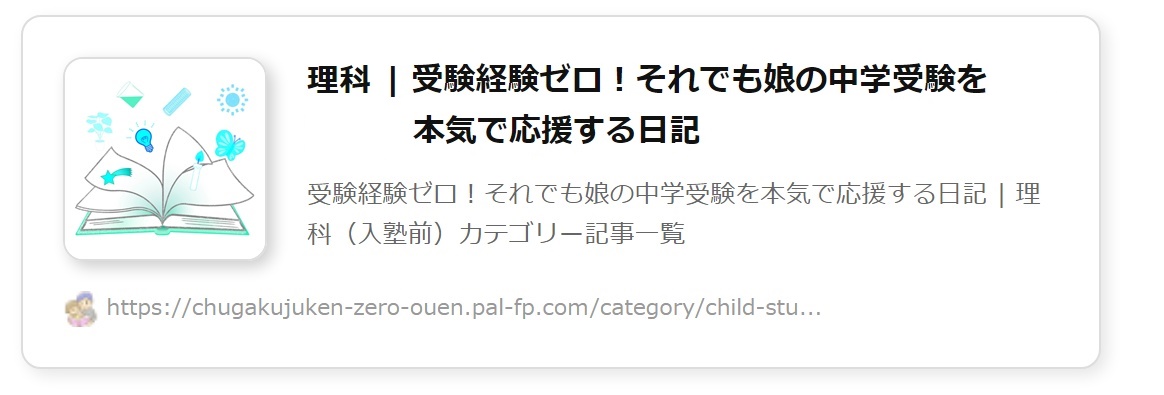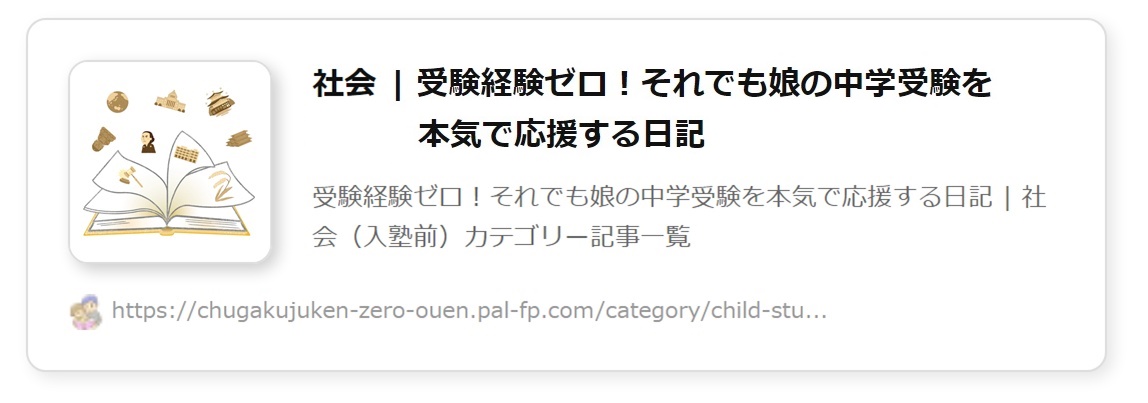中学受験の理科・社会はいつから始める?後回しが危ない3つの理由と始めどきの目安
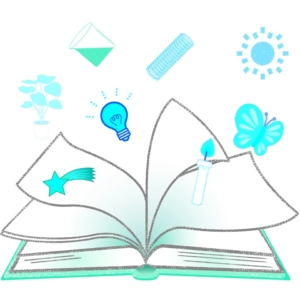
中学受験を目指す家庭にとって、理科・社会の学習開始時期は大きな悩みの一つだと思います。特に算数や国語の重要性が強調される中で、理社を後回しにしても大丈夫なのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。私自身も、子どもが5年生に進級した頃に「そろそろ理社も本格的に始めた方がいいのでは?」と焦った記憶があります。



この記事では、理科・社会を後回しにするリスクと、始めどきの目安について考えてみたいと思います。
理科・社会を後回しにするリスクとは?
知識の積み上げが間に合わない可能性
理科や社会は暗記科目と捉えられがちですが、実際には知識の積み上げが重要です。特に理科では、4年生で学ぶ基礎的な内容が5年生以降の学習に直結しており、後回しにすると理解が追いつかなくなることがあります。社会でも、地理や歴史の基本的な流れを早めに把握しておくことで、応用問題への対応力が養われます。
思考力を問う問題への対応が難しくなる
近年の中学受験では、単なる知識の暗記だけでなく、思考力や分析力を問う問題が増えています。例えば、理科では実験結果の考察やグラフの読み取り、社会では資料の分析や時事問題の理解が求められます。これらの問題に対応するためには、早い段階からの訓練が必要です。
他教科とのバランスが崩れる
理社を後回しにすると、6年生になってから急いで詰め込むことになり、他教科とのバランスが崩れる恐れがあります。特に算数や国語の学習時間が削られることで、全体の成績に影響を及ぼす可能性があります。「6年生の夏からで良い」のような話も見聞きしますが、そのころには過去問に取り組み始める時期ですし、何よりも最優先となる算数を差し置いて理社の時間を確保するのは現実的でありません。
理科・社会の学習を始めるタイミング
新4年生からのスタートが理想的
多くの塾では、新4年生(小学3年生の2月)から理社の授業が始まります。この時期から後回しをせずに、きちんと授業やテストと向き合って本格的に取り組むことで、基礎から応用へと段階的に学ぶことができ、無理なく知識を定着させることができます。私の子どもも、新4年生2月の入塾の最初から6年生の最後まで理社を軽んじることがなかったこともあり、比較的安定した成績を取ることができました。
遅くとも5年生の夏までには本気を出す
5年生の夏までに理社の学習としっかり向き合うことが必要です。この時期を過ぎると、出題範囲が広がり、短期間での習得が難しくなるため、計画的な学習が求められます。また、算数がグッと難しくなって振り落とされる子が増えるのも5年の後期です。その時期から理社を本格的に取り組もうという計画、本当にうまくいくでしょうか?
興味を持たせる工夫も大切
ところで、理社の学習はなにも入塾開始以降からでない理由はありません。低学年のうちに、理科や社会に興味を持たせることが重要です。例えば、博物館や科学館への訪問、図鑑や学習漫画の活用など、楽しみながら知識を増やす工夫が効果的です。私の場合は、子どもと一緒に地図を見ながら旅行の計画を立てることで、地理への関心を高めることができました。
理科・社会の学習を進める上でのポイント
繰り返し学習で知識を定着
理社の学習では、繰り返し学習が効果的です。一度覚えた内容でも、時間が経つと忘れてしまうことがあるため、定期的な復習が必要です。特に、まとめ教材や問題集を何度も解くことで、知識の定着が図れます。サピックスから市販されているコアプラスであれば、評判がダントツですので、迷うことなく進められますね。
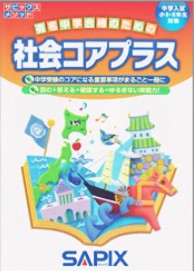 |
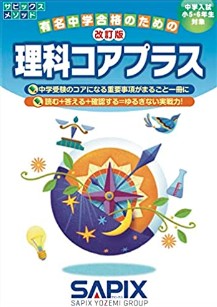 |
苦手分野の克服に重点を置く
理社の学習では、苦手分野の克服に重点を置くことが効果的です。自分の苦手な単元を把握し、重点的に学習することで、全体の成績向上につながります。私の子どもも、理科も社会も、予習シリーズだよりではなく、市販の参考書である「?に答える!」と「自由自在」も使いながら知識の幅を増やしつつ、繰り返し学習することで、苦手分野を克服することができました。
理社の参考書はいくつか出ていますが、この2冊は、私が書店で見比べてお互いを補完しあえて良いとこ取りをできると判断して選んだ、おすすめの参考書です。「いやいや、1冊で十分・・・」ということであれば、「?に答える!」がわかりやすく見やすく、また、相対的に私と子が参考にすることが多かったので、イチオシです!
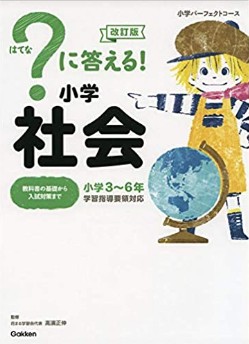 |
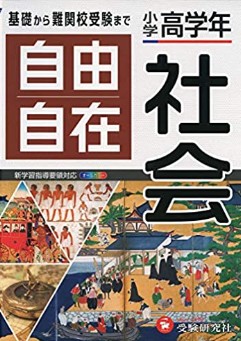 |
過去問の活用で実践力を養う
6年生になったら、過去問を活用して実践力を養うことが重要です。過去問を解くことで、出題傾向や自分の弱点を把握し、効率的な学習が可能になります。ただし、古い過去問ばかりに頼らず、最新の出題傾向にも注意を払うことが大切です。
まとめ
中学受験において、理科・社会の学習は後回しにせず、早めに取り組むことが成功への鍵だと思います。新4年生からのスタートが理想的ですが、遅くとも5年生の夏までには本格的な学習を始めることが望ましいとされています。繰り返し学習や過去問の活用、苦手分野の克服など、計画的な学習を心がけることで、理社の成績向上につながると思います。私自身も、子どもの学習をサポートする中で、早めの取り組みの重要性を実感しました。ぜひ、理科・社会の学習計画を見直してみてはいかがでしょうか。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は、関連記事です。