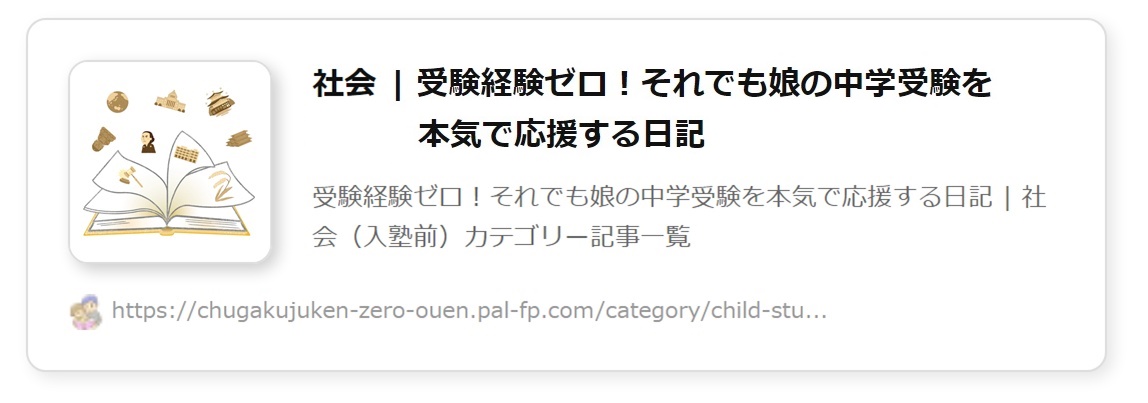予習シリーズ社会の活用法|学年別特徴と家庭学習で伸ばすコツ

中学受験を目指すご家庭にとって、算数や国語と並び重要な科目が社会です。その社会の学習で、四谷大塚の「予習シリーズ社会」は多くの塾や家庭で利用されています。カラフルな紙面と体系的なカリキュラムが魅力ですが、実際のところ学年によって構成や難易度は大きく変化します。



私自身、娘の学習でこの教材を使ってきましたが、「4年生の安心感」から「5年生の情報量ラッシュ」へのギャップには驚かされました。この記事では、学年別の特徴や注意点、家庭学習での工夫、そして他塾教材との違いまで、実際の使用感を交えながら詳しくお伝えします。
学年別の予習シリーズ社会の特徴と学習のポイント
4年生:社会の世界への入り口
4年生の予習シリーズ社会は、1回分が6ページ構成。テーマは地理で、都道府県や自然地形、気候など、身近で興味を持ちやすい題材から始まります。
図表と写真が豊富な理由
この学年の特徴は、カラー写真やイラストの多さです。子どもは文章よりも視覚情報からの理解が得意なので、川の流れや地形、農作物などもイメージしやすくなっています。
多くの回で、写真と地図が並び、視覚的に理解できます。この段階で「社会って面白い」と感じられるかどうかは、その後のモチベーションに直結します。
落とし穴:「これだけで十分」ではない
4年生の範囲はあくまで基礎。基礎はとても大事ではありますが、入試に求められる細かい知識はあまり含まれていません。娘も当時は「テストも簡単だし余裕」と思っていましたが、5年生に上がったとたん情報量に押しつぶされそうになりました。ここでの対策は、興味を持った分野の関連資料を一緒に見せること。特に地図帳や都道府県カードは重宝しました。
5年生:情報量の急増と分野の広がり
5年生になると、1回分が8ページになり、紙面は文字でびっしり。扱う分野も地理だけでなく、歴史が加わり、知識量は倍増します。
地理の細分化
都道府県ごとの産業、気候、観光資源まで細かく覚える必要があります。例えば北海道なら農業・漁業・観光の特徴を全て押さえる必要があります。単に「じゃがいもが有名」ではなく、「十勝平野での畑作が盛んで、輪作が行われている」まで求められます。
歴史分野の導入
年号暗記も必要ですが、それよりも出来事の流れと因果関係を理解することが重視されます。例えば、「聖徳太子がなぜ冠位十二階を制定したのか」など、背景を説明できることが重要です。塾の授業では時間の都合もあり省かれる項目も多いため、親が必要に応じてサポートする必要があります。
6年生:受験直結の総仕上げ
6年生は、予習シリーズ社会が入試本番仕様に変わる時期です。
公民の基礎
国会や内閣、裁判所の役割、地方自治の仕組みなど、中学内容の先取りも含まれます。抽象的な概念も多く、初めて学ぶ子には難しく感じられます。私は娘に、選挙期間中のニュースを一緒に見て解説することで理解を深めさせました。
分野横断の総復習
地理・歴史・公民が混ざった総合問題が中心になります。例えば「○○の地域で見られる地形とその歴史的背景を説明せよ」のように、複数分野を組み合わせる設問が増えます。
資料問題の比重増加
地図や統計資料、グラフなどを読み取る力が問われます。「資料を見れば答えられる問題」と「知識がないと読めない資料問題」の両方を解けるようにする必要があります。
記述力の鍛錬
6年生後半は「なぜそうなるのか」を文章で説明させる問題が多くなります。用語暗記で終わらせず、自分の言葉で言い換える練習が欠かせません。
家庭学習で予習シリーズ社会を活かす方法
資料集・地図帳の併用
社会の学習は、知識を点で覚えず、線や面で理解することが大切です。予習シリーズの説明が簡潔な部分は、資料集や地図帳で補足しましょう。歴史分野では文化財や人物像の写真を確認しながら学ぶと定着が違います。
暗記は小分けに
特に5年生以降は情報量が多いため、1回分を3〜4日に分けて復習するのが現実的です。我が家では「月曜は地理」「火曜は歴史」「水曜は公民」と曜日ごとに分けて暗記しました。
クイズ形式で定着
子どもはゲーム感覚で覚えると意欲が続きます。私の場合、夕食時に娘に「北海道の農作物3つ言える?」とクイズを出し、正解ならデザートを豪華にするなど小さなご褒美をつけました。
予習シリーズ社会と他塾教材の比較
カラー写真と図表の強み
日能研やサピックスの教材と比べて、予習シリーズはカラー写真やイラストが含まれており、図表も豊富で視覚的に覚えやすい構成です。
背景説明の薄さ
一方で、背景知識や理由の説明は少ない傾向があります。そのため、家庭での補足が必要になる場面が多くあります。
まとめ
予習シリーズ社会は、学年ごとにレベルと範囲が大きく変化します。4年生のうちから基礎知識と興味の土台を作り、5年生の情報量に対応できる力をつけ、6年生では総合力と記述力を磨く。この流れを意識すれば、家庭でも十分に得点源にできます。
教材の強みを最大限活かしつつ、弱みは資料集や家庭での補足で補い、計画的に進めることが成功への近道だと考えます。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は、関連記事です。