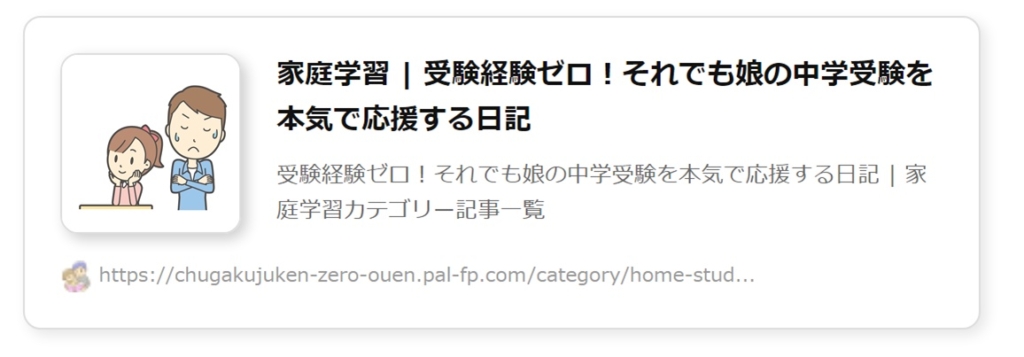学校のテストは満点でも油断ならない?――中学受験で見えた「学力差」の正体と、親子の振り返り記録

リビングのテーブルに広げた小学校のテスト用紙。赤ペンで大きくついた花丸を見て、娘と一緒に「やった!」と喜びました。でも学校では高得点、でも模試になると点が伸びない。同じ「テスト」なのに、どうしてこんなに差が出るのか。
この記事は、そんな違和感から始まったわが家の試行錯誤の記録です。親としての喜びや焦りはそのまま残しつつ、「学校テスト」と「受験学力」のズレ、そして日々の勉強の中で生まれる学力差のメカニズムをかみ砕いて整理しました。
学校テストで喜んだ日、模試で冷や汗をかいた日
「できた」実感は本物だったのに
学校の単元テストは、授業で扱った範囲が中心。用語や手順を覚えていれば正確に再現して解ける問題が多く、子供も手応えを感じやすい。一方で、条件がひとひねりされる塾の模試では、覚えた解き方をそのまま適用しづらく、思考の乗り換えが必要になります。ここで「できたはず」が崩れ、親子ともに戸惑うポイントです。
「範囲学習」と「横断思考」のズレ
学校は単元ごとの確認、模試は複数単元の横断で問う、という構図。例えば算数なら、割合とグラフ、文章題が混在します。単元の壁をまたぐ設計に慣れていないと、途中で詰まる。わが家はこの「壁」でつまずきがちでした。
言語化の不足がボディーブローのように効く
国語や理社で説明を自分の言葉に訳す練習が薄いと、設問の要求を取り違えます。学校テストではキーワード穴埋めで正答できても、記述や選択根拠の吟味が求められる模試では粗が出る。「なぜそう思う?」の口頭練習が不足していたと、後から気づきました。
親の「過大評価」という落とし穴
赤丸が並ぶと、つい学力の底力まで上がったと錯覚します。けれど実際は「範囲に最適化された力」が伸びただけのことも。学校テスト=日常の整備、塾の模試=未知への対応と役割を分けて見る視点が、やっと腹に落ちました。
学力差はどこで生まれる?――日々の習慣に潜む小さな分かれ道
「復習の粒度」が粗いと差が開く
まちがい直しを答え合わせで終わらせると、再現力は育ちません。誤答原因のタグ付け(読み違い/用語理解不足/計算精度/戦略ミス)をして、同原因の「横展開復習」へ。同じ落とし穴を「幅」でふさぐと、模試でも崩れにくくなりました。
可視化の量より「更新の速さ」
ノートやアプリでの記録は大切。でも、溜めることが目的になると情報が化石化します。「今週の仮説→土曜に検証→日曜に更新」という短い改善サイクルにしてから、気づきが翌週の点に反映される感触が出てきました。
語彙・用語の「意味のネットワーク」
理社の語句は「単独暗記」から「関係づけ」へ。たとえば理科で言うなら「侵食・運搬・堆積」を図解で矢印にし、実例(河口の三角州・扇状地)を紐づけ。ネットワークを増やすほど読解が速くなり、設問の「たくらみ」が見抜きやすくなります。
非認知スキルが実は点数に直結
時間配分・見切り・気持ちの立て直しは、問題解決の土台です。学校テストは余裕があり見えにくいけれど、模試本番は制限時間が本性を暴く。捨て問宣言や残り8分の「計算だけ回収」など、事前に言語化した「行動指針」が差を生みました。
日記だからこそ残したい:親の喜び・焦り・学び
「喜ぶ」は戦略。ご褒美の出し所を決める
結果そのものよりプロセスの改善を褒めると、次の行動につながります。わが家は、「誤答の原因タグを自力で3つ書けたらシール」など、行動に連動した小さい報酬に変更。「再現可能な努力」を強化する意図です。
「焦り」はメモに落とすと武器になる
親の心配は、子どもに伝わりやすい。ならば焦りを「数値」に変える。
(例)単元横断のミスは国語読解の設問解釈が原因 → 説明文の設問だけ練習。「心配」を「タスク化」してから、家庭学習の会話が具体になりました。
「学び」は次の週に間に合う形で
日記に長く書くより、次のプリント1枚に反映させる。たとえば算数のケアレス対策は、最初の1分で「見直しポイントを欄外に先に書く」ルールに。手順の先出しは子どもが嫌がらず、効果はてきめんでした。
「できない日」を計画に織り込む
疲れたら、「要約1本だけ」で終了もOK。やり切れない日を想定した「最小セット」を用意することで、学習の連続性が途切れない。この小さな連勝が、自己効力感を支えてくれました。
算数:数字に線・◯を付ける「手を動かす癖」をつける
1)問題文への書き込み(必ずやる)
- 数量(数値・単位)に一本線、求めるものに二重線。
- 比・割合の語句(%、倍、比)に◯、時間・速さ・距離などの条件語に四角。
- 図形は角や辺にA,B,C等のラベルを付け、与条件は矢印で結ぶ。
ねらい:簡単な問題でも毎回書き込むことで、難問で手が止まる「線も引かずに諦める」を防ぐ。
2)途中式の「最低限ルール」
- 等号は縦に揃える/単位は最後にもう一度書く。
- 約分・通分は分数の横に小さくメモ(消さない)。
3)余り時間の見直しチェック(算数の「3点」)
- 桁ミス(0の数・小数点・繰り上がり)
- 符号/向き(+−、増減、進む向き)
- 単位(m↔cm、分↔秒、円↔%)
→ 3つに○○○と小丸を描き、確認したら塗りつぶすだけ。子どもが一人でも運用可。
国語:本文線引きと選択肢「正誤書き込み」を習慣化
1)本文の線引きルール(20秒で準備)
- 筆者の主張・結論に二重線、理由・根拠に一本線。
- 対比・転換の語(しかし/一方で/つまり)に◯。
- 指示語(これ/それ/そのため)の指す内容を欄外に2〜5字でメモ。
ねらい:学校の易しい文章でも線引きしない「練習」をさせない。手を動かす読解をデフォルトに。
2)選択肢問題の正誤書き込み
- 各選択肢の語尾・条件を本文の該当行番号でマーク(例:3行・7行)。
- 本文と一致:○、言い換えズレ:△、本文にない:×を選択肢の横に記号で。
- 迷いは本文の言い回しを2〜4語で写す(例:「〜とある」「具体例のみ」)。
3)記述の「最低限チェック」
- だ・である/です・ますの統一、主語と述語が対応しているか、本文語の使い回しがあるか。
- 余り時間で文末だけを読み返す→因果が逆転していないかを確認。
テスト返却日の「超シンプル振り返り」(家で5〜8分)
- 事実だけ共有(1分)
正答率・ケアレス数(算数)・本文行番号の抜き(国語)を数字で一言。 - 線引きの形だけ点検(2分)
算数:二重線(求めるもの)がない設問は?/国語:主張二重線・理由一本線が機能した? - 次回の「1個だけ約束」(2分)
例:「割合の%に◯を必ず付ける」/「選択肢は本文行番号を必ず書く」。一つに限定。 - ごほうびは「実行」に連動(1分)
約束を3回連続でできたらOK(点数連動ではなく行動連動)。
保護者の声かけ例(15秒):
「今日は数字と単位の線がはっきり引けてたね(具体)。次は%の◯だけ絶対やろう。3回できたら〇〇しよう(報酬)。」
1枚テンプレ
- 今日のテスト:算数( )点/国語( )点
- 算数:線引き達成[数量線/求め二重線/単位確認](○○○)
- 国語:線引き達成[主張二重線/理由線/行番号メモ](○○○)
- 見直し:算数[桁・符号・単位](○○○)/国語[一致・ズレ・文末](○○○)
- 次回の約束(1個):__________
- 3回続いたらごほうび:__________
使い方のヒント
- 「難しい日ほど、線だけはやる」を合言葉に。計算が間に合わなくても線引きと行番号は死守。
- 最初の1〜2週間は親が横で同じ線を引くと、子どもが真似して定着が速いです。
- 学校テストが易しすぎても、「できた=線を引いたから」と口に出して関連づけると、塾の難問でも手が動くようになります。
まとめ:学校テストは「安心」、模試は「現実」。両輪で前に進む
学校テストは「整っているか」を見る鏡、模試は「未知にどう向き合うか」を試す場。役割が違うから、見方も違って良い。そして学力差は、劇的な勉強法ではなく、誤答原因の横展開・言語化・短サイクル改善・行動指針の事前決定といった小さな習慣の積み重ねから生まれます。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。