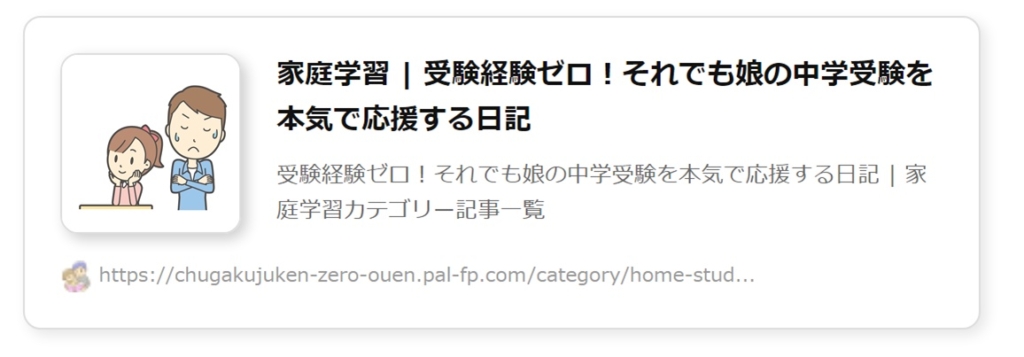中学受験の「勉強時間」はどれくらい?学年別・偏差値別にリアルな目安と考え方を解説

中学受験を目指すご家庭にとって、「毎日何時間勉強すれば大丈夫?」はとても気になるポイントだと思います。実際、SNSで他のご家庭の勉強時間を見ると焦ってしまいますが、長ければよいというわけではありません。大切なのは質と量のバランスです。また、お子さまの性格や集中力、学力の現状によって最適な時間は変わります。



本記事では、学年別・偏差値別にリアルな目安を示しつつ、エピソードも交えながらご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
学年別の勉強時間の目安と注意点
目安:小4〜小5の場合
小4〜5では1日1〜2時間、週末は3時間ほどが一般的です。量よりも「勉強習慣を身につけること」に主眼を置き、遊びや休みとのメリハリを大切にしたほうが良いと思います。私の娘も小4の頃は、興味があれば続ける、飽きたら切り替えるというスタンスで、自然と自主学習の土台ができていました。
目安:小6の場合
小6では、塾の日は夜1.5〜2時間+週末に3〜4時間を目安とする家庭が多いです。ただし、「だらだらやる時間」では意味が薄いので、タイマーを活用して短時間集中→休憩など、メリハリ型の時間割を心がけると効果的です。
注意:学年だけで決めない
学年ごとの平均は目安にすぎず、お子さまの性格・集中持続時間・学力の伸び具合に応じて調整が必要です。たとえば、娘は比較的集中力が続く子だったので、50分区切りで1コマにしたら集中力が維持でき、やる気も継続しました。
偏差値別の勉強時間と戦略
偏差値55以下の層
普段の授業の内容が理解できるとは言えない状況なので、ここから学力を向上させようとすると、相応の負荷を覚悟する必要があると思います。月〜金は1日2時間、週末3〜4時間を目安に、苦手科目の補強と基礎固めを優先しましょう。
ポイントは「苦手→克服」も念頭に置きながら、「得意→伸ばす」姿勢です。苦手克服ばかりだと勉強にうんざりするかもしれないので、少しずつ自信を積み上げていくことがやる気につながります。
偏差値60前後の層
伸び悩みやすい学力帯です。応用問題演習を増やしつつ、平日は1.5~2時間、休日4〜5時間程度。「できなかった問題の振り返り」を必須にすると、学力が定着しやすいと思います。
偏差値65以上の層
基礎的な問題は難なくこなしていけるので、学力維持でよいのであれば、学習時間は意外と少なく抑えることができますね。
しかしながら、やはり志望校レベルが高いほど応用力や時間管理が鍵になります。平日2~3時間、休日5〜6時間を基準に、本番想定演習とペース配分トレーニングを取り入れると安心です。ただし、疲れすぎには注意し、どこかの曜日や時間帯をオフにすると気力が回復しやすいです。
質×量が大切:—勉強時間を最大限に活かす工夫
工夫1:短い区切り勉強
例えば、「30分×◯セット+10分休憩」というスタイルは、集中力が途切れても気にせず切り替えやすいので低学年から取り入れやすいです。中学受験では体力的にも精神的にも余裕が生まえます。
工夫2:定期的な振り返り
週末に「何が苦手だったか、次週の目標は?」を親子で確認する時間は目的意識と責任感を育ててくれます。娘も、この振り返りを始めてから、目標設定が上手になったと思います。
工夫3:勉強スケジュール表を共有
紙ベースでもアプリでも、自分でスケジュール表を作ると、目に見える形で進捗管理ができるのでやる気維持につながります。娘は「親が確認してくれる」ことで責任感が上がったと感じていました。
工夫4:勉強以外の過ごし方も重視
勉強の質は「睡眠」「食事」「休憩時間」によって左右されます。テストなどの拘束がなければ、我が家では土日それぞれ必ずと行っていいほど外食を楽しんでいました。特に週末など、リフレッシュ時間を入れることで、勉強時間そのものの質が上がるように思います。
他の子との比較より、自分の子どもを見るべき理由
比較1:学力レベルの違い
他のお子さまが4時間勉強していても、それは前提学力や学習習慣次第です。当家庭では、娘は最初から最後まで高偏差値をキープできていましたが、まわりから思われるほど勉強時間は長くありませんでした。これは、他の子よりも基礎から標準問題では苦労すること無くスピーディーに解けてしまい、とき直しも必要なかったためと考えられます。その分、難問に時間を取ることができ、無理に時間を増やさず効率の良い復習に注力でき成績が安定しました。
先取り学習の有無
塾の勉強をしながら先取りをする子は、勉強時間だけを見ると長く見えがちですが、進み具合自体が違います。逆に、先取りをしているからこそ、塾の学習が新単元であったとしても復習となるので、より短時間で学習できるということもあります。そのため「時間だけ」に惑わされない視点が重要です。
地頭や性格による差
瞬発力・直感力・集中力が違いますし、理解スピードにも個人差があります。今思えば、娘は勉強全般が得意だったのでしょう。妹たちとは大きく異なることを実感しています。
まとめ
勉強時間は学年や偏差値ではなく、「子どもにとって効果的かどうか」で決めるべきです。また、学年ごとの平均は目安であり、お子さまに合わせた調整が必要です。そして、質×量のバランスが大切。短時間集中と定期的振り返りで効果を高めましょう。さらには、比較ではなく、自分の子の「個性・理解度・目標」に目を向けることが、最短距離です。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)