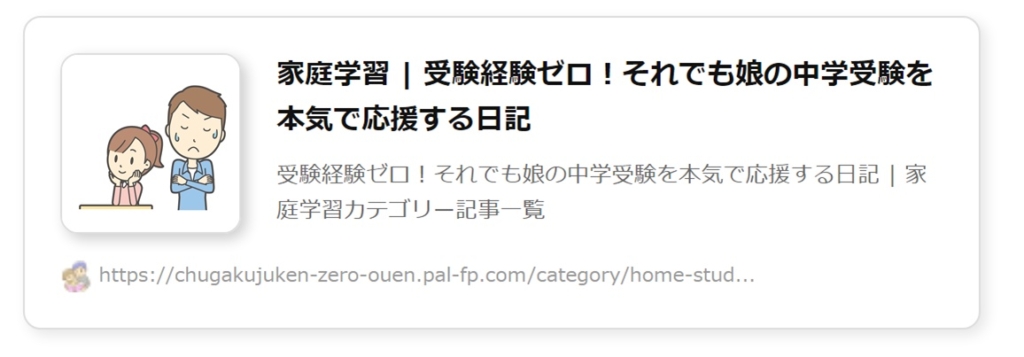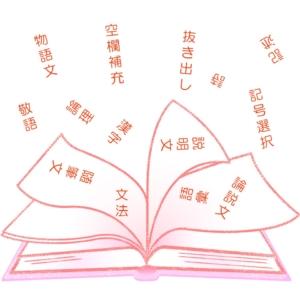中学受験を見据えて低学年で「やっておけばよかったこと」5選|後悔しない家庭学習のすすめ

中学受験を経験した今だからこそ思うのは、「あの頃、もっとこうしておけばよかった…」という低学年時代への反省です。もちろん、家庭の方針や子どもの性格によってベストな方法は違いますが、私の場合は「もう少し、やっておくことを早く始めておけばよかったな」と思うことがいくつもあります。



この記事では、実体験と他の保護者からよく聞く声をもとに、私の次女、三女で実践している「中学受験を目指すなら低学年でやっておけばよかったこと」を整理しました。
低学年でも「学習習慣」を身につけられる
朝と夜にルーティンを作る
低学年のうちから、決まった時間に机に向かう習慣がある子は、後の受験勉強にスムーズに入れます。高学年になってから急に「さあ、やろう」と言っても、なかなか身が入りません。「時間になったら机に座る」というルールは、短時間でも継続が鍵です。
学校の宿題やテストの振り返りを「丁寧に」やる癖を
単に終わらせるだけでなく、ノートに丁寧に書く・解き直しをするなど、正しい勉強のやり方を早めに身につけることは重要です。学校の学習のレベルには思うところもある方もいらっしゃると思いますが、良い習慣・癖をつけるには丁度良い機会となります。私の子どもも、低学年で癖づけたおかげで、高学年ではスムーズに学習を進めることができました。
親が一緒にやる時間を取る
この時期はまだ「一人で勉強」は難しいもの。保護者が横に座って一緒に取り組む時間を作ると、勉強に対するポジティブな印象が残ります。反対に「勉強=怒られること」というイメージがつくと、後々大変です。
基礎的な「計算・漢字・語彙力」をコツコツと
毎日の「計算練習」は数分でOK
中学受験の算数では、計算力のスピードと正確性が前提です。低学年からの積み重ねが後の「応用力」につながります。朝食前や登校前の5分など、生活の中に自然に組み込むことがコツです。
「漢字練習」も無理なく習慣に
難関中学の国語では、語彙力・漢字力の差が得点に直結します。長女の場合は2~3年生からのスタートでしたが、慌てて詰め込み始めるより、1・2年生で楽しみながら漢字と触れ合っておくと、もっとよかっただろう…と今は感じています。
「読書」と「言葉遊び」で語彙を豊かに
低学年で本を読む習慣がある子は、読解力の伸びが違います。おすすめは「音読」と「なぞなぞ」「しりとり」など、言葉を楽しむ習慣を作ること。後から始めた子が追いついても、先行していた子の余裕は大きな武器になります。ちなみに、読書をするにも、漢字がハードルになることがあるので、特に漢字の「読み」の先取りは大変有効です。
やっておくことは机の勉強だけじゃない!「外の体験」の大切さ
自然・博物館・旅行で感性を育てる
理科・社会において、「体験を通じた知識」は記憶の定着度が全然違います。川遊び・山歩き・科学館・歴史スポットなど、実際に見て触れる体験は、後に知識の引き出しとして役立ちます。
習い事やスポーツは息抜きにも
勉強漬けにしすぎず、バランスよく身体を動かすことも重要です。ピアノや水泳、空手などの習い事を通して、「継続する力」「自己管理」も自然に育ちます。
「遊ぶこと」から学ぶ力も
低学年はまだまだ遊びたい時期。ブロックやボードゲーム、パズルなどの知的遊びは、思考力や集中力を育てる良い手段です。私の子もシンクシンク!のようなパズルゲームにハマっていたおかげで、思考問題に強くなったように思います。
先取り学習の是非と「気づいたときが始めどき」
「先取り不要論」の落とし穴
「先取りしなくても追いつける」という意見もありますが、基礎が抜けていたり、学習習慣ができていないと、結局は苦労します。私自身、「やっておけば…」と後悔するのはこういった部分です。
逆に、先取りをした場合に、「どうせ後から始めた子に追いつかれる」という主張もありますが、「先取りしていなければもっと苦労することになっていた。」ということでもあるということだと思います。
無理のない範囲で少しずつ
大切なのは、無理なく・楽しみながら先取りを取り入れること。小数や単位の感覚、語彙の幅など、受験に直結する素地を、ゆっくり作っていけばいいのです。
「気づいたときがチャンス」と考える
低学年のうちに気づけたなら、それが最良のスタートです。「遅かったかな?」と迷うより、「今この瞬間から始めればいい」と、私は考えています。
まとめ
中学受験に向けて、低学年の時期にやっておけばよかったことは、どれも「将来の土台になること」ばかりでした。学習習慣・基礎の反復・外の体験・語彙や読解力…いずれも急には身につかないものだからこそ、早いうちに取り組む価値があります。もちろん、子どもが楽しんで学べる形を見つけながら、家庭ごとのペースで「やっておくこと」を進めるのが一番です。今、小さな一歩を踏み出すことが、数年後の大きな力になると信じています。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)