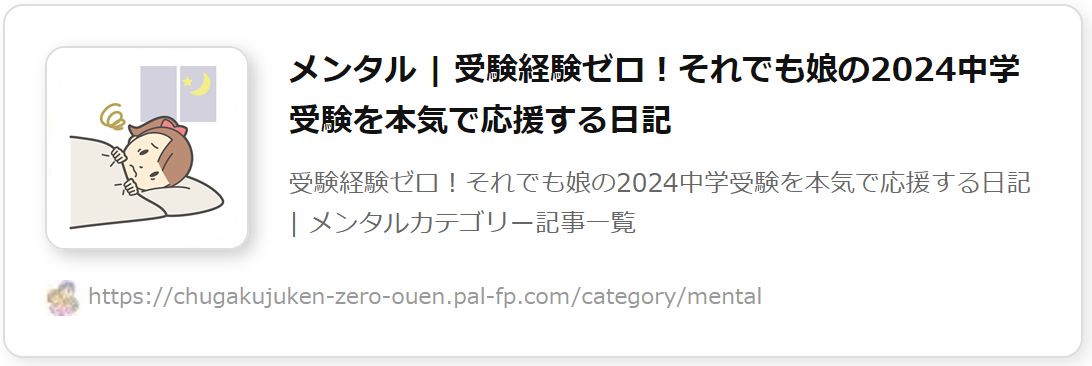中学受験生の睡眠時間は何時間が理想?統計と実例で読み解く「学力と健康」のバランス術

中学受験に挑むわが子を見ていて、「これだけ勉強していて、睡眠時間は大丈夫なのだろうか」と感じたことはありませんか?学力と健康の両立は、受験期の最大の課題のひとつです。
娘が受験を意識し始めた5年生の頃、毎晩の就寝時間が遅くなり、朝は眠そうにしていたことが気になっていました。塾や宿題に追われる生活のなかで、どれくらいの睡眠を確保すればよいのか、どうすればリズムを整えられるのかは、今でも多くの保護者の悩みだと思います。



この記事では、実際の統計データや中学受験生の平均睡眠時間の現状をもとに、理想と現実のギャップを読み解きながら、わが子の睡眠と学習バランスをどう整えるべきかを考えていきます。
小学生の理想的な睡眠時間とは?
小学生に必要な睡眠時間の目安
厚生労働省や米国睡眠医学会のガイドラインによると、小学生の理想的な睡眠時間は「9〜12時間」とされています。これは身体や脳の発達が活発な時期だからこそ、成長ホルモンの分泌や記憶の定着に十分な睡眠が必要だからです。
実際の平均睡眠時間とのギャップ
しかし実態はというと、日本国内の小学生の平均睡眠時間は8時間56分、中学生では7時間57分という調査結果が出ています(2025年全国統計より)。特に小学5〜6年生では平均8.3〜8.5時間にとどまり、理想より1時間近く短いというのが現状です。
年齢別の平均データに見る傾向
年齢別にみると、小学4年生までは9時間近い睡眠を確保している子もいますが、5年生になると宿題量の増加や塾通いによって一気に減少。6年生では7時間を切る子も多く、睡眠時間の減少が学年とともに顕著に表れるのが特徴です。
中学受験生の睡眠時間:実態と統計
中学受験生の平均睡眠時間とは?
保護者や受験生対象の調査によると、中学受験生の平均睡眠時間は「7〜8時間」が最多、次いで「6〜7時間」、「6時間未満」も一定数存在、という結果が得られているということです。特に受験直前期の6年生ではかなり短くなるというデータもあるようです。
難関校志望者ほど短くなる傾向
難関中学を志望する層では、塾の授業終了が21時を超えるケースも多く、帰宅後の夕食や宿題を終えるとどうしても就寝が23時以降になることも。朝6時起床で7時間を切るのは、もはや当たり前とされているご家庭もあるようです。
我が家では、娘の体調が悪くなることがわかったため、6年生の受験期でも睡眠時間8時間をキープするようにしていました。
睡眠不足が続いた場合の影響
睡眠が不足すると、集中力や記憶力、免疫力の低下、感情コントロールの乱れなどさまざまな影響が指摘されています。特に「海馬」と呼ばれる記憶領域の発達は、睡眠時間が10時間以上の子どもに比べて6時間の子では体積が約1割小さいという研究もあるそうです。
成績と睡眠の関係:質と量の両立は可能か?
「夜型」学習の限界
中学受験生の生活リズムは、どうしても夜型に傾きがちです。ただし、夜遅くまでの学習は集中力の低下やミスの増加、定着率の低下を招きやすいと言われます。「夜の1時間は昼の30分」とも言われるほど、効率面で差が出ることも。
「朝型」への切り替えのすすめ
朝に短時間の復習や暗記時間をとる方が、効率よく記憶に残るという研究も多くあるようです。とくに入試本番は午前中に行われるため、「午前の脳」を活性化させておくことが鍵です。娘の場合も、6年生の秋以降は意識して22:00までには寝て、6:00起きを習慣づけるようにしました。
量だけでなく「質」も大切
仮に7時間しか眠れないとしても、寝る前のスマホや刺激の強いテレビを避け、眠りの「質」を上げる工夫も重要です。お風呂の時間を調整したり、照明を落として寝室を落ち着かせるだけでも、睡眠の質はぐんと良くなります。
受験学年ごとの睡眠時間の目安と対策
小学4〜5年生の理想的な睡眠時間
この時期は9〜10時間を意識しておきたいところ。塾も週2〜3日程度であれば、21時台の就寝も十分に可能です。ここで生活リズムの基礎を整えておくことが、6年生以降に大きな差を生むと私は感じました。
小学6年生の現実と調整法
塾の頻度や内容がハードになる6年生では、8時間睡眠は現実的に難しいケースも。それでも最低7時間の確保を目標に、家庭でできる調整(夕食の簡略化・入浴順の工夫など)を積極的に取り入れたいところです。
直前期の「睡眠確保」は最優先事項
1月以降の受験直前期は、勉強量より「体調管理」が成績に直結します。短期間で詰め込むよりも、睡眠時間を確保して脳の回復を図ることが、逆に得点力を上げる近道になることもあると思います。
睡眠時間を確保する家庭での工夫
夕方以降のスケジュールを「固定化」する
毎日のスケジュールをある程度パターン化し、「夕食→入浴→学習→就寝」の流れをルーティン化することで、無駄な時間を削減し、睡眠時間にゆとりを持たせることができます。
食事とお風呂のタイミング
消化活動と体温上昇を考慮して、夕食は就寝の2時間前、お風呂は1時間前が理想とされています。これを意識するだけでも、自然と入眠がスムーズになります。
休日の「寝だめ」はNG?
休日に遅くまで寝ると、月曜以降のリズムが崩れ、かえって眠れなくなることも。平日と±1時間以内の起床・就寝リズムを守るのが理想的だと感じています。
まとめ
中学受験期は、どうしても勉強時間の確保が優先されがちですが、「睡眠こそが学習効率を左右する鍵」でもあります。理想は9時間、現実的には6〜8時間。限られた時間の中でも「質の良い睡眠」を確保する工夫が大切です。
娘の受験を通じて感じたのは、「長く勉強するより、元気に集中して取り組める状態を作ること」が合格への近道だということでした。保護者としてできることは、「睡眠」と「生活リズム」の環境を整えること。今できる最適な選択を、親子で一緒に考えていきましょう。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)