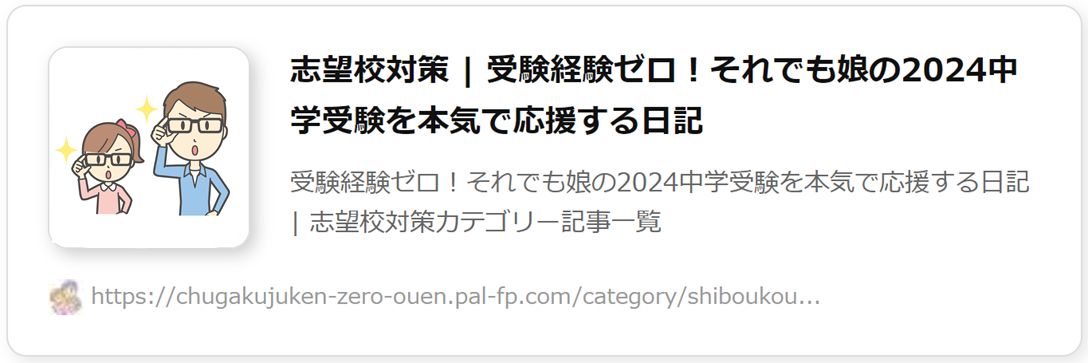中学受験の過去問やり方完全ガイド|効果的に進めるための親の工夫と注意点

中学受験を控えたご家庭では、「過去問ってどうやってやればいいの?」という疑問に直面する方も多いのではないでしょうか。特に初めての中学受験だと、「過去問っていつから始めるの?」「何年分やればいいの?」といった疑問が次々に出てきますよね。



うちの場合も、小6の夏休みに入ってから「そろそろ過去問の準備かな」と意識し始めたものの、具体的にどう取り組めばよいかは、かなり迷いました。頼みの綱の塾からもなかなか過去問については連絡が来ず、問い合わせても一般論的な話だけ。
この記事では、中学受験の過去問の「やり方」について、親目線で丁寧に解説します。過去問の役割、始めるタイミング、解く順番、使い方のポイント、やり直し方法までを網羅しているので、「これから過去問に取り組みたい」と考えている保護者の方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
過去問の役割を正しく理解しよう
志望校の傾向を知るための資料
過去問を解く最大の目的は、「その学校がどんな問題を出すのか」を知ることです。問題の形式や難易度、出題分野の傾向など、塾の模試では見えてこない学校独自の特徴がつかめます。
合格点のイメージを持つ
学校によっては合格最低点が公開されており、それと比べて自分がどれくらいの得点が取れているかを確認することで、現状の立ち位置や課題も把握しやすくなります。
本番を意識した時間配分の練習
本番に近い形で時間を計って解くことで、時間配分や集中力のトレーニングにもなります。普段の問題集では測れない「時間との戦い」の感覚を得ることができます。
過去問はいつから始める?開始時期の考え方
王道は夏休み明け、でも早めもアリ
多くのご家庭が小6の夏休み明けから過去問を始めます。基礎がある程度固まったタイミングだからです。ただし、早い段階で志望校が決まっている場合、小5の終わりや小6の夏休み中などに試しに1年分解いてみるのも効果的です。
基礎力がまだの子は無理に始めない
過去問は基礎がある程度できてからでないと、ただの自己否定になってしまうことがあります。点数に一喜一憂して「うちの子には無理かも…」と不安になるのは本末転倒です。
塾の志望校別コースなどの対策講座に合わせる
例えば早稲田アカデミーのNN後期講座では、週ごとに「今週はこの学校の過去問」とスケジュールが決まっています。ただしこの発表は遅いこともあるので、夏休み中に解きたい場合は事前に相談するのがベターです。
解く順番の決め方|新しい?古い?どちらから?
古い順は失敗リスクあり
「10年前から順番にやっていけばよい」と考える方もいますが、時間切れで最新年度を解けないまま入試を迎えるのは避けたいところです。
また、傾向が変わってしまっていて、古い過去問は意味が薄れる可能性も。例えば早稲アカでは、第一志望でも5年分が推奨され、これで十分ということでした。
最新年度から?それとも中間から?
最近の中学入試は年々難化しています。そのため、最新年度から順に解いていくと、本番レベルを意識した演習になりやすいですが、基礎が未完成の時期に難問にぶつかるリスクもあります。
折衷案:最新年度を「あとに残す」
うちの場合は、第一志望校の場合は「NNで決められている年度はNNに従い、それ以外は新しい順に」、第二志望校以下は「最新年度の1回分を残し、新しい順に」という方式を取りました。過去問のレベル感に慣れたうえで、直前期に一番新しい年度を解くと効果的と考えました。
効果的な解き方と使い方の工夫
本番と同じ環境を意識
可能であれば、四谷大塚のデータベースから過去問をダウンロードして印刷し、本番と同じ用紙・サイズで練習するのがベストです。実際にやってみると、「試験用紙の扱いに慣れているかどうか」で集中力に差が出ることに気付きました。
なお、プリント型ではなく冊子型の場合は、少し手を加えることで冊子型を準備することが可能です。ダウンロードしたPDFは見開きのプリントになっているので、真ん中で2ページに分割し、プリンタの設定で冊子型印刷を行えばよいだけです。
いずれにしても、解説がないのが四谷大塚過去問データベースの欠点ですので、別途、市販版の過去問も必要と考えたほうが良いです。
声の教育社などの市販版も活用
市販の過去問は、解説が充実しているという利点があります。レイアウトが異なるという意見もありますが、家庭学習では解説の有無が非常に重要。コピー用紙やファイリングで調整すれば、本番の形に近づけることはできます。
問題の難易度を記録・整理
過去問演習の後は、「難しかった問題」「間違えた原因」「得点できた理由」などをノートに記録することが大切です。特に社会や理科は、ミスのパターンを把握すると対策しやすくなります。
解き直しと復習の仕方
一度解いて終わりにしない
過去問の目的は「できた・できなかった」ではありません。「なぜできなかったか」を明らかにすることが最大の目的です。
解き直しノートを作ろう
間違えた問題をもう一度やり直すために、「解き直しノート」を作るのがおすすめです。うちの娘の場合も、算数、理科、社会では解き直しを繰り返すことで、正答率が上がるだけではなく、周辺知識や解法の理解が深まりました。
2回目どうする?
一度解いた年度の問題を、時間が経ってから再度取り組むという考えがあります。しかしながら、私は前述の解き直しノートによる間違えた問題だけを反復することにし、全体を2回解くことはしませんでした。同じ問題は二度と出ませんし、単純にそんな時間はありません。
ただし、繰り返しになりますが、間違えた問題の理解が完璧になっているかは、時間を置いてから確認します。二度と出ないと行っても、近い問題は出るかもしれません。受験者のうち、過去問をきちんと理解していた子に差をつけられるわけにはいきません。
まとめ
過去問は、「解けば合格に近づく魔法の教材」ではありません。しかし、正しい時期に、適切なやり方で、繰り返し活用することで、確実に志望校合格への道筋を築ける強力なツールになります。
焦らず、でも着実に。我が家のように、早めの試行と柔軟な取り組みで、過去問を味方につけていきましょう。子どもの成長は、親の伴走で大きく変わります。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下は、関連記事です。