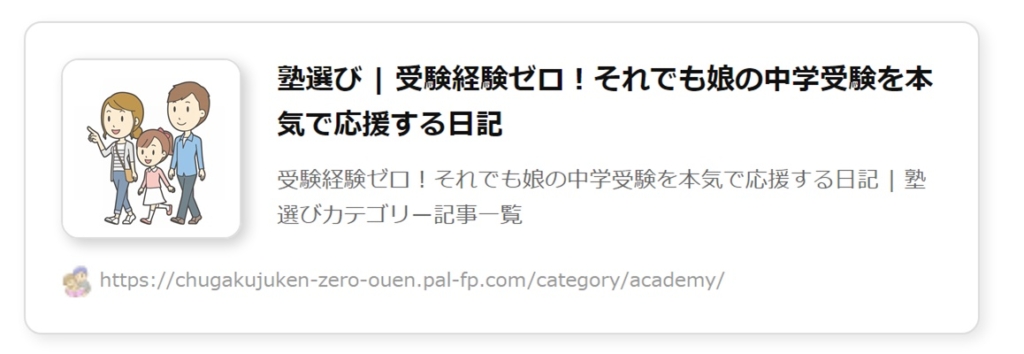早稲田アカデミーの「校舎別合格実績」をどう読む?Exiv・中規模・小規模の違いとNN活用まで保護者目線で徹底解説

中学受験で塾選びをするとき、多くの保護者が最初に見るのが「合格実績」です。なかでも校舎別の実績は、通える範囲の校舎がどれくらい強いのかを判断する材料になります。ただ、数字はその年の生徒構成や志望校分布に強く影響されるため、単純比較は危険だとも感じます。



私自身、娘の受験の際にデータを集めて考えました。本稿では、「早稲田アカデミーの校舎別中学受験の合格実績」の読み解き方を、Exiv・中規模・小規模という校舎タイプの違い、NNの存在、在籍規模による見え方の差、そして年度差の大きさという視点で整理します。
校舎タイプの把握:Exiv・中規模・小規模は何が違うか
Exiv校:最上位層が厚く、実績が安定しやすい
Exiv校は、所属生徒数が多く、最上位層が相対的に厚いのが特徴です。結果として、毎年一定数の最難関校合格者が出やすく、実績が安定する傾向があります。一方で、絶対数では強く見えても、生徒一人あたりで見た効率を採ると印象が変わることもあります。私は、ここを見落としがちな盲点だと感じます。
中規模校:SSが複数クラスのパターン。年度によって「跳ねる」ことがある
中規模校は、SSクラスがSS1・SS2のように複数に分かれるタイプ。年度によってはExivに匹敵する実績を出すこともあります。
早稲アカでは、四谷大塚の組分けテストを受験しますが、早稲アカ生だけの結果を集計した「WinJr」がもらえます。ここには上位生の所属校舎がわかるようになっていて、娘の年度のデータを追ったことがあります。すると、四谷大塚の組分け分類でSコースの上位帯に限って比較すると、「Exiv校」が占有しているというわけではなく、中規模校が勝っている印象の校舎も複数ありました。
ただし、これは年度依存が大きいという点は強調しておきたいです。長女の所属校舎では、長女の年度は「Exiv校」に勝るとも劣らない実績だったようですが、その前後の実績はそうでもないことを確認しています。
小規模校:SSが1つ。平常の学習では難問密度が下がりやすい
小規模校はSSクラスが1つのことが多く、平常授業では上位と中位が同じ土俵で学ぶ場面もあります。特に算数では、最上位特化の難問演習の比率が低い可能性は意識しておきたいです。
早稲アカの小規模校でも、NNがあるため最難関校に合格することは不可能ではないでしょう。一方で、平常授業では四谷大塚の分類でSコースだけでなくCコースの生徒も一緒にSSクラスとして授業を受けることになります。そうなると、特に算数ではExiv校や中規模校ほど難問を扱わない可能性が高いということです。長女の校舎の場合ですが、当時、Cコースでは解くのが難しいだろう問題ばかりをSS1クラスの算数では扱っていました。
\ 「読む力」は、家庭の手で育てられます。/
中学受験の国語で苦戦するお子さんは、実は「センス」ではなく「読む手順」を知らないだけです。授業だけでは身につかない読解の基礎を、家庭でどう支えればよいか――その具体的な方法をまとめた記事「親が変える。才能ではなく手順で伸ばす中学受験・国語の読解力」をnoteで公開しました。家庭での国語学習を変えたい方は、ぜひご覧ください。
数字の落とし穴:年度差・在籍規模・志望校分布をどう補正するか
年度差:同じ校舎でも「山谷」がある
娘のときに感じたのは、同一校舎でも年度による振れ幅が大きいこと。ある年度はExivに引けを取らない実績でも、前後の年度を並べると安定して最難関を量産しているとは言い切れないケースが普通にあります。
単年ランキングではなく、最低でも直近3年の推移を見ることを強くおすすめします。前述の通り、少なくとも長女の校舎はこのパターンに該当してしまっていました。
在籍規模で割る:実数だけでなく「密度」を確認
校舎別実績は実数で並ぶことが多いですが、在籍数で割った「合格者密度」を見ないと評価を誤ります。母数が大きければ合格者総数も大きく見えますが、一人あたりのアウトプットという観点では中規模の方が競っていることもあります。実績=規模の影響を受ける指標であることを忘れない視点が重要です。
志望校分布:校舎カラーと可処分時間の合致
各校舎には志望校の「偏り」があり、御三家志望が多い校舎や、共学校志望が厚い校舎などさまざまです。志望校と校舎カラーが合っているかは、合格者数以上に大事かもしれません。ただし、やはり在籍者の絶対数が少ない場合、年度による差が大きく出てきてしまいます。
外部生の影響:NNの合格者カウントの見え方
NNには一定割合の外部生が参加しています。年度や志望校にもよりますが、長女のときは体感で少なくとも2割が外部生でした。これは、オンラインの保護者会では所属校舎も入力するので外部生がどれくらいいるかは大まかにわかります。
そして、長女は最初から最後まで1組でしたが、1組にもやはり外部生は少なからずいました。SNSでときどき見かけるほど「外部生がNN上位を占有」ではなく、「多くが早稲アカ内部生」だったと私個人的には持っていますが、ここは「当時の長女の記憶」ベースですし、年度やNN志望校によっても変わるところだと思います。
\ 決勝大会では「作文」が勝負を分ける!/
全国統一小学生テストの決勝大会では、作文の配点が差をつけます。
親としてどんなサポートができるのか?どこまで関わるか?
経験者でなければ知り得ない「評価基準」「構成パターン」などを、
5回分の実際の課題・成績・講評分析から体系化しました。
上位30人を目指す保護者に役立つ具体策をnoteで公開しています。
データの集め方:公式・校舎配布・コミュニティの三層を重ねる
公式資料:合格実績・説明会資料・校舎掲示を時系列で保管
まずは公式サイト・校舎掲示・説明会配布の資料を年度ごとに集め、同条件で比較できるように時系列で保管します。男子校・女子校・共学校の区分、学校名の表記揺れなどの整形をしておくと便利です。
校舎に直接聞く:在籍規模・上位クラス数・直近3年の推移
体験授業や面談の席では、在籍総数、SSクラスの数と人数、直近3年の実績推移を尋ねるのが有効です。模試偏差値分布まで確認できると、数字の土台が見えてきます。
コミュニティ・自作集計:穴を埋めるが、過信しない
X等で公開されている有志スプレッドシートや、保護者ブログのまとめは、公式の空白を埋める材料として便利です。ただし、入力漏れや定義の差は避けられません。公式と突き合わせて矛盾がないかを常に点検し、単独で断定しないことが肝心だと思います。
検索で辿れる有志データの例として、Googleで「早稲アカ主要校 校舎別合格実績 ThreeStars」と入力すると、上位に「X(旧Twitter)」の投稿が表示されるはずです。そこから校舎別・年度別の合格実績をまとめたスプレッドシートを閲覧できます。イメージとしては「サピックスの『サピクサー』」に近い設計ですが、入力数が少なく網羅性は限定的で、抜けや定義差がある前提で扱うのが安全だと思います。
- 到達手順:Googleで検索 → 上位のX投稿を開く → 投稿内の案内に従ってスプレッドシートを表示。
- 見方のコツ:校舎タブや年度フィルタで絞り、直近3年の流れを確認。可能なら在籍規模で合格者数を割って密度を見ます。
- 注意点:未入力の年度・校舎がある、合格者のカウント基準(平常在籍とNN参加の内訳など)が明記されないことがある、更新タイムラグがある——などの理由で、単独で断定しないのが原則です。
- 活用法:公式の校舎掲示や配布資料と突き合わせ、矛盾がないかをチェック。もし差があれば、面談で在籍規模・上位クラス数・外部生の寄与を質問して「数字の背景」を詰めると精度が上がります。
なお、有志スプレッドシートは空白を埋める補助線としては便利ですが、基準の異なる数字を横並びで比較しない姿勢が大切です。まずは公式で骨組みを作り、こうしたコミュニティ発のデータで「傾向」を補正し、最後は体験や面談での具体情報で仕上げる、という順番を意識するとブレにくいと感じます。
早稲アカ版サピクサーの集計が部分的とはいえ、どう外挿しても「早稲アカの校舎別合格実績の合計が早稲アカ全体の合格者数に届かなそう」な理由の1つは、やはり外部生の存在と思っています。さらに、「私の体感の外部生率を考慮しても、それでもまだ早稲田アカデミー本部発表の数字に届かそう・・・」とも思っています。
そのため、私自身ではもちろん体験していないのですが、早稲アカに子どもが通っている知人などの話を聞く限り、ネットで不安を掻き立ててくれる「早稲アカは受験直前に外部生に特待や個別指導を提供して、代わりに合格実績にカウントする」については、「どうやら本当なのだろう・・」と私は個人的に考えています。
もっとも、だからといってNN校を目指すなら子どもや親がやることは変わりません。子どもの苦手を捉え、克服し、NNでの順位を上げ、サピックスだろうが負けない学力を身につけるだけです。
なお、本家であるサピックスの合格実績を校舎別に集計しているサピクサー(sapixer)については、以下の記事で詳しく紹介しています。
NN(志望校別講座)の位置づけ:小規模校でも突破口になる理由
NNの役割:志望校の出題形式にピンポイントで寄せる
NNは学校別の出題傾向に合わせた最終調整の色が濃く、頻出パターン・時間配分・得点設計を短期間で体に入れる場です。小規模校所属でも、NNで最上位と切磋琢磨できるのが強みだと思います。
外部生の参加:合格実績の解釈が難しくなる要因
NNには他塾生の参加も一定数あります。平常在籍とNN由来分を切り分けて把握できると、校舎の平常授業の力と最終局面の仕上げ力を分けて評価できます。
ただし、気にしても仕方ない部分でもあります。優秀な外部生がいることで、その分NNの子たちの層もよりいっそう厚くなるとでも思っておくのがよいです。
科目バランス:算数と国語・理社の補完関係
Exivや中規模では算数の難問演習密度が高いですが、国語の記述精度や理社の知識は校舎よりも個人レベルで差がつきます。NNでの仕上げと自学の役割分担を設計するのが現実的だと思います。
\ 成績が伸び悩むときに読みたい実践ガイド。中学受験の「停滞期」を抜け出す重要ポイントを網羅! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。よろしければ、以下のリンクよりご覧ください。
実績を「自分ごと」に落とす:校舎選びステップ
①通塾動線×学習時間の確保
ドアツードアの移動時間=学習量です。Exivが遠ければ、中規模で定着率を上げた方がトータルで強いこともあります。
私も、「最寄りの中規模校舎よりも、少し電車に乗ってExiv校のほうが良いのでは?」と思って、所属校舎に相談したことがあります。結果的にExiv校に行くことはありませんでしたが、逆に、最寄りの校舎ではなくExiv校を選択する子がいたことも知っているので、家庭の考え方次第だと思っています。
②直近3年の実績推移+在籍規模補正
難関校実績は3年平均+在籍規模で割って比較するのが基本です。最上位帯の人数もセットで確認するとブレません。もっとも、「早稲アカ版サピクサー」を使ってもデータが不足していますし、あまり気にしすぎない・・という開き直りも大切です。
③志望校との相性:演習素材と講師の強み
志望校の頻出分野・時間配分と校舎の素材が合っているか、講師の強みと噛み合うかを必ず見極めましょう。
④NNの利用計画:所属校舎の弱点を補う
早稲アカに通ってNN校を目指すなら、「所属校舎で併願校向け対策を、NNでNN校対策を仕上げる」と早稲アカから説明を受けます。つまりは、小規模校でもNNがハマれば合格可能性が一段上がるということです。近くに小規模校しかなく、中規模校・Exiv校だと遠いという場合は、通塾の負担は子どもが受けることになるし、小規模校の方が現実的なことが多いのではと思います。
よくある誤解と注意点:数字に強く見える「理由」を言語化する
Exiv=常に最適、ではない
Exivは強いですが、移動時間やクラス密度の高さが裏目に出ることもあります。家庭の生活設計と噛み合うかが重要です。
「跳ねた」年度をそのまま信奉しない
中規模校がExiv級の実績を出す年もありますが、持続性を確認しなければ錯覚します。
小規模=不利、ではない
NNでの上振れ余地や講師の面倒見は小規模の強みです。
合格実績の「カウント」の中身を確認する
平常とNNのみ参加、外部生の扱いなど、実際に所属しないとわからないし、所属しても全てを知れるわけではないですが、適度に気にしつつも、「気にしすぎても、結局子どもや親がやることは変わらない」という事実も重要視したいところです。
まとめ
校舎別合格実績は大事ですが、単年の総数ランキングだけでは本質を見誤ると私は考えます。
Exiv・中規模・小規模のタイプ差、在籍規模で割った密度、志望校分布、NNの寄与、年度差を重ねて見ることが、納得度の高い塾選びにつながります。最終的には、志望校と学習スタイルに合う校舎で走り切れることが最大の武器だと思います。
そして、重要なところなので繰り返しますが、「気にしすぎても、結局子どもや親がやることは変わらない」ということです。
\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介し始めました。
Follow @zeropapa_jukenTweets by zeropapa_juken