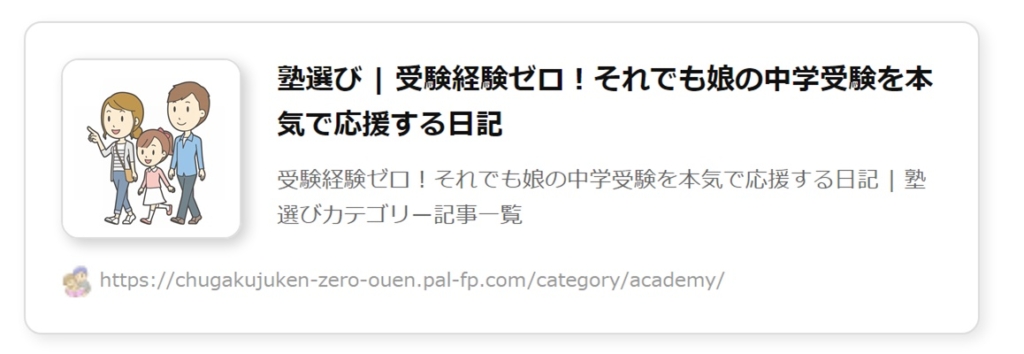サピックスの合格実績は「水増し」?—仕組み・勘違いポイント・正しい見方を保護者目線で徹底解説

「合格実績の水増し」と聞くと、いくつかの塾が思い浮かびと思います。ここで、「サピックス(SAPIX)の合格実績に水増しはある?」という話題を考えてみたいと思います。結論から言うと、「悪意ある水増し」と断定できる事例は一般論としても少なく、むしろカウントの仕方や用語の理解差が疑念を生みやすいと感じます。



私も娘の受験期に数字を追いましたが、見方を整えるだけで印象は大きく変わると思いました。本稿では、よくある誤解の源、塾側のカウント慣行、保護者が実務で使えるチェック方法をまとめます。
なぜ「水増し」に見えるのか:疑念が生まれる3つの文脈
「合格実績=合格者『数』」のインパクト
紙面やWebで目にするのは多くが「合格者数」です。同一の受験生が複数校に合格すれば、そのぶん数字は積み上がるため、総数の見た目は大きくなります。これはサピックスに限らず、早稲田アカデミー・四谷大塚・日能研など大手でも一般的に起こり得る現象です。
複数所属・併用学習の時代背景
近年は集団塾+個別指導+家庭教師といった併用が当たり前になりました。複数の機関が同じ合格者を「自塾の合格実績」として発表することは珍しくありません。数字が重なって見えるのは、この構造的要因が大きいです。
在籍基準・カウント基準のズレ
「どの時点から在籍とみなすか」「短期・講習生を含むか」などの基準は塾により差があります。昔より基準は明確化が進みましたが、完全統一ではないため、「横比較」だけで優劣を断じるのは危険です。
よくあるカウントの仕組み(一般論)
① 合格者「総数」=延べ数であることが多い
1人の受験生がA校・B校に合格すれば「2」として合算されます。塾の指導力評価を単純な総数だけで語るのは不正確になりやすいので、「在籍規模」や「志望校の難易度分布」も一緒に見るのが筋です。
② 併願戦略の高度化による「数字の膨らみ」
午前・午後入試の増加、出願の前倒し、抑え校の多層化で、1人当たりの合格校数が増える傾向があります。合格者数の伸び=学力上昇と短絡せず、併願パターンのトレンドも合わせて捉えたいところです。
③ 在籍・カウントのラインは塾ごとに差
「直前期だけ講習参加の子を含めるか」「模試のみの参加は除外か」など、ラインの引き方は各社のポリシーに依存します。ガイドラインの整備でグレーは減ってきたものの、完全に同一条件ではないという理解が必要です。
サピックスに対する私見:王者ゆえに「水増し」の必要性が低い
「悪意ある水増し」と言い切る前に
サピックスは大手塾の中でも合格実績の「絶対数」が圧倒的です。トップ帯の母集団規模と密度が段違いなので、数字を盛らずとも目立つと私は考えます。だからこそ「水増しの動機」が相対的に弱いのでは、と。
他社のカウントで個人的に引っかかる点
噂に聞いていたものの終わってみて知人に聞くとどうやらあるらしい早稲田アカデミーの個別指導付きのNN特待の扱い、教材が予習シリーズだからと四谷大塚による準拠塾分の合格カウントなど、「それも自塾扱いにするの?」と感じる場面はあります。ただ、これは私個人の感想であり、各社のポリシーを否定する意図はありません。
「サピックス=無謬」でもない
一方で、併願増による延べ数の増加や在籍基準の差といった構造的な「膨らみ」から完全には逃れられないのも事実です。だからこそ保護者側の読み方が重要になります。
数字の読み解き方:保護者ができる5つの補正
1. 在籍規模で割る(合格者数÷6年在籍数)
母集団当たりの成果で見ると、校舎力や面倒見の実力差が浮きます。総数だけで優劣を断じないのが第一歩。
2. 志望校レンジ別に分解する
「御三家・難関女子・早慶付属・中堅進学校」などレンジ別ヒット率を見ると、その塾(校舎)の得手不得手が見えます。「全体で強い=うちの志望校にも強い」とは限らないです。
3. 年度を縦串で見る(3年移動平均)
年度ブレは当たり前。3年平均や中央値で眺めると、偶然の当たり年に引っ張られにくくなります。
4. 志望校別講座・直前講座・外部冠講座の影響を分けて考える
志望校別講座や直前特訓だけ参加した外部生が実績に含まれるかは、塾ごとに方針が違うようです。「平常在籍の成果」と「直前講座の寄与」は別物として見ると誤差が減りますが、その情報は限られているのが困りものですね。私も別記事で紹介していますが、気になるのはブログやSNSなどを駆使して集めると良いと思います。たとえN=1でも、集めるとなにもないところでモヤモヤし続けるよりは参考になります。
5. 有志データの使い方:使うが、鵜呑みにしない
校舎別の集計や有志スプレッドシートは便利ですが、入力漏れ・偏りはつきもの。方角を示すコンパスとして使い、最終判断は自校舎の面談・配布資料で裏取りするのが安全です。
ケース(私の場合):疑うより使う
娘のときにやったこと
いくつかの塾について、我が家では「数字の見方を整える」→「志望校レンジで再集計」→「3年平均で安定度を確認」の順で見直しました。そうすると「水増し」というより、カウント慣行と併願の増加で数字が大きく見えているだけという印象に落ち着きました。
私の場合は、当時、通塾時間から早稲田アカデミーに興味が傾いていました。そのような中、早稲アカ最寄り校舎の実績は毎年微妙、全体実績はうさんくさい話も聞くけど上り調子、サピックスの候補は2校舎でどちらも電車に10分くらい乗る必要があるものの、どこからどう見ても実績は素晴らしいの一言。という感じでしたね。
校舎選びへの落とし込み
在籍規模で割ったヒット率と過去3年の変動幅を基準に校舎を比較し、体験授業と面談内容で最終判断。数字は入口、現場は出口だと感じます。
サピックスならサピクサーで事足ります。サピックス以外だと校舎別年度別の情報が簡単には得られません。塾だけではなく校舎レベルまでベストを探そうとするなら、子供が通い始める直前ではなく、子供が低学年のうちから3月ごろ以降に説明会や模試を受けるなどして候補校舎の実績データを集め始めたいものです。
内部リンクで深掘りできる実用記事
校舎別の数字を読む方法は、以下の自サイト記事で手順を図解しています。
在籍規模で割る・年度で並べる・有志データの留意点など、実務の型をまとめました。
また、早稲田アカデミーの校舎別実績をどう読むかも合わせて比較視点を持てると、全体像がクリアになります。
まとめ
「サピックスで合格実績の水増し!?」と聞くと構えてしまいますが、大半は「延べ数」という表現方法と併願戦略の高度化が生む見え方の問題と思っています。サピックスは絶対王者で、数字を盛らずとも強い—これが私の実感です。
他方で、在籍基準の違い・外部講座の寄与など、構造由来の「膨らみ」はゼロにできません。だからこそ保護者は、在籍規模で割る/志望校レンジで分解/3年平均で安定度を見るといった「読む技術」を持ち、面談・公式資料で裏取りする。数字は道具。うまく使えば、校舎選びも学習方針も、ぶれずに前へ進めると考えます。
\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)