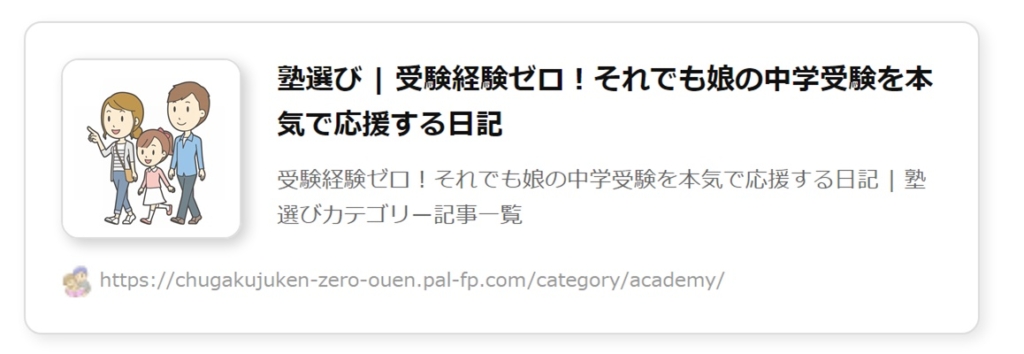サピックスの教材を完全解剖|デイリーサピックス・基礎力トレ・コアプラスの使い方から予習シリーズとの違いまで

サピックスの教材は「量より質」で有名だと聞きますが、実物を手に取ってみると、その評価に納得しました。授業と家庭学習が強く連動するように作られていて、復習前提の設計が一貫しています。



私は長女が四谷大塚系(早稲田アカデミー)の「予習シリーズ」でした。予習シリーズも評判が良いですが、私の体感としてサピックスの評判はそれを超えていました。予習シリーズユーザーにとっては、「サピックスの圧倒的な実績は、講師や所属している子の素質の差以上に、テキストの差なのではないか?」と、なにかと気になるものです。
私の場合、長女が早稲アカに通っているときに、職場の同僚からサピックスの4・5・6年のテキスト一式を譲ってもらうことができたため、予習シリーズとサピックスのテキストを並べて比較できました。
この記事では、その比較を交えながら、サピックスの教材の全体像、学年別の使い方、科目別の特徴、管理と復習のコツまでを保護者目線でまとめます。途中に私がやって効果的だった整理法や声かけも差し込みます。
サピックス教材の全体像:何で構成されているのか
教材体系の核は「デイリー」+「復習セット」
サピックスの中核は「デイリーサピックス」(授業用の小冊子)で、授業→家庭学習→確認テストのサイクルが一体化しています。同じ日の教材に「授業内で扱う問題」と「家でやり切る再演習」がセットになっていて、短いサイクルで定着を図る狙いを感じます。
反復のための「基礎力トレーニング」
算数の基礎計算や作業系の力を日割りで積み上げるのが「基礎力トレーニング」。毎日の歯みがき感覚で進めやすく、デイリーの「考える問題」とぶつからない難度になっています。「考える力」と「手のスピード」を別々に鍛える発想は、とても合理的だと思います。
このテキストは、四谷大塚の「予習シリーズ 計算」と比べると、計算練習というよりも1行問題対策の印象を受けます。その分、基礎的な解法について徹底的にマスターできることが期待できます。ネットでも同僚の話でも、意外とこの基礎トレを軽んじている方が多いようなのですが、私なら多くの成績帯でやって欲しくなるテキストだなと思います。
知識科目を固める「コアプラス」
理社(必要に応じて国語知識)では「コアプラス」の一問一答で抜け漏れを可視化。小テストやマンスリーに直結するため、「コアプラは短時間でも毎日触る」を合言葉にすると安定します。
予習シリーズ勢にも「四科のまとめ」がありますが、やはりサピックス生が取り組む「コアプラス」は気になります。なぜなら、「コアプラスに掲載されている問題は、サピックス生のほとんどが取ってくるということですから、特に難関校においてコアプラスに掲載されている問題を落とすことは致命的になる」からです。私は夕食後などスキマの10分だけ「クイズ大会」のように回して、テンポを上げました。
6年後半の「SS」や志望校別教材
6年の夏以降は志望校の形式に合わせた演習(いわゆる「SS」)が走ります。学校別の出題作法に寄せる最終調整で、素材の選び方がとても巧み。「広く強い」から「志望校に強い」へ焦点が絞られていきます。
予習シリーズ(四谷大塚)とのちがい:手元の実物比較で見えたこと
予習前提か、復習前提か
予習シリーズは「事前に読み込んで解く」流れが基本・・なはずですが、塾からは予習不要と言われるかと思います。でも、やはり予習をしておくと理解が深くなる効果が期待できるため、私は長女に予習してもらっていました。算数では例題を解いておき、理社では一緒に予習シリーズを読んでいました。
一方でサピックスは「授業で初見→家で再構成」が設計思想。そもそもテキストは授業で配られるため、事前に読んでおくことが物理的に不可能です。家庭学習の時間配分が根本から違うので、どちらが合うかは家庭の生活リズム次第だと感じます。
理社のテキストの大きな違い
予習シリーズの最も良いところは図表がフルカラーで、とても見やすいことではないかと思います。一方で、サピックスのフルカラーページはごく一部で、基本的に白黒です。
一方で、深さとしてはサピックスの方が圧倒的物量を感じます。文字数は同じぐらいでも、予習シリーズに載っていない用語や説明が多数見られます。もちろん、その逆もあるわけですが、サピックスのテキストに載っておらず予習シリーズに載っている量が1とすれば、サピックスのテキストに載っていて予習シリーズに載っていない量は3~4でしょうか。
ただ、多くの子にとって、これらの知識をすべて理解しようとすると相当な苦労が予想され、また、多くの知識は多くの入試・模試で出ないでしょうから、大いなる無駄ということもできてしまうなと感じていました。多ければ多いほど、やりきったときの安心感は得られるのでしょうが、多ければ良いというものでもなさそうです。
解説の「厚み」の差と親の伴走
同僚家庭の声もそろいますが、サピックスの解説は要点が絞られていて淡白です。予習シリーズのように図や手順の段階説明が厚いわけではありません。その分、授業で聞き切ることと、家で「自分の言葉でノート再現」することが重要になります。子供が自分でできないときは、親の伴走力で差がつきます。
もっとも、予習シリーズも解説が丁寧と定評がありますが、すべての解説が充実しているわけではありません。例えば、国語の解説は分厚くて期待させてくれますが、選択肢問題では不正解の選択肢の解説がないなど、ほとんど役に立ちませんでした。深くやり込もうとすると、どうしても親の伴走が必要となります。
問題の選び方:良問主義と「発想の切り替え」
サピックスは「A→B→Cへらせん状に深める」作り方で、一見少量でも「考える濃度」が高い。予習シリーズは網羅のよさが強みで、反復で盤石にするのが得意。どちらが優かではなく、「子どもの特性」との相性だと思います。思考の跳躍と出し分けが得意ならサピックス、段階的な積み上げで安心感を得たいなら予習シリーズがフィットしやすい印象でした。
学年別の使い方:4・5・6年でどう変える?
4年:習慣化のゴールは「翌日復習」
4年は授業翌日など、すぐにデイリーを「まるっと再演習」できるかが勝負でしょう。基礎力トレは朝10分で先に片づけ、夜はデイリーの「できなかった星印だけ」を丁寧に。結局、テキストがなんでも、やることは同じと思われます。スピードより「なぜそうなるか」のノート1ページを優先したほうが、5年で伸びやすいです。
5年:量が増える→やることを「絞る」
5年は科目横断で演習量が増加。全部を完璧に、は現実的ではありません。「A:必ず、B:できれば、C:切る」の3段階で交通整理し、A=デイリー基本+間違い直し、B=コアプラ弱点、C=既に定着のように優先度を家族で合意すると迷いが消えます。
6年前半:得点源の「固定化」
6年前半は「取るべき分野の取りこぼしゼロ」を確立。理社のコアプラス、知識の総完成は週1で弱点章だけ、算数は「計算・一行題のノーミス週」を作ると安定します。国語は知識と語彙の先回りが効く時期で、毎日10分の知識カードを習慣に。
6年後半:学校別の「型」へ寄せる
過去問とSS教材で「学校の言語」を身につける段階。算数は頻出の「解法の入口」を一列メモ化、理社はコアプラ・知識の総完成を「語句→説明」の逆引き練にして記述耐性を上げます。ここで「出し分けの瞬発力」が効いてきます。
科目別・教材の活かし方
算数:技術リスト化と「同値変形」の練習
デイリーの良問を「技術名」でタグ付けしていくと、入試直前の横断復習が一気に楽になります(例:「比の消去」「ダイヤグラム」「場合分けの枝立て」など)。同じ技術で別問題を3題回す「同値変形」は、サピ教材の真価が出る使い方と考えられます。
国語:記述は「根拠線→要約ワード→自分の文」
サピックスは長文の比重と記述の圧が大きめ。本文の根拠に線を引き、要約ワードを欄外に並べてから文にする手順を固定化すると再現性が上がります。言語知識は短時間×高頻度(例:朝5分・夜5分)で。
理科:観察語彙と因果のワンフレーズ
図と語彙が多い分野ほど、「だから」「一方で」で因果を1行にまとめる癖と、3語で説明(例:「上昇→冷却→凝結」)を足すと思考の芯ができます。
社会:データ→意味づけ→文章化
地理統計・公民数値は覚えるだけでなく「意味を言う」が得点差。グラフを矢印3本で要約→口頭説明→20〜30字で記述の順で、デイリー→コアプラ→マンスリーにリンクさせることができると思います。
管理と復習のコツ:家庭で回し切るために
「教材の物理管理」は最初の投資
予習シリーズ準拠の塾でもプリント整理は必須です。王道のクリアファイル(週別)+A4ボックス(科目別)で「今週回す束」を作っておくと迷いが激減です。終わった紙の「直しだけ」を別ファイルに分け、週末に「直しファイルだけ」を総点検すると、努力が得点に変わる瞬間が見えやすいです。私もここはかなりこだわりました。
直しは「誤答ラベル」で可視化
誤答に「原因ラベル(計算・読み違い・方針・知識)」を貼ると、次の1週間の優先順位が自然に決まります。「原因別の再演習」が最短距離です。
マンスリー・組分けの「教材返り」
テストで間違えた部分は、とき直しだけでなく、テキストに戻るのも塾のテキストによらず鉄則ですね。テスト後48時間以内に「×の技術リスト→デイリー該当回に戻る」をやると、同じ穴で二度こけない。テストは教材へ戻るためのナビだと割り切ると、復習の質が一段上がります。
予習シリーズとのハイブリッド:家での補助は「薄く広く」
「厚い解説」で穴埋めする
サピックスの解説が端的でハイコンテクストなので、説明が欲しい単元だけ予習シリーズの解説や市販参考書で補助するのは現実的だと思います。ただし「同じレベルの問題だけ」を補助に回すのがコツで、難度のズレは避けたほうがいいです。
類題は「少量・高密度」
1題に30分「考え切る」を週に数回入れると、発想転換の筋力が育ちます。量で埋めるより「似ているけど入口が違う」問題を3題だけ精選、が効きます。
サピックスが向く子・向かない子と親の関わり
向く子
初見で粘れる子、説明を聞いて「自分の言葉」に変換できる子、図や式の再現が好きな子は、サピックス教材の良問主義と相性がいいです。「なぜを面白がれる」かが指標。
向かないケースへの工夫
手順型の分かりやすい導入を好む子は、導入だけ親が「3行プリント」にして渡すと切り替えやすいです。復習中心のリズムに乗れるまでは親のファシリが効きます。
親のサポート量を見積もる
解説が薄い=親の伴走が増えるは事実です。平日の「質問バッファ15分」を家族計画に組み込み、土日に「直しファイルの棚卸し」をすると、教材の設計と家庭の運用が噛み合います。
さらに理解を深めたい方向け(関連内部リンク)
合格実績や偏差値の見方など教材の外側の文脈も押さえると、日々の優先順位が決めやすくなります。次の記事も合わせると全体像がクリアになります。
→ [サピックスとは?「考える力」を鍛える最難関向け進学塾のしくみ・強み・向き不向きまで保護者目線で徹底解説]
→ [サピックスのクラス分けを完全解説|αとアルファベットの違い・昇降の仕組み・テスト頻度・校舎差まで]
オンラインでもできる、中学受験向けの立て直し
地方在住や送迎の都合で通塾の選択肢が限られる場合でも、オンラインで中学受験対策を進めることは可能です。
塾フォロー型の個別指導(オンライン対応)という選択肢があります。
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中で公式情報や条件を確認した限り、候補の1つとして比較対象に入れやすい印象で、資料を取り寄せておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
SS-1では無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
例えば、成績が伸び悩んでいる・苦手がいつまでも苦手なまま…などの悩みが出始めているなら、個別指導を検討し始めてもよいかもしれません。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
体験談も参考になりますが、私自身はまず公式資料を正しく理解することが大切だと考えています。
子どもが頑張っているからこそ、親も判断材料を集めるという形で一歩進めておくと安心です。
まとめ
サピックスの教材は「授業→家庭学習→テスト」を高速循環させる復習中心の設計で、良問を少量・高密度に回す思想が貫かれています。
解説の薄さは「自分で再構成する力」を鍛える余白で、そこを親が物理管理・時間設計・直しの可視化で支えると、教材の力が最大化します。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)