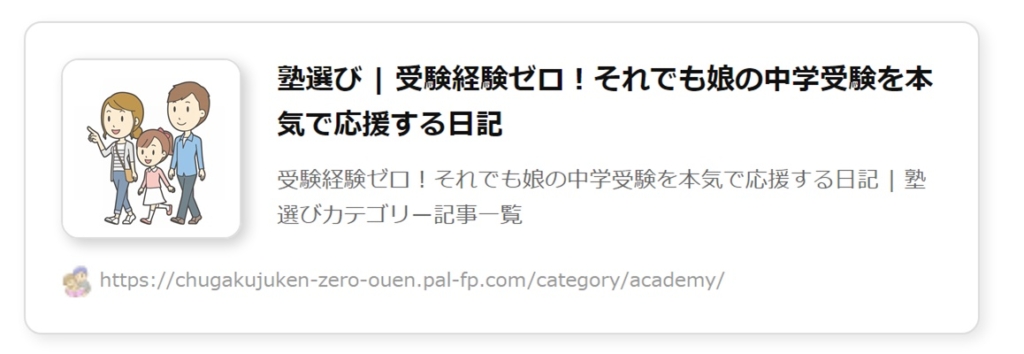サピックス「マンスリーテスト」完全ガイド|出題範囲・昇降・平均点の目安と学年別対策、直しの型まで整理

サピックスの「マンスリーテスト」は、直近1か月の学習定着を測る定期テストです。位置づけは一見シンプルでも、クラス昇降に直結し、その後の課題設計を左右するため、親としては毎月の学習サイクルのハブとして扱うのが得策と言われています。



大手塾では、塾によって頻度は違うものの定期的に範囲のあるテストが行われ、テストに向けての対応やテスト後の振り返りは共通しています。
この記事では、実施学年・出題範囲・昇降の仕組みから、学年別の対策・当日の立ち回り・復習テンプレまでを網羅。さらに「組分けテスト」「復習テスト」との違いも明確化し、家庭で再現しやすい運用方法に落とし込みます。
マンスリーテストの全体像(対象・形式・ねらい)
対象学年と名称の変化
原則として小3〜小6前半までが対象です。小6の後半は「マンスリー実力テスト」となり、範囲が広がり実戦色が強まるのが一般的です。目的は一貫して「定着確認」→「学習計画の微修正」にあります。
科目の目安
4科(国語・算数・理科・社会)。年度差はありますが、標準〜やや難の混在が基本。基礎〜標準問題の取り切りが成績を左右しやすく、平均点は中〜やや高めに出やすい回もあります。
出題範囲と難易度の特徴
直近1か月のカリキュラム範囲が中心。「教わった内容を翌月も再現できるか」が問われ、思考・読解・知識の「橋渡し問題」が得点差を生みます。正答率60〜80%帯の取りこぼしを最優先で回収できるご家庭が、偏差値を安定させているようです。
他テストとの違いと「昇降」の実像
「組分けテスト」との違い
組分けテストは出題範囲なしで大幅昇降が起きやすいのに対し、マンスリーは範囲あり×昇降幅は中程度。日々の学習が最も反映されやすいため、コース基準の「現実的な更新」に向いています。
「復習テスト」との違い
復習テストは小テスト寄りでクラス昇降とは直接連動しにくいのに対し、マンスリーは昇降データに直結。毎月の「学力会議」の材料と捉え、テスト後48時間の復習で学習計画を一段深く更新すると効果的とされます。
昇降の仕組みとメンタル設計
昇降は4科合計が軸(校舎運用による細部差あり)。「昇降=評価」ではなく「次の一手の入力」だと捉えると、一喜一憂が減り改善速度が上がるはずです。科目バランス(弱1強3より均等4)が安定の鍵と考えられます。
学年別の対策と到達目安
小4:型づくり期(読む・書く・数えるの基礎を「時間内に」)
- 算数:計算の無意識化と図・表先行。標準問題の取り切りが命綱。
- 国語:設問条件に線引き→要約→骨子→清書の型を定着。
- 理社:語句→因果→具体例の三段ロジックで説明できるか。
「時間内に正確に」という処理力を最優先で鍛えます。
小5:伸長期(思考×情報処理の接続)
- 算数:条件整理→捨て順→再訪の時間設計。
- 国語:設問タイプ別のテンプレ(指示語・要約・記述)。
- 理社:グラフ・統計・時事の読み取りを演習で補強。
志望校帯を意識しつつも、マンスリーは「範囲内の完成度」で稼ぐのが王道です。
小6前半:受験設計期(コアの取り切り×速度)
- 算数:「取るべき中問」→「拾う小問」→「触るだけの難問」の三段優先。
- 国語:設問に沿った根拠の引用位置を即断。
- 理社:頻出テーマの知識×資料題を往復。
偏差値の安定=標準帯の落としを消すこと。ここが合格力に直結します。
小6後半:「マンスリー実力テスト」期(再現性×志望校適合)
範囲は総合寄りになり、学校別対策との両立が課題。合格力判定・学校別演習と並走し、「今週の弱点→来週の改善」の短サイクルで回します。
科目別の出題傾向と対策のツボ
算数:図表先行と優先順位の固定
- 読み→図表→条件書き込みを先に行い、捨て順を決める。
- 標準の取り切り=合格点の下支え。ラスト3分の見直しは死守。
- 計算・一行問題の失点ゼロ化が、上位帯での分水嶺です。
国語:設問制約→要約→骨子→清書
- 設問の制約に下線、該当箇所の根拠囲い。
- 要約→骨子で冗長さを削る。
- 記述は「事実→理由→結論」で整えるとブレません。
理科:語句と現象、数値の往復
- 語句→現象→数値関係を口頭で説明できるかチェック。
- 資料題の単位・桁感を確かめる習慣化。
- 頻出実験は表に落とし、作業手順→結果→考察で回す。
社会:因果の鎖と資料読解
- 地理×歴史×公民の横断因果で記憶をつなぐ。
- 地図・統計の“読み取り語彙”(増減・割合・構成比)を固める。
- 用語は「定義→具体例→反例」まで用意すると得点が安定。
1か月サイクルで回す「家庭運用テンプレ」
①直前1週間:体を温める
- 毎日15分の計算+語彙で速度と基礎を維持。
- 範囲表から「落とせない単元」リスト化→見出し教材で再確認。
- 睡眠優先、前日は持ち物と動線を確定。
②当日:時間設計で「止まらない手」
- 冒頭2〜3分で見取り図→解く順・捨て順を即決。
- 迷った問題は印だけ付けて後回し。
- 最後3分はケアレス専用に確保。
「止まらない手」が実力の最大値を引き出します。
③48時間復習:結果を「行動」に変換
- 当日夜:ミス分類(読み落とし/計算/知識/戦略)。
- 翌日:正答率60〜80%帯の取りこぼし回収。
- 2日目:類題3問×時間計測で再現性を点検。
この48時間テンプレは、偏差値の「ブレ」を縮める即効薬です。
よくある疑問と誤解の整理
「平均点が高い回で差がつく?」
つきます。高平均回ほどケアレス1つの重みが増し、標準の取り切り能力が順位を決めます。作業手順の固定化が最良の対策です。
「過去問は意味ある?」
意味はないとはいえないと思いますが、それよりも「取り組み順」が肝心かと思います。まずは教わった単元の類題→その後に過去回で時間感覚、の順が効率的。復習優先を崩さないのがコツです。
「昇降が不安定で心配」
科目バランスの偏りが原因になりがち。弱科の「標準帯」を底上げし、強科のケアレス減で合計点の底上げを狙います。
「組分け/公開模試との両立は?」
範囲あり(マンスリー)で「基礎の再現性」、範囲なし(組分け・公開)で「実戦対応力」を鍛える役割分担にすると、負荷が分散します。関連の全体像はこちらがわかりやすいです →
関連:サピックス模試を完全ガイド
連携して読むと効率が上がる関連記事
- 教材の使い分けを確認:デイリーサピックスやコアプラスの役割整理 →
関連:サピックスの教材を完全解剖
- 昇降の仕組みを確認:α・アルファベット帯/昇降の頻度や校舎差 →
関連:サピックスのクラス分けを完全解説
まとめ
マンスリーテストは「毎月の定着確認×クラス運用の指標」。
範囲あり×標準帯の取り切りで安定しやすく、48時間復習テンプレで得点の再現性を高めると、組分け・公開模試にも好影響が出ます。昇降は評価ではなく「次の一手の入力」。科目バランスの底上げとケアレスの削減を徹底し、短いサイクルで改善→検証を回す——これが、合計点をなだらかに引き上げる最短手だと考えます。
\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)