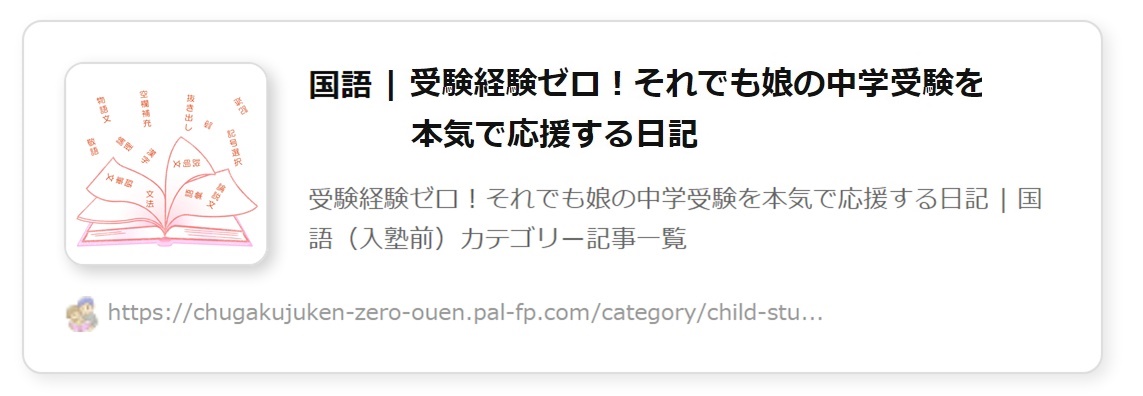予習シリーズ国語の全貌|構成・特徴・効果的な活用法を保護者目線で徹底解説
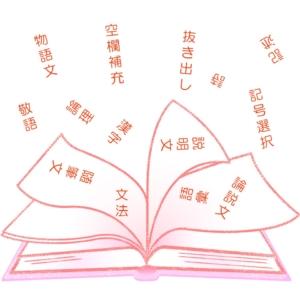
「予習シリーズ国語」というと、中学受験を目指すご家庭では一度は耳にするテキストです。しかし、市販はされているものの、入塾前だと予習シリーズ準拠の塾に入塾するかはわからず、あるいは確定していても改定の可能性があり、入塾前にその内容や構成を詳しく知る機会は意外と限られています。一方、入塾後だと、塾に任せられることが増えるので、じっくりと予習シリーズテキストを見ることも減っていきます。



この記事では、実際の紙面内容を踏まえて構成・特徴・注意点・効果的な使い方を、保護者の立場から解説します。私自身も、娘の受験準備でこの教材と向き合い、使い方を工夫してきました。その経験を交えてお伝えします。
予習シリーズ国語の構成と特徴
全体の構成
予習シリーズ国語は、基本的に以下の4つのパートで構成されています。
- 読解問題のポイントの説明
- 基本問題(短文読解や語句確認)
- 発展問題(応用的・入試レベルの文章題)
- ことばや文法など(語彙、文法知識)
読解問題の特徴
- 塾やクラスによって扱う文章が異なる場合があります。
- 解答解説は分厚く、一見頼もしいですが、記述問題では答えありきの説明になっていることも多く、子どもには理解しにくい言い回しが見られます。
- 選択問題では、不正解の選択肢に関する解説が省略されているケースが多く、誤答分析がしにくいのが難点です。
基本問題
- 読解問題に入る前のウォームアップとして設計。
- 語句の意味確認や短文読解が多く、基礎力の底上げに有効。
- 上位のクラスでは省略されがち。
発展問題
- 記述量が多く、入試問題に近いレベル感。
- 「本文の要旨をまとめる」「理由を説明する」など、記述力と論理的思考力の両方を問われます。
- 制限時間を設けて演習すると、本番の時間配分練習になります。
ことば・文法
- 漢字・熟語・文法事項を網羅的に学べます。予習シリーズ「漢字とことば」と合わせて学習していくことになります。
- 毎週の積み上げで、長期的な国語の知識強化につながります。
- 娘の場合は、ここを侮ることなく、きちんとルーチンの学習に組み込み、テストに向けてしっかりと反復させました。
\ 毎日の漢字練習が「作業」から「成果」へ! /
「10回書けば覚えられる」から卒業しませんか?
我が家の実践記録と工夫を17,000字の大作にまとめ、さらに自作の「スーパー漢字復習ツール」もセットにした記事をnoteで公開しました。
「効率的な覚え方」「忘れにくい復習法」「プリント活用」を一つの記事に凝縮しています。ぜひ以下からご覧ください!
https://note.com/zeropapa_juken/n/n0df46d444fbf
予習シリーズ国語のメリットと注意点
メリット
- 網羅性が高く、基礎〜応用を一冊で回せる。
- 大手塾である四谷大塚や早稲田アカデミーで採用されている安心感。
- 別冊の「予習シリーズ 漢字とことば」を合わせると、ことば・文法分野が充実しており、サピックスにも十分に対抗できる。
注意点
- 説明が難解で、子どもが自力で理解しにくい部分がある。
- 解説の質にばらつきがあり、また、回りくどい場合もあり、解説の文量の割に納得感が得にくい場合も。
- 全部を完璧にやろうとすると時間が足りなくなる。
学年別の予習シリーズ国語の特徴
4年生:基礎固めのスタートライン
4年生の国語では、まず文章を正しく読み取り、設問に答える基本力をつけることが中心です。物語文・説明文・随筆文など幅広いジャンルが登場しますが、文章量はまだ短く、設問も直接的な問いが多いのが特徴です。
-
物語文の読み方
4年生の段階では「登場人物の気持ち」や「場面の変化」を押さえることが中心です。 -
説明文の読み方
段落ごとの要点をまとめる練習が多く、図や表の情報を文章と照らし合わせる力も養います。 -
ことば・文法
四字熟語・慣用句なども徐々に取り入れられますが、覚えやすい例が多めです。
私の場合、娘が4年生のときは、この時期の読解問題に対して「もっと簡単かと思った」と言っていました。それでも、復習を繰り返すうちに選択肢問題は正答率が上がっていきました。
5年生:思考力を深めるステップ
5年生になると文章量・設問の複雑さが増し、根拠を明確にして答える力が求められます。
-
記述問題の比重増加
記述は、文章構成力も問われます。この段階では、解説を読んでも子どもが「なんでこうなるの?」と感じることが少なくありません。 -
発展問題の位置づけ
読解力が一定レベルに達していないと手こずる問題が多いです。 -
語彙・文法の深化
敬語や接続語の使い方、品詞の分類などがより体系的に登場します。
我が家では、「授業で間違えた問題は、授業で解説を受けているはずだが、本当に理解しているのか」を確認するためにも、授業後に復習する時間を設けていました。時間はかかりますが、思考の道筋を一緒にたどる経験は子どもの力になります。
6年生:実戦力の完成期
6年生の予習シリーズ国語は、志望校入試レベルの問題への対応力を磨く時期です。ただし、早稲田アカデミーの場合は講師裁量も大きく、予習シリーズの代わりに適度な難易度の学校の過去問を使うこともあります。
-
高度な記述・論述
「なぜそう考えたのか」を文章中の根拠と結びつけて説明する力が不可欠です。 -
多様なジャンルの文章
小説・随筆・評論など、これまで以上に幅広い文章が出題されます。もちろん、大人顔負けの語彙力・背景知識も試されます。
私の娘の場合、6年生の秋以降は塾の授業を休んだりしつつ、予習シリーズ本体よりも過去問に時間を割きましたが、ことば・文法部分は最後まで予習シリーズで復習していました。
家庭学習で予習シリーズ国語を使うコツ
解説を「そのまま信じすぎない」
予習シリーズの解説は分量が多く一見頼もしいですが、記述問題では難しい言い回しや模範解答に寄せすぎた説明が目立ちます。お子さんが理解できる言葉に置き換える作業が必要です。また、選択肢問題では、間違っている選択肢の解説がないので、理解した気になって終わることも警戒する必要があります。
「できる問題」と「できない問題」の仕分け
すべての問題を均等に取り組む必要はありません。家庭学習では特に、苦手分野を明確にして重点的に取り組むのが効率的です。
語彙・文法は毎週繰り返す
「ことばと文法」部分は蓄積型の学習です。1回やって終わりにせず、週単位で繰り返す習慣をつけることが大切です。
オンラインでもできる、中学受験向けの立て直し
地方在住や送迎の都合で通塾の選択肢が限られる場合でも、オンラインで中学受験対策を進めることは可能です。
塾フォロー型の個別指導(オンライン対応)という選択肢があります。
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中で公式情報や条件を確認した限り、候補の1つとして比較対象に入れやすい印象で、資料を取り寄せておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
SS-1では無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
例えば、成績が伸び悩んでいる・苦手がいつまでも苦手なまま…などの悩みが出始めているなら、個別指導を検討し始めてもよいかもしれません。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
体験談も参考になりますが、私自身はまず公式資料を正しく理解することが大切だと考えています。
子どもが頑張っているからこそ、親も判断材料を集めるという形で一歩進めておくと安心です。
まとめ
予習シリーズ国語は、中学受験国語の学習設計において非常に優れたベース教材です。しかし、全てを一人で消化するのは難しく、保護者のフォローや別教材の併用が不可欠です。特に記述問題は、解説を鵜呑みにせず「どうしてそう答えるのか」を親子で話し合うことが大切だと感じます。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は参考記事です。