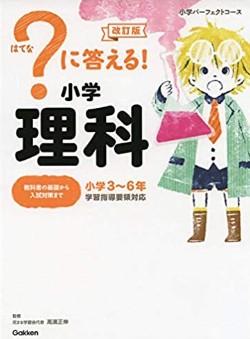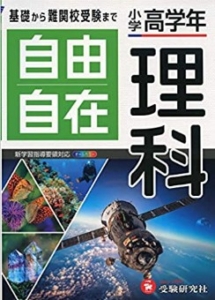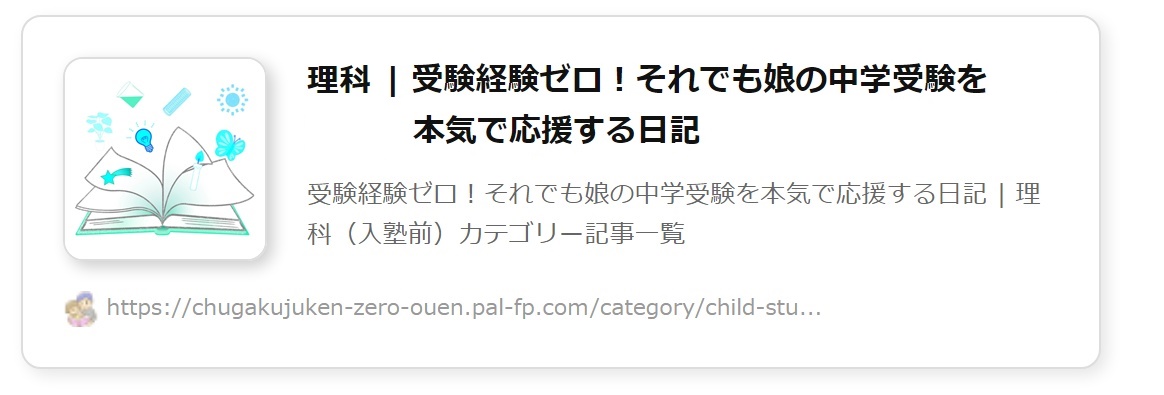予習シリーズ理科の学年別活用法|家庭学習で差をつける勉強法と注意点
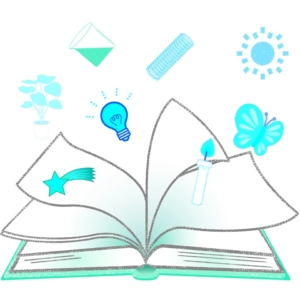
中学受験において理科は、暗記だけでなく「理解」や「思考力」が問われる重要科目です。四谷大塚の「予習シリーズ 理科」は、多くの進学塾で採用されており、学年別にカリキュラムや内容が緻密に組まれています。



ただし、実際に使ってみると、4年生の安心感と5年生以降の情報量の差、図表や表の暗記の負担、そして計算問題の少なさなど、注意すべきポイントが見えてきます。私自身、娘の学習に使ってきて、良さも課題も両方実感しました。今回は、学年別の特徴と家庭での活用法、他塾教材との違いも含め、詳しくお伝えします。
学年別の予習シリーズ理科の特徴とポイント
4年生:理科の楽しさを知る時期
4年生の予習シリーズ理科は、1回分6ページ構成で、自然や身近な現象から入ります。
扱う内容の幅
春夏秋冬の自然観察、植物の成長、動物の体のつくり、天気の変化など、学校の理科と重なる内容が多く、親も教えやすい単元が並びます。
カラー図表の魅力
写真やイラストが豊富で、子どもが直感的に理解しやすいのが強みです。例えば植物の発芽実験では、芽の出方や葉の形を写真で確認でき、「百聞は一見にしかず」を実感します。
注意点
内容が易しいため、子どもは「理科は簡単」と思い込みがち。しかし5年生になると覚える量が倍増します。私の場合は4年生から、資料集を併用することを家庭で追加し、興味を持った分野を深掘りするようにしました。参考書としては、「?に答える!小学理科」と「小学高学年 自由自在 理科」がダントツでおすすめです。
5年生:情報量と難易度の急上昇
5年生の理科は1回分8ページ、文字は小さくなり、覚えるべき知識が急増します。
分野の広がり
地学(天体・気象)、物理(てこ・ばね・電気回路)、化学(物質の性質・状態変化)、生物(生態系・人体)と、ほぼ全範囲を網羅します。
図や表の暗記の負担
「星座と出現時期の表」「金属の性質一覧」「人体の器官と働き」など、そのまま覚える必要がある資料が増えます。娘は天体分野の星座表を覚えるのに苦戦し、リビングの壁に貼って毎日少しずつ確認しました。
計算問題の不足
物理分野では計算が必要ですが、予習シリーズ単体だと演習量が無いに等しく、演習問題集に取り組むことで最低限という印象です。一方、早稲田アカデミーであれば錬成問題集も取り入れて問題量を確保することができます。
さらに、私の場合、原田プリント(https://sansu.info/)を基礎固めに併用することで、算数並みに計算練習に取り組んでもらうことができるようになりました。
6年生:入試直結の総合力養成
6年生では、全分野の総復習と入試レベルの演習が中心になります。
分野横断型の出題
「水溶液の性質+金属の反応+温度変化」など、複数分野を組み合わせた問題が多くなります。後期になると予習シリーズや演習問題集の問題も応用問題となっていきます。なお、早稲田アカデミーでは早稲アカオリジナルの「マスターテキスト」に軸足が移っていきます。
記述問題の増加
実験結果から理由を説明する問題が増えます。例えば「天秤が水平になった理由を説明せよ」のように、ただの暗記では解けません。娘の場合、口頭で説明させてから書かせる練習を繰り返しました。
資料の読み取り
グラフや表の読み取りは入試で頻出です。日頃から実験資料や観測データを見せ、「何を表しているか」「何がわかるか」を話し合う習慣が効果的です。
家庭でできる予習シリーズ理科の効果的な活用法
資料集・図鑑の併用
理科は実物や写真で理解が深まります。例えば「岩石の種類」では実物図鑑、「昆虫の成長」では動画を見せるなど、五感に訴える学習を心がけました。予習シリーズでも多くの写真やイラスト、図や表がありますが、資料集や図鑑を加えていくと理解が深まります。
復習の小分け
情報量が多いため、1回分を1日で覚えるのは非現実的です。3〜4日に分けて学習するサイクルを作ると定着しやすいです。
演習不足の補強
物理・化学の計算系は特に演習不足になりがち。市販の演習問題集やプリント教材を加えることで、入試レベルに対応できる力がつきます。
他塾教材との比較
ビジュアルの強み
サピックスや日能研のテキストと比べると、予習シリーズはカラー写真や図解が豊富で、初学者でも理解しやすいです。
文章解説の課題
一方で、背景や理由の説明は簡潔すぎることも。そこは家庭で補足しないと応用が利きません。やはり参考書や資料集の併用はほとんど必須ではないかと思っています。
まとめ
予習シリーズ理科は、視覚的理解と体系的カリキュラムが魅力ですが、学年ごとに大きな変化があります。4年生は興味を広げ、5年生で基礎を網羅し、6年生で総合力を固める。この流れを意識し、演習不足や説明の薄さは家庭で補うことで、得点源にできます。家庭での学習サイクルづくりと、適切な補助教材の活用が、合格への近道だと考えます。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は、関連記事です。