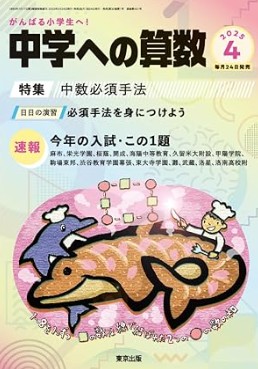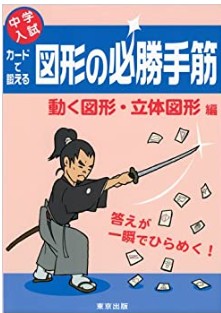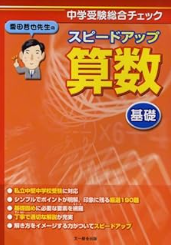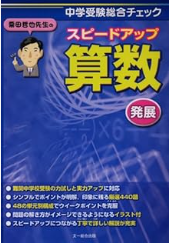【難関校向け】中学受験算数|参考書・問題集の活用法とおすすめの使い分け方

難関校を目指す中学受験に向けた算数の学習では、どの参考書・問題集をどう使うかが結果を大きく左右します。わが家も最初は、何冊も買ったはいいものの、うまく使いこなせず迷走しました。
目的に合った使い分けができれば、参考書は最強の味方になります。今回は、実際に家庭学習で使ってみて効果を感じた活用法をご紹介します。
参考書の役割と選び方を知っておこう
目的に応じて「知識補充」と「実戦演習」を分ける
参考書には知識をインプットするためのものと、実戦に近い問題でアウトプットするものがあります。まずは「基礎を固める」ための参考書を選び、そのあとで応用・実践用に切り替えていくのが基本です。
「レベル」と「志望校層」を意識する
難関校向け・中堅校向けなど、参考書には対象レベルがあります。子どもの現在地と志望校のギャップを冷静に見極め、背伸びしすぎない選択が大切です。特に高学年からの切り替えは慎重に。
冊数を絞って「使い切る」ことが何より大事
たくさん買って満足するのではなく、1冊を徹底的にやり込む方が効果的です。復習しやすく、定着も図れます。まずは親が全体像を把握して、習熟度に合わせて選びましょう。
難関校向け参考書・問題集の活用法
『中学への算数』で思考力を育てる
言わずと知れた定番の一冊。「考え抜く力」や「粘り強さ」を養うのにぴったりです。特に日々の演習問題や巻末の「発展問題」は、解法の引き出しを広げるのに役立ちます。
毎号購入して全部勉強するトップ層もいますが、月ごとに単元が別れているため、苦手であったり得意を伸ばしたりしたい分野だけ購入して取り組むのも良いですね。
また、「うちの子にはレベルが高すぎるはず・・」は思い込みかもしれません。引用されている入試問題は必ずしも難関校ばかりというわけではなく、難問というよりも、良問がたくさん掲載されている問題集となっています。
『プラスワン問題集』『ステップアップ演習』
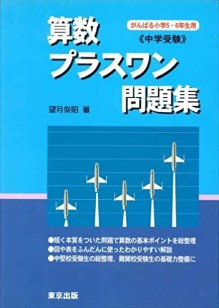 |
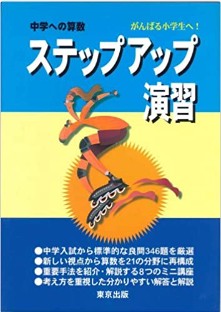 |
古い問題集ですが、難関校への登竜門的な問題集ですね。基礎~応用のバランスが良く、着実にレベルアップできる構成が魅力。
若干プラスワン問題集の方が難しいとされ、どちらか1冊であればプラスワン問題集を選ぶ人が多い印象ですが、好みで決めるのもよいと思います。いずれにしても量がちょうどよく、解きごたえがあります。
『算数 塾技100』は「技」を知るための辞書的存在
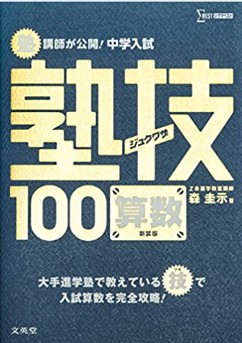 |
分野別に整理されていて、テクニックの確認・復習に最適です。特定単元が苦手なとき、辞書のように使うのがおすすめ。解き方を知った上で、他の問題集で練習する形が効果的です。
もちろん、全部解くとかなりの力がつく問題集です。計画的に学習を進めていきたいですね。
『図形の必勝手筋』は図形のパターン学習に有効
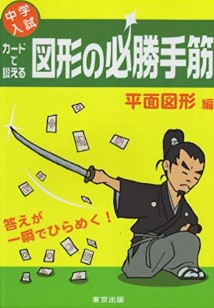 |
図形に苦手意識がある子には特に有効です。「見えない線を引くセンス」が身につくよう構成されていて、類題への応用力も養えます。図解が丁寧なので家庭学習でも取り組みやすいです。
難度がA~Dまであり、C~Dになってくるとかなりの難問となり、ここまでこなせるころには図形が得意になっているはずです。
薄い問題集に見えて、本に掲載されているのは例題でいわば練習段階あり、問題と答えが記載された大量のカードが本番ですので、かなり歯ごたえのある1冊となっていますね。
『スピードアップ算数』で処理力と正確性を強化
一問ごとの時間配分やスピードを意識する訓練に最適です。試験本番を意識したトレーニングができ、計算ミスやケアレスミスの減少につながります。
評判のいい問題集ですが、他の問題集と内容がかなり異なっていて、お子さまが算数をそれなりに得意でないと、途中で挫折する可能性が高い1冊かなと思います。
まとめ
中学受験算数において、参考書の使い方次第で成績は大きく変わります。大切なのは、子どもに合ったレベルと目的に応じた教材選び、そして継続的な活用です。
やみくもに数をこなすより、「1冊を使い切る」ことの価値を実感しています。ご家庭でも、ぜひ学習状況に応じてうまく活用してみてください。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)