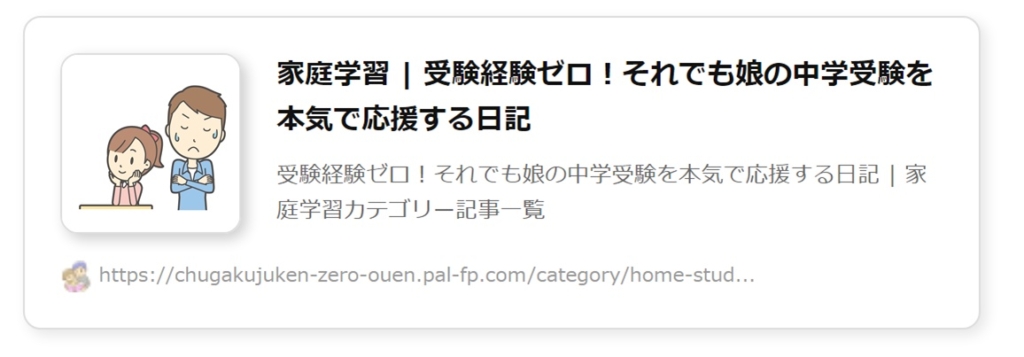2020年(小3)の振り返り
\ この学習法が娘の成績を変えました! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537

みなさま、新年、あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回は、去年(娘は小学校3年生)の振り返りをしてみました。
2020年度は、3年生に上がったと思ったらコロナ禍で学校がはじまらず、家でなにをすればいいかよく考える必要がありました。当時は、いつから学校が始まるかもわかりませんでしたので、先取りで3年生の範囲を終えていた算数と漢字はともかく、理科と社会についてはとても気になっていました。
まずは学校から配布された課題については、算数は先取りできていたため無視するものの、ほかは4教科以外もきちんととりくみました。音楽などはリコーダーだったと思いますが、恒例の「ドラえもんのおもしろ攻略」も使いながら、娘も楽しんでいましたね。
学校の課題以外については、勉強漬けも違うだろうけど、ここぞとばかりに遊び倒すのも違うと思い、学校にいる時間割と全く同じ時間帯で、学校からの課題を含めて何かしら勉強することを目標とすることにしました。英語はもちろん公文ですね。
社会は何をすればいいかもよくわからず特に追加で何もしませんでした。一方で、理科については、3年生の範囲を休校中に終わらせるだけの学習はしました。具体的には、算数でお世話になっている「これでわかるシリーズ」と、と公文の問題集である「理科にぐーんと強くなる」を使いました。
国語は、漢字については先取りを進めました。読解については理論を先行させ、親向けの読解の技術についての書籍を要約してプリントを作って教えたり、読解に役立つ説明や問題に加えて文法解説もついている「はじめての論理国語」を使って学習しました。直近の娘の模試の結果を見る限り、頭ではある程度わかっていても、理論を実践で使うレベルには至らず、今思えば、理論を先行させすぎてしまったと思っています。この時期にきちんと読解問題の練習を地道に進めていれば、今、娘は国語への苦手意識がそれほど高くなかったかもしれませんので、私の中では大きな反省点です。
算数は、先取りや現学年での難しい問題に挑戦し、また、きらめき算数脳やきらめき思考力、図形を描けるようになるために天才ドリルなどにも取り組みました。途中、かっこがある計算、暦算などなど、「苦手かな?」と思った部分は、別途プリントを用意するなどして、苦手を潰す余裕があるほど、時間的なゆとりがありました。「苦手は早期発見、早期克服が必要」であることを理解したのはこの時期です。
模試を受けたらほとんどの方が復習すると思いますが、「その問題をやり直したら、理解できたし解けた」で安心するのではなく、その中で子供の「苦手」を感じたら、どのように、そして、どこまで手広く復習して克服するかが重要と考えています。そして、今後、塾が始まりテストが多くなったとき、子供の「苦手」に気づくことができるかどうか、そして、限られた時間の中で、効率よく苦手克服に対応できるかどうかが鍵なのだろうと思っています。
\ 毎月、新たに多くの方が復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
休校が終わると、あるべき状況に戻り、日々の学習はよくよく優先順位を考えて進める必要がでてきました。
算数を重視し、5年生以降に習う難しいとされる単元があることを考慮し、先取りを進めることにしました。勉強机に向かっているときだけではなく、生活する上でその知識を使い、身近になってもらうためです。これは、下剋上受験で有名な桜井信一さんの考えを導入しています。一方で、思考力を養うことを考えたとき、やはり難しい問題に触れるということは必要だと思っていて、時々ではなく定常的に頭を使ってもらうことを意識して学習計画を立てました。
しかしながら、あまりに国語の読解が手薄になってしまっていました。娘の国語の成績を見てみると、良かったと言えるのは6月に受験して決勝に招待いただいた四谷大塚の全国統一小学生テストくらいで、2年生の3学期以降、国語の順位が上位10%に入ることはほぼありませんでした。
それなのに、「中学受験は算数が重要!」「国語は論理が重要!」という考えに私の頭が支配されてしまっていました。普段、仕事柄、極端な解釈は避ける習慣ができているつもりでしたが、中学受験においてはそれが完全には発揮されていませんでした。特に、後者の論理傾倒については、「論理と読解の技術的な理論を理解すれば、成績は上がるはず」と、完全に楽観的なシナリオを描いてしまっていました。業務では、私の悲観的な性格こそが、複雑なプロジェクトを進める上ではシナリオ策定上有利に働き(想定されるワーストケースに備えることになるので)、割と何でも成功させることができている要因の1つと思い自信を持っていたのですが、プライベートでは全然だめでした。極端な解釈とシナリオ・プランニングの不完全性は、とても大きな反省点でしたが、プラスに考えると、3年生の時期に、自分ができていると思っていた数少ない部分ですら、実はまだまだ不十分であることに気がつくことができてよかったと思っています。
娘の国語の話に戻ると、8月に受けた、早稲田アカデミーのチャレンジテストで全ての記述問題が白紙だったことで、その理解が誤ったことにようやく気づき、その後、日能研の全国テストで、読解の記述以前に、作文の能力に課題があることに気付かされました。いまは算数の優先順位を下げて少しは対応することができます。でも、私が楽観的に考えていた結果がこれですので、塾に通い始めれば国語の成績も上がるはずというのもまた楽観的なのでしょう。そうだとすると、誰でも国語が得意になるはずですし。そう考えると、塾が始まってから娘の国語の課題に気づいていたのでは、使える時間も限られますし、もしかしたら手遅れになってしまっていたかも、とも思っていて、親の役割は思った以上に大きいということを実感しています。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。