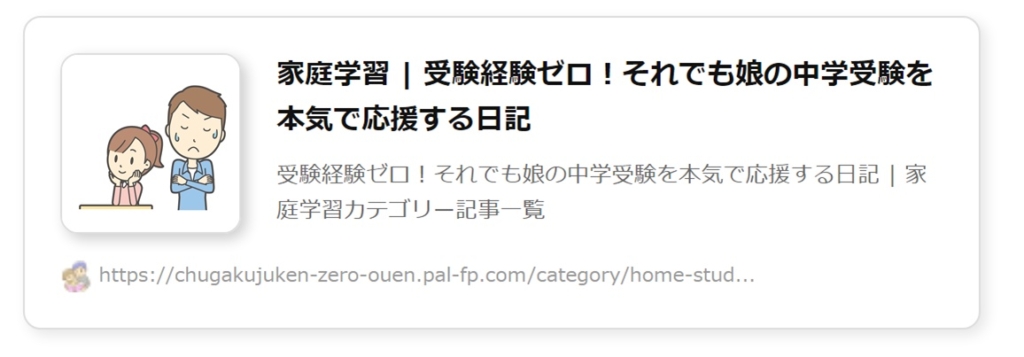中学受験の「塾なし教材」最強ロードマップ|四谷大塚「予習シリーズ」とEN「新演習」を核に、市販問題集で合格力を積み上げる

塾に通わずに中学受験を乗り切れるのか——私も正直、最初は半信半疑でした。ただ、4年生以降に「カリキュラムを持つ教材」を軸に据え、教科別の市販問題集を足し引きしていけば、十分に戦えると今は考えます。



この記事では、四谷大塚の「予習シリーズ」とエデュケーショナルネットワークの「新演習」を中心に、長女のときに大活躍した市販問題集についても手厚く解説しながら、塾なしで合格力を作る方法を保護者目線でまとめました。長女は四谷大塚準拠である早稲田アカデミーでしたが、次女は進学くらぶ+市販問題集で新四年生から中学受験に向けて学習を進めていこうと思っています。
塾なしで戦う基本戦略と前提
学習時間の土台づくりと生活設計
塾なしは時間管理が命です。例えば、平日90〜120分・休日180〜240分を基準に、学校宿題と両立できるブロックで割ります。就寝時刻を固定し、夜に詰め込みすぎないことが重要です。
カリキュラムを持つ教材を核にする
体系書を週次で回すことが最短です。単元配列と演習サイクルが明確な教材を核に、弱点補強だけ市販問題集を追加。核がぶれると積み上がりません。この記事では「予習シリーズ」「新演習」を主軸に据えます。
親の関与のリアル
塾なしは、親が進捗の交通整理を担う前提です。丸つけ・誤答分析・翌週の割り振りまで含め、最初の数週間は並走が必要。慣れてくると、チェックリスト運用だけで回ります。もっとも、これは通塾していても同じでしょう。私は前もって数週間分の時間割を立てて、使える時間を割り振るようにしていました。
四谷大塚「予習シリーズ」を中核にした進め方
安心の大手塾テキスト
新演習も有名ですが、やはり「予習シリーズ」が第一選択となるのではないかと思います。何と言っても、大手塾である四谷大塚製であり、いつどの回を進めれば良いかのカリキュラムも公開されていて参考にすることができます。
算数の運用ポイント
図・式・言葉の三点セットで解説を読み込み、解き直し用ノートを必ず分けるとミス傾向が見えます。思考系単元は時間を区切って2周回し、演習量は市販の「ステップアップ演習」「プラスワン問題集」「塾技」などで底上げ。
国語の運用ポイント
語彙は毎回、読解は設問分類ごとの手筋を意識。残念ながら、国語の読解は演習を積めば積むほど国語の点数が上がるというものではないです。そのため、きちんと読解の型を身に着けたいところですが、これはそもそも通塾していても簡単ではなく、きちんと家で補強するのが良いです。
\ 「読む力」は、家庭の手で育てられます。/
中学受験の国語で苦戦するお子さんは、実は「センス」ではなく「読む手順」を知らないだけです。
授業だけでは身につかない読解の基礎を、家庭でどう支えればよいか――
その具体的な方法をまとめた記事「親が変える。才能ではなく手順で伸ばす中学受験・国語の読解力」をnoteで公開しました。
家庭での国語学習を変えたい方は、ぜひご覧ください。
https://note.com/zeropapa_juken/n/nd5ae81109d59
理科・社会の運用ポイント
理社は資料読み取り→用語整理→一問一答の三層で。予習シリーズ各回の最後のページや演習問題集の一問一答、さらにはコアプラスなどの暗記教材で知識をメンテナンスします。資料集を併用して知識をつなげて学習の理解を深めると、暗記が効率化します。週末に単元まとめを確認するようにすると定着が加速します。
進学くらぶで何が揃うか
四谷大塚のオンライン講座はカリキュラム・講義・テストが自宅で完結します。つまりは、これだけで通塾に近い学習環境を在宅で再現できます。さらに、これに市販問題集を重ねると、まさに鬼に金棒。
実際に全てを親が管理し、ときに教えたりと運用することは簡単ではないですが、理論上は超低コストで通塾とほぼ同じ学習を進めることができます。進学くらぶについての詳しい全体像は次の解説も参考にしてみてください。
四谷大塚『進学くらぶ』徹底解説|オンライン中学受験:https://chugakujuken-zero-ouen.pal-fp.com/academy/shingakuclub-online-chugakujuken/
EN「新演習」を中核にした進め方
構成とレベル感
新演習は演習量が多く、段階的に負荷を上げやすいとされているようです。手を動かす時間が増えるので、実戦的な体力がつきます。となると、自走できる子や演習好きなタイプに相性が良いと感じます。
予習シリーズとの違いと選び分け
予習シリーズは解説の段取りと週次運用のしやすさが強み。新演習は反復・到達度の見える化がしやすい。迷うなら、説明重視なら予習シリーズ・演習量重視なら新演習という基準で選ぶとブレないでしょう。
どんな家庭に向くか
親の関与が薄くてもチェック表で管理できる設計が合うなら新演習、親子で段取りを整える余地を残したいなら予習シリーズ。私の場合は、娘の性格的に予習シリーズの方が回しやすかったです。
市販問題集で「底力」を作る(教科別の具体)
国語:語彙・選択肢・記述の三本柱
語彙は「中学受験国語の必須語彙2800」。選択肢は「中学受験国語 選択肢問題の徹底攻略」、記述は「中学受験国語 記述問題の徹底攻略」。設問形式ごとにトレーニングを分けると伸びが早いです。
「『答え探しの技(ワザ)』で勝つ! 中学受験 国語の読解」
選択肢の「消去の型」や設問別の見抜き方を具体例で示す読解の実戦書。読みに迷ったときの手順が明確で、独学でも再現しやすいのが利点です。
「中学受験国語の必須語彙2800」
入試頻出の語句・慣用表現を例文つきで整理。短時間で回せる構成で、読解ミスの原因になりやすい語彙の取りこぼしを計画的に穴埋めできます。
「中学受験国語 選択肢問題の徹底攻略」
設問タイプごとに「引っかけ」のパターンを分解。本文→設問→選択肢の読み順を矯正し、根拠の持ち方を訓練できます。
「中学受験国語 記述問題の徹底攻略」
抜き出し・要約・心情説明などを手順化。採点基準に沿った加点の積み上げ方がわかり、答案の型を固めたい段階に最適です。
算数:計算・頻出手筋・思考系
毎日「一行計算問題集マスター1095題」で計算体力を維持。頻出手筋は「塾技」「プラスワン問題集」「ステップアップ演習」。思考・図形はサピックスBASICや「図形の必勝手筋」「秘伝の算数」「下剋上算数」で粘りを育てます。
「マスター1095題 一行計算問題集」
日能研系の定番。イメージとしては「予習シリーズ計算」の最後の2問のような複雑に入り組んだ計算のみで構成された問題集です。毎日3題×365日で計算の筋力を維持・強化。難問対策前にケアレスを減らす「土台」として効きます。
「算数分野別問題集 ベイシック 基本60題(SAPIX)」
分野別に「基礎のツボ」を60題で固めるシリーズ。短い解説でも考え方の骨格が掴みやすく、穴の点検に向きます。特に、割合と比は必須ではないかと個人的に思っています。なお、通塾生でなくても、サピックスの校舎で購入することができます。
「図形の必勝手筋(平面図形/動く図形・立体図形)」
頻出図形の「手筋」をカード感覚で反復。作図や補助線の入れ方が体に入り、ひらめき待ちを減らす練習ができます。「これだけ解けば、それはできるようになるよね。」という一冊です。
「秘伝の算数(入門・応用・発展)」
数の性質や特殊算を「なぜそうなるか」から解く良書。解法の背景理解が進み、思考の持久力をじわっと育てます。
「下剋上算数 基礎編/難関校受験編」
到達度別に基礎~入試レベルを段階的に攻略。演習量が確保しやすく、家庭学習の主軸に組み込みやすい構成です。
「中学への算数 ステップアップ演習」
「基礎→標準→応用」の三段構えで無理なく負荷を上げる名シリーズ。解説が密で、思考の階段を踏み外しにくいです。
「中学への算数 プラスワン問題集」
頻出テーマをピンポイントで補強する短期集中型。演習穴のスキマ埋めに使い勝手が良く、直前期の微修正にも有効。
\ 毎月、新たに多くの方が復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
理科:知識×図表×短問反復
日課はコアプラス、理解を深めるのに「?に答える」や「自由自在」。写真・図表を伴う教材でイメージを先に作ると、暗記の負担が下がるのを実感します。
「理科コアプラス」
持ち運びやすい小型本で頻出暗記を効率化。スキマ時間に回しやすく、確認→上塗りの反復が癖になります。
「?(はてな)に答える! 小学理科」
写真・図解が豊富な「疑問解消」型の資料本。概念の土台づくりに役立ち、理解→暗記の順で入れる学習に向きます。
「小学高学年 自由自在 理科」
入試範囲まで網羅するハイレベル参考書。図表が整理され、横断理解と調べ学習のベースに置きやすい一冊です。「?に答える」と補完しあいながら、確実な知識を与えてくれます。
「論述でおぼえる最強の理科」
記述式の問題に対しても暗記で対応してしまえる教材。理解が進んで余裕が出てきたら取り組みたい一冊です。
社会:年代・地理・資料読み
社会もまずはコアプラス。地理・歴史・公民の資料は「?に答える」や「自由自在」で補強。年代は横断年表を自作して週1で回すと、入試の横断設問に強くなります。
「社会コアプラス」
地理・歴史・公民を要点カード感覚で総ざらい。頻出語の定着に特化し、年代や地名の取りこぼしを防げます。
「?(はてな)に答える! 小学社会」
地理・歴史・公民の素朴な疑問に答える資料本。写真と図版で背景知識を補い、資料読みの土台づくりに向きます。
「小学高学年 自由自在 社会」
用語から資料読解まで体系的に整理された決定版。記述の根拠探しに使える辞典的な一冊として常備がおすすめ。「?に答える」と補完しあいながら、確実な知識を与えてくれます。
「論述でおぼえる最強の社会」
理科と同様に、記述問題を暗記で対応してしまう教材。知識の積み重ねとともにじっくりと取り組みたい一冊です。
教材の選び方チェックリストと失敗回避
レベル設計と到達目標
基礎を軽んじず、きちんと固めてから応用へ。教材を手に取ったとき、簡単すぎるか難しすぎる場合には適していないでしょう。パッと見て半分以上わかりそうもなければ、まだ時期尚早かもしれません。
スケジュール適合と回転効率
1週間で無理なく回せる量に限定。教材を増やすより、同じ教材の反復で精度を上げる方が得点に直結します。私の場合は、間違えた問題の反復で理解を確実なものとしてから、次の1冊に進むようにしました。
フィードバックと見える化
間違えた問題は解説を読んできちんと理解。できなかった理由を言語化し、次にいつその問題を解くかも考えておきます。このように、理解不足を正しくするとともに、次の行動に落とすと、塾なしでも学習が回ると考えられます。
中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に
集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。
中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。
例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。
どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
個別指導・オンライン指導を検討している場合
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
家庭教師を検討している場合
一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。
講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。
各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。
中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】
無料の資料請求ページへ
![]()
確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。
ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。
少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。
まとめ
塾なしでも、核となるカリキュラム教材(予習シリーズ or 新演習)を週次で回し、教科別の市販問題集で弱点を補強すれば、合格に必要な学力は着実に積み上がると考えられます。オンラインの進学くらぶを組み合わせれば、通塾に近い学習サイクルを自宅で再現することも可能です。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)