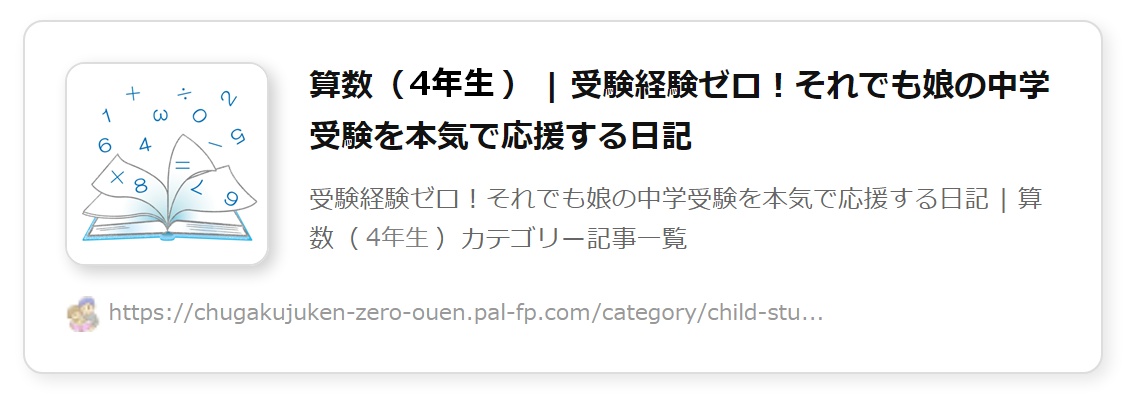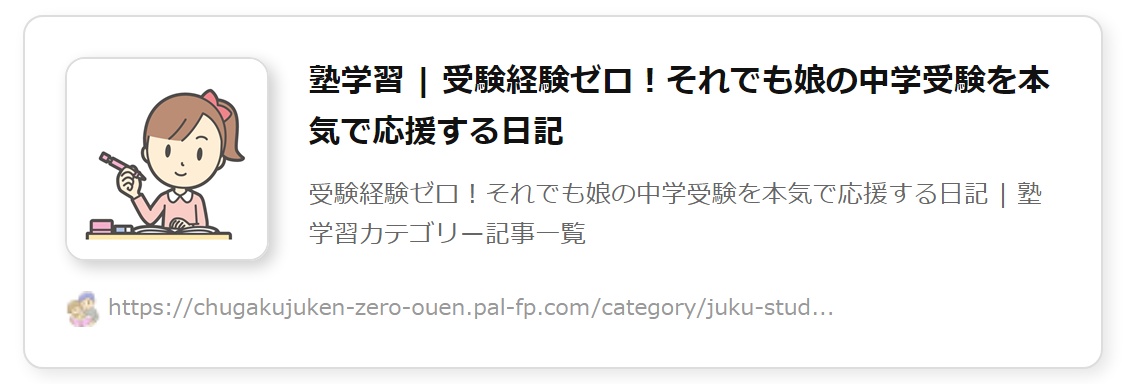算数:等差数列は始めだけでなく最後も大事
\ この学習法が娘の成績を変えました! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537

中学受験と関係ないですが、少し前に紹介したバケツ稲が育ってきました。3種類の土を買って混ぜ、それと別に小皿で芽を出させたイネの種子を分散して植えます。にょきにょき10cmくらい伸びて葉もいくつかついてきましたので、根を傷つけないようにすべて抜き、5本くらいまとめてバケツの中心に植え直しました。
あたかも知ったような書き方ですが、全部マニュアル通りです。。
さて、娘が早稲アカで算数の第14回の授業を受けましたので、いつもどおり応援します。
早稲田アカデミーでの、算数、予習シリーズ第14回は「等差数列」でした。数学で扱う範囲ではありますが、中学受験の勉強で出会ったときにはきれいサッパリ忘れていたのがいい思い出です。
第13回の周期算の延長のような側面もあるせいか、今回は、娘は特に苦もなくすらすらといていくことができました。こういうときは復習も少なくすんで楽ではありますが、時間がかかり過ぎかなと思った問題を中心に復習ノートにはいくつか入れるようにします。
復習ノートが少なすぎると、それはそれで復習の機会がほとんどゼロとなってしまい、しばらく経ったころに忘れてしまう可能性があります。何問かは難しめの問題を入れておいて、直近のテスト対策以上に、忘れた頃に思い出してもらうために入れています。
\ 毎月、新たに多くの方が復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
予シリ:授業前に例題だけ見ておきました。でも、授業では使わなかったようです。練習問題も解かなかったので、今回はほぼ使いませんでした。
演習問題集:練習問題をいくつか、授業で解いたようです。危なさを全く感じませんでしたので、基本問題と練習問題は省略し、トレーニング、実戦演習のみ解いてもらいました。実戦演習の後半は少し複雑そうに見えますが、特に問題なく、時間もかからず、正解することができていました。
しかしながら、1点、指摘しました。後半2つの問題は図が書かれている問題だったのですが、図の使い方や書き込みが少なく、数式で解き切っていました。とても危うさを感じます。頭の中だけで考えようとすると、最後までとき切れればいいのですが、手が止まると完全思考停止しやすい気がしています。簡単な問題でも、複雑な問題でも、「いつも同じように、図を活用しながら解く。図がなければ図を書く」を習慣化した方が安定するのではないかなと思います。少なくとも、私はそれで安定するようになりました。ゼロから自分で勉強してみると、いろいろ見えてきますので、受験経験がないのも、あながち悪くないなと思います。
最難関問題集、プリント:全部解きました。応用問題Bの桜蔭の問題は授業で扱われ、娘は(3)はわからなかったようなのですが、授業中に解けた子もいたとか。
通っている早稲アカのクラスの算数のレベル、とても高いです。組分けテストのクラス平均点を聞いてびっくりしました。SSクラスの基準は4科で偏差値60弱なのですが、算数だけなら通っているクラスのそれは、基準をはるかに超えているようです(4科の平均は知らない)。とても頼もしく、娘もうかうかしていられません。
ほかはミス1つ除いて、問題なく解くことができていました。渋幕の問題、私も解いてみたら結構面倒だったのですけど、粘り強く頑張っていました。と褒めつつ、復習ノート行きです。
ところで、難しめの問題の中には、「数列を進んでいくと、その間隔が広がってくるような問題」になってくると、数列の最後の方がイメージしにくくなっていきます。こういうとき、計算だけに頼らないで、最後の列と1つ前の列、問題によっては最後の次の列をきちんと図や数列に書いてみることを勧めました。
勧めるというか、娘が解いたあとに、「こういうふうに追記すると、ミスしてるかも・・とか不安にならないですむよ」と、見せながら私が解く感じです。数字だけで追っていくと、「1つずれました」というもったいないことが起きやすいと思うからでした。
算数のカリキュラムテスト13-14回はステキ成績(*)でした。最後の問題もきちんと取りきり、感心しました。途中、題意と異なる意味不明解答でミスしたのはご愛嬌ということにします。4科すべて調子よかったし、ミスはいえば治るものでもないので、日々の工夫でなんとかします。
*主観的な評価です。ステキ成績:点数か順位か偏差値が良いか、前回と比べて上がったなど、私と妻と娘で喜んだ成績です。むむむ成績:もう少し頑張れた気がするものの、きちんと復習することで挽回できそうな成績です。たいへん成績:一通り復習する程度では挽回できなそうな、苦手認定と本格的な対応が必要な予感のする成績です。ただ、「比較的成績が調子良い=普段から余裕」というわけではないです。確かに、第14回の等差数列はゆとりがありましたが、第13回の周期算はあとから手こずることになりました。演習問題集の練習問題レベルの問題で、1回目、少し時間がかかったものの問題なく解けていた暦算の問題がありました。これを、復習ノートに入れていたので、しばらく時間がたったころに解いてもらったら、どれだけ考えても、まったくわからなくなっていたのです。
そこで、ネットで暦算のプリントを見つけて、少しテコ入れしました。カリキュラムテストには間に合ったので良かったですが、こういうこと、ちょくちょくあります。以前、面積の単位換算なんかも、とても苦手だったので、テストまでに克服できるように計画を微調整したりしています。
何か違和感を感じたら、即時対応です。そして、違和感を感じるために、アンテナを広げ、間違えた問題だけでなく正解した問題のメモ書きなどもチェックするようにしています。娘の頑張りももちろんありますが、これが娘の成績を伸ばすことができている理由の1つのような気がします。
ちなみに、国語のカリキュラムテスト13-14回もステキ成績でした。いつもと異なり、記述と言えるような記述問題がなかったこともありますが、読解満点は感心しました。算数と並ぶ点稼ぎをできるようになりつつあります。むしろ、算数はミスのあるなしで点数がかなりぶれますが、国語はミスというものがあまりないので、ぜひ、国語を得意教科にしてもらいたいなと思っています。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。