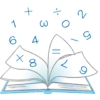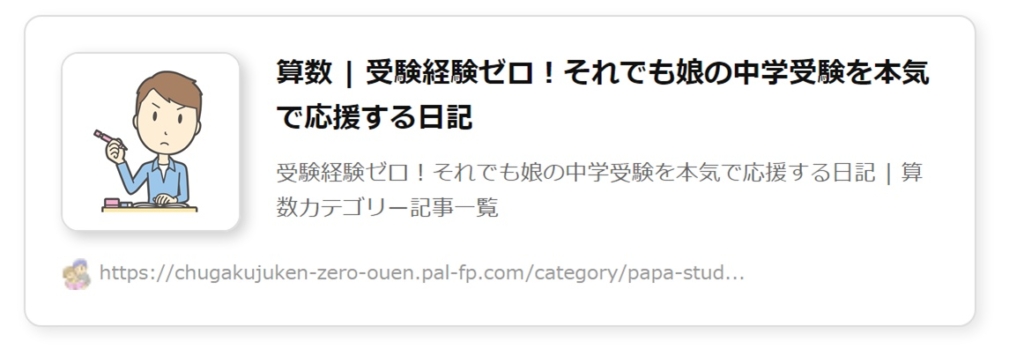すらすら解ける魔法ワザ 算数・文章題の親学習4日目~消去算

\ この学習法が娘の成績を変えました! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537
すらすら解ける魔法ワザシリーズ3部作の最後となる「すらすら解ける魔法ワザ 算数・文章題」を使って、私自身、算数の勉強を進めています。

「すらすら解ける魔法ワザ 算数・文章題」は、12のチャプターから構成されています。それぞれのチャプターは、つるかめ算、差集め算・過不足算、消去算、倍数算、仕事算、ニュートン算、食塩水、売買算、旅人算、通貨算、流水算、時計算となっています。そして、チャプターによっても異なりますが、1つのチャプターにつき3~8個の解法の説明があります。1つの解法あたり例題、基本問題、練習問題、レベルアップ問題が1題ずつ掲載されています。
今日は、「Chapter3 消去算」です。合計3解法分のページ数ですが、加減法、代入法、そして3つ目が何かと合体した消去算となっています。
「消去算を加減法で解く」
連立方程式の加減法と同じですね。
わからない数のどちらか、自分が計算しやすい方の数に注目し、最小公倍数で揃えることになります。
消去算はさすがに私も算数の勉強を今していなくても教えられそうですが、きちんと解法や解説も読みました。いわゆる連立方程式のような式を2つ並べる方法ではなく、表を使った方法も説明されていました。どちらの方法でも、最小公倍数に揃えることは変わらないですね。
中学受験で避けられない「方程式は子供に教えてはならない」という考え方については、私は個人的に、消去算だけでなく比例式など□を使った式を用いて解く問題も少なくないため、できるようになっておいたほうがメリットが大きいという結論にしました。そこで、例えば消去算を使う問題では、加減法だろうが代入法だろうが、□や数字にマイナスがついてびっくりしてしまうことを避けるため、娘には正負の数を教えました。ついで、文字式と一次方程式は教えるつもりです。
「消去算を代入法で解く」
代入法についても、連立方程式でおなじみの式で解く方法の他に、線分図で解く方法と①解法が紹介されていました。もっとも、式も①解法も大差ないようには見えますが。
未知の数の一方に係数がついてなければあきらかに代入法の方がいいのでしょうが、加減法で攻めるか代入法で攻めるかの判断は、好みもあるでしょうが、慣れも大事な気がしています。そういう意味では、娘には一次方程式でやめるのではなく、連立方程式も教えてしまっても良いのかもしれないと思い始めています。
「何かと合体した消去算」
相当算、取り違え、平均と循環(A+B、B+C、C+A)、立体図形と循環(A×B、B×C、C×A)の4つの応用問題が紹介されていて、はじめの3つは表を使った解法が、最後の立体図形の問題では式を使った方法の解説でした。
式でも表でもどの解き方でも良いと思うのですが、いろいろな解法を知っている中で、自分の中で、「迷ったらとりあえずこれを使ってみよう」という解法を持っておくと良いような気がします。頭でごちゃごちゃ考えてもわかることはまれなように思いますが、とりあえず手を動かすとなにか見えてくることもあると思います。娘にも、心の拠り所となる自信を身につけてほしいなと思っています。
娘が通塾を開始する2021年2月まで、あと85日です。娘が質問で先生の行列に並んで睡眠時間を減らさなくて済むように、また、娘のためにいずれ過去問を分析できるようになるためがんばります!
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
なお、以下のページに、「すらすら解ける魔法ワザ」シリーズの記事をまとめています。