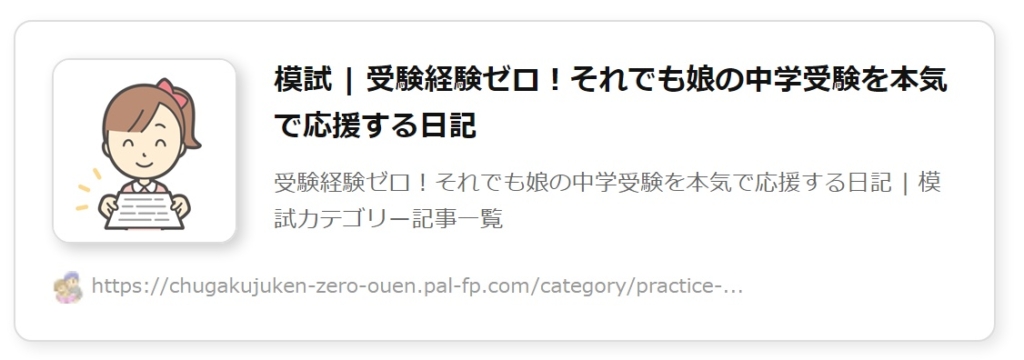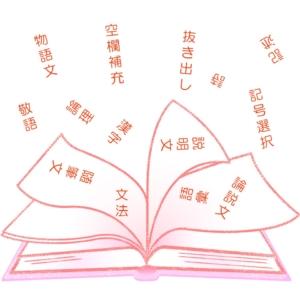四谷大塚の小学生向けテスト完全ガイド|合不合・週テスト・志望校判定の違いと活用法
\ 決勝大会では「作文」が勝負を分ける!/
全国統一小学生テストの決勝大会では、作文の配点が差をつけます。
親としてどんなサポートができるのか?どこまで関わるか?
経験者でなければ知り得ない「評価基準」「構成パターン」などを、
5回分の実際の課題・成績・講評分析から体系化しました。
上位30人を目指す保護者に役立つ具体策をnoteで公開しています。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne5f74f65d5cb

中学受験を考え始めたとき、まず気になるのが「どのくらいの実力があるのか?」という点ではないでしょうか。特に、初めての受験を控える小学生にとって、自分の位置を客観的に知ることはとても重要です。そこで多くの家庭が活用しているのが、四谷大塚の小学生向けテストです。



私の場合、長女が早稲田アカデミーに通っていたこともあり、早稲アカは四谷大塚カリキュラム準拠の大手塾なため、四谷大塚の模試はほぼ受けてきました。
この記事では、四谷大塚が実施する代表的な小学生向けテストの種類・目的・内容の違いについて整理し、それぞれのテストをどのように活用すれば中学受験に役立てられるのかを具体的に解説していきます。
四谷大塚のテストは何がある?目的別に理解しよう
合不合判定テスト(6年生対象)
このテストは、中学受験本番の「予行演習」としての意味合いが強い模試です。
- 対象:小学6年生
- 実施回数:全6回(5月〜12月)
- 判定精度:四谷大塚の「合格可能性判定システム」に基づき、精度が高い
- 特徴:実際の入試問題に近い出題形式で、志望校別に合格判定が出る
合不合判定テストは、受験生の9割近くが受けるとされる「受験の登竜門」です。偏差値の数値だけでなく、志望校別の相対位置を確認できるのが強みです。
学校別判定テスト(6年生対象)
より本番に近い形式で行われるのがこのテストです。
- 対象:小学6年生
- 実施回数:年2回(秋~冬)
- 特徴:志望校ごとに出題傾向を反映した「本番仕様」の模試
特に御三家や難関校を狙う受験生にとっては必須のテストといえるでしょう。
ただし、早稲アカ生の場合は、早稲田アカデミーの学校別判定テストとも言えるNNオープンがあり、また、サピックスの志望校判定サピックスオープンも必須として受けるので、四谷大塚の学校別判定テストも受ける子は珍しい印象です。
志望校判定テスト(4・5年生対象)
低学年のうちから「自分の志望校を意識する」ことを目的に設計されたテストです。
- 4年生:1月に1回実施
- 5年生:9月・1月に2回実施
- 判定方法:合不合と同様の志望校判定システムを活用
実際に志望校が定まっていない場合でも、範囲なしの模試として、今の学力がどのレベルなのかを知る指標として非常に有効です。
公開組分けテスト(4~6年生)
もっとも実施頻度が高く、学習進捗管理に適しているのが公開組分けテストです。
- 対象:小学4〜6年生
- 実施回数:
- 4・5年生:年9回
- 6年生:年3回(合不合と時期が重複)
- 特徴:成績によってコース分けがされ、教材のレベルが変動する
定期的なテストで順位や偏差値を確認できるので、「学習のモチベーション管理」に役立ちます。我が家ではこのテストの後にごほうび方式で対策の振り返りをするようにして、子どものやる気につなげていました。
週テスト(四谷大塚生または進学くらぶ生対象)
毎週行われるミニ模試のような存在です。
- 対象:四谷大塚の塾生または進学くらぶ会員
- 内容:その週の学習内容から出題
- 活用法:理解度の定着確認に最適
週テストの良いところは、復習のタイミングを固定化できる点です。自宅学習でも学習リズムを整えるのに非常に効果的だと感じました。
なお、早稲アカ生は、4年生と5年生では四谷大塚作成の2週に1度のカリキュラムテストを受けていきますが、6年生の前期(人によっては後期も)は四谷大塚生と一緒に週テストを受けていきます。
全国統一小学生テスト(年2回、全学年対象)
四谷大塚が主催する全国最大規模の公開模試で、学年・地域・通塾有無を問わず、誰でも無料で参加できます。
- 対象:小学1年生〜6年生(学年別に問題が用意される)
- 実施回数:年2回(6月・11月)
- 特徴:
- 無料で参加できる全国規模のテスト
- 問題は学年の到達度と応用力を測る構成
- 上位成績者は「決勝大会」に招待される場合も
このテストの魅力は、自分の実力が全国の中でどの位置にあるかを客観的に確認できることです。我が家も初めて参加したのは小3の時で、当時は「試験ってこんなに緊張するんだ!」と親子で実感しました。
また、テスト後に返却される「成績帳票」には、得点・偏差値・全国順位・分野別の正答率などが明記されており、学習面での課題発見やモチベーション向上にもつながります。
「うちはまだ受験は先だけど、今の実力を知っておきたい」「無料で実力試しをしたい」と考えているご家庭には特におすすめです。
\ 決勝大会では「作文」が勝負を分ける!/
全国統一小学生テストの決勝大会では、作文の配点が差をつけます。
親としてどんなサポートができるのか?どこまで関わるか?
経験者でなければ知り得ない「評価基準」「構成パターン」などを、
5回分の実際の課題・成績・講評分析から体系化しました。
上位30人を目指す保護者に役立つ具体策をnoteで公開しています。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne5f74f65d5cb
偏差値だけじゃない!テスト結果の見方と活かし方
判定の種類を理解する
四谷大塚のテストでは、一般的な「偏差値」だけでなく、
- 順位(全国順位・校舎別)
- 分野別の得点率
- 志望校別の合格判定
といった、多面的な指標が用意されています。
これをうまく活用するには、偏差値だけを見ないことが大切です。たとえば、「理科の生物分野だけ著しく低い」とわかれば、そこを集中して強化すればよいのです。
成績帳票は必ず保護者が読み込む
実は、子ども自身は「A判定かB判定か」ばかりに気を取られがちです。しかし、本当に大切なのは「なぜ解けなかったのか」「なぜミスをしたのか」の分析です。
私はいつも、娘の問題用紙への書き込みなども確認したうえで、ポイントをチェックしてフィードバックしていました。間違えた問題だけではなく、正解した問題についても、書き込みが怪しければ、きちんと理解していたのか、それともマグレだったのかを確認するようにしていました。
テストをうまく活用する家庭の共通点とは?
テストの「結果」ではなく「材料」として捉える
上位層に入っても油断せず、下位でもあきらめず、「今の課題は何か?」を探すことに重きを置いているご家庭ほど、着実に力を伸ばしているように思います。
家庭で「模試後面談」を設ける
模試のたびに子どもと親で「模試後振り返り会議」を開くのがベストです。「どうして解けなかったのか?」「どこで時間を使いすぎたか?」などを共有することで、次回への意識が変わってきます。
テスト結果は成長の「スナップショット」
テストはあくまで一時的な状態の記録です。結果だけで一喜一憂しすぎず、継続的な成長の視点で見守ることが、親としての姿勢として求められるのではないかと感じます。
テスト受験のタイミングと戦略を立てよう
4年生からの受験で「慣れ」を積む
4年生から塾のカリキュラムに従って模試を受け続けることで、試験慣れができます。緊張で頭が真っ白になることも減り、本番に強くなります。
志望校選びの材料として使う
志望校が定まっていないご家庭こそ、志望校判定テストを使って視野を広げるのがおすすめです。思いもよらない学校が選択肢に入ってくることもあります。
合不合や学校別判定は「本番想定」で
6年生の秋以降は、実戦形式の模試を「本番と同じように受ける訓練」として活用しましょう。服装・時間・持ち物・起床時間までシミュレーションすることで、当日のメンタル安定にもつながります。
オンラインでもできる、中学受験向けの立て直し
地方在住や送迎の都合で通塾の選択肢が限られる場合でも、オンラインで中学受験対策を進めることは可能です。
塾フォロー型の個別指導(オンライン対応)という選択肢があります。
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中で公式情報や条件を確認した限り、候補の1つとして比較対象に入れやすい印象で、資料を取り寄せておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
SS-1では無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
例えば、成績が伸び悩んでいる・苦手がいつまでも苦手なまま…などの悩みが出始めているなら、個別指導を検討し始めてもよいかもしれません。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
体験談も参考になりますが、私自身はまず公式資料を正しく理解することが大切だと考えています。
子どもが頑張っているからこそ、親も判断材料を集めるという形で一歩進めておくと安心です。
まとめ
四谷大塚が実施する小学生向けのテストは、単なる成績評価ではなく、学習管理や志望校選びに直結する重要なツールです。
- 合不合判定テスト・学校別判定テストは6年生の本番前対策
- 志望校判定・公開組分け・週テストは学年を問わず実力測定に有効
- 偏差値に振り回されず、原因と対策に目を向けることが重要
私自身も、「テストの目的を理解し、うまく活かすことで、子どもの成長にしっかりつながる」と実感しています。ぜひ皆さんも、お子さまに合ったテスト受験の計画を立ててみてください。
\ 決勝大会では「作文」が勝負を分ける!/
全国統一小学生テストの決勝大会では、作文の配点が差をつけます。
親としてどんなサポートができるのか?どこまで関わるか?
経験者でなければ知り得ない「評価基準」「構成パターン」などを、
5回分の実際の課題・成績・講評分析から体系化しました。
上位30人を目指す保護者に役立つ具体策をnoteで公開しています。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne5f74f65d5cb
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は参考記事です。