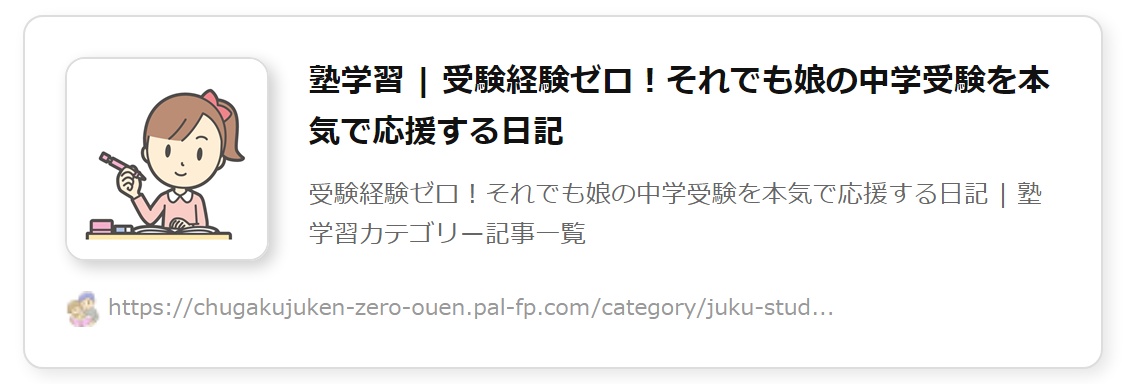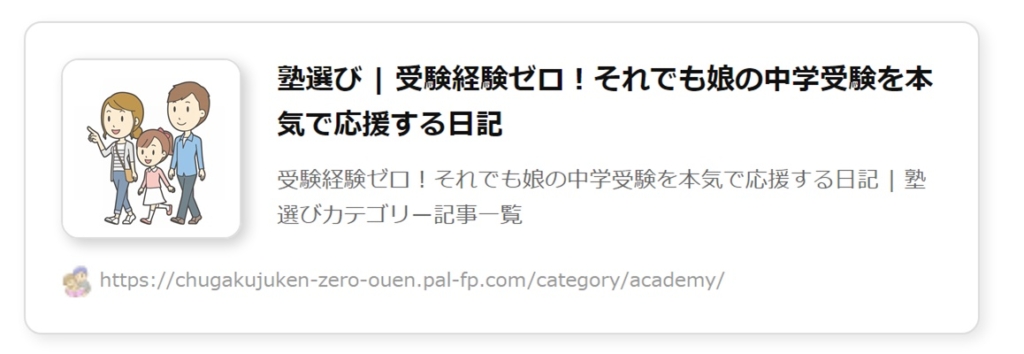Z会で中学受験は「失敗」するのか?実際に起こりやすい落とし穴と対策を徹底解説

中学受験に向けてZ会を活用するご家庭は年々増えています。しかし同時に、インターネット上では「Z会だけで大丈夫?」「失敗したらどうしよう」といった不安の声も少なくありません。私自身も娘の中学受験を考えたとき、Z会は候補の一つでしたが、「通信教育で本当に合格まで導けるのだろうか」と徹底的に調査しました。



そこで本記事では、「Z会 中学受験 失敗」というキーワードを軸に、よくある失敗パターンとその回避法を整理しました。長女のときは最終的にZ会ではなく早稲田アカデミーを選びましたが、これからZ会を利用するかどうか検討している保護者の方にとって、判断材料の一つになればと思います。
Z会だけで中学受験に挑戦するリスクとは?
通塾と比べたときの違い
Z会は通信教育を軸とするため、通塾のように直接的な指導は受けられません。学習管理や進度調整を親子で担う必要があるのが最大の特徴です。塾に比べると柔軟に学習できますが、その分、本人の自主性と家庭のサポート体制が不可欠です。
よくある「つまずき」ポイント
・計画通りに進められない
・添削課題を出さずに溜めてしまう
・難問に立ち止まってしまい先に進めない
このような状況が積み重なると、実力がつきにくくなり「Z会は失敗だった」と感じてしまうケースがあります。
「失敗」と感じやすい原因と背景
学習習慣や自己管理が難しい
Z会は通信教育型のため、自ら計画を立てて継続する力が必須です。塾のように毎週授業や課題が与えられるわけではなく、課題を後回しにすると一気に積み重なります。実際、毎月添削課題を提出していたものの、学年が上がるにつれて子どものやる気や集中力が続かず、第一志望に届かなかったケースがあるようです。
さらに、周囲に受験仲間がいない環境では「競争意識」や「緊張感」が生まれにくく、課題をこなすだけの受動的な学習になりやすいことも失敗の要因とされています。競争を身近に感じられる大手塾とは大きく異なるポイントと思います。
教材の難易度が高く、ついていけなくなる
Z会の教材は難関校を強く意識しており、小学校の進度より早く、特殊算や応用理科問題など未習範囲が多く含まれるのが特徴です。基礎固めが十分でないまま応用に進むと、理解が追いつかずに挫折するリスクが高まります。
特に小4後半や小5から始めると「スタートが遅かったために基本が不足し、そのまま難問に取り組む羽目になった」という例が見られます。
学習時間の確保が困難
学校行事や習い事、家庭の事情によって、思うように学習時間を確保できず失敗した例もありました。
例えば、低学年では家庭学習が順調だったものの、学校再開後に学習時間が減り、Z会の進度についていけなくなったケースがありました。通信教育は柔軟な反面、安定した学習時間を確保できる環境が不可欠です。
親のサポート不足・教育方針のずれ
Z会を利用する上で、親の学習管理や声かけは極めて重要です。通塾していても同じことが言えますが、塾からのアドバイスが得られない通信教育では特に、親が「お金を払っているから何もしない」「家庭学習は子どもに任せる」と距離を置いてしまうと、子どもは孤立しやすくなります。
実際に、親がサポートを拒否して失敗したケースも報告されています。親と子どもの受験に対する意識のずれが致命的な結果につながるのです。
競争意識・実戦経験の不足
通塾の場合は模試や友人との切磋琢磨が自然に得られますが、通信教育中心だとテスト慣れや競争環境が不足しがちです。
資料では、模試で第一志望の合格率80%以上を維持していたのに、本番で緊張し実力を発揮できず失敗した例が紹介されています。これは、本番を意識した練習や多様な模試の受験が不足していたことが大きな要因と考えられます。
志望校とのミスマッチ
Z会のカリキュラムは標準~難関校をカバーしていますが、志望校ごとの対策に直結するとは限りません。過去問演習を取り入れないままZ会中心で学習してしまうと、「想定外の出題形式に対応できなかった」と後悔することがあります。
周囲との比較
塾に通う友達の話を聞いて「うちは遅れているのでは?」と不安になるのも失敗と感じる要因です。他人と比べるより、自分の子の成長に焦点をあてることが大切だと思います。
失敗を避けるためのZ会活用法
学習計画を立てる
通信教育は自由度が高い分、計画性が求められます。1週間ごとに学習スケジュールを可視化し、達成度を確認する仕組みを取り入れると効果的です。
添削課題を必ず提出する
Z会の強みは添削指導です。提出を怠ると大きなメリットを失うことになります。中学受験向けではないですが、私も大昔に添削教材を取っていたものの、添削課題の提出が遅れがちで効率よく学習できていなかったなと振り返ってみて感じています。
苦手科目を補強する
算数や理科のように自宅学習では理解しにくい分野は、市販教材や動画解説を併用すると安心です。場合によっては塾の模試だけ受けるなど、外部との接点を持つのも有効です。ただし、親がその選別をしなければならない点に、通塾と比べてハードルがあると言わざるを得ないところです。
志望校に合わせた対策を取り入れる
6年生以降は過去問演習が必須です。Z会だけで完結させず、志望校ごとの傾向に合わせた演習を計画的に取り入れることが、失敗を防ぐ大きなポイントです。ただし、これもまた言うのは簡単ですが、実行するのは大変難しいところです。
Z会と他の学習手段をどう組み合わせる?
塾併用のメリット
塾とZ会を併用すれば、演習量や指導の厚みを補うことができます。例えば、算数は塾で解説を受け、国語や社会はZ会で演習を積むとバランスが取れます。
模試や外部テストの活用
塾に通わなくても、模試だけは積極的に受けると自分の立ち位置を確認できます。Z会の学習がどこまで通用するのかを客観的に判断できるため、学習計画を修正しやすくなります。
内部リンクの活用
「Z会だけで中学受験は本当に可能?」という視点では、以前こちらの記事で詳しく解説しました。あわせて読むことで全体像がつかみやすくなると思います。
まとめ
Z会は質の高い教材と添削指導で、多くの受験生を支えてきた通信教育です。しかし、学習管理を親子で担う必要がある点や志望校ごとの対策不足が、失敗につながりやすい原因でもあります。失敗を避けるには、計画性・添削活用・志望校対策・外部模試などを組み合わせることが大切です。
「Z会は失敗するのでは?」と不安に思うのは自然なことですが、実際には工夫次第で十分に合格を目指せる学習法だと考えます。私自身も娘の受験を通じて、Z会の良さと課題を両方体験しました。これから取り組むご家庭には、ぜひ自分たちに合った使い方を見つけていただければと思います。
\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。