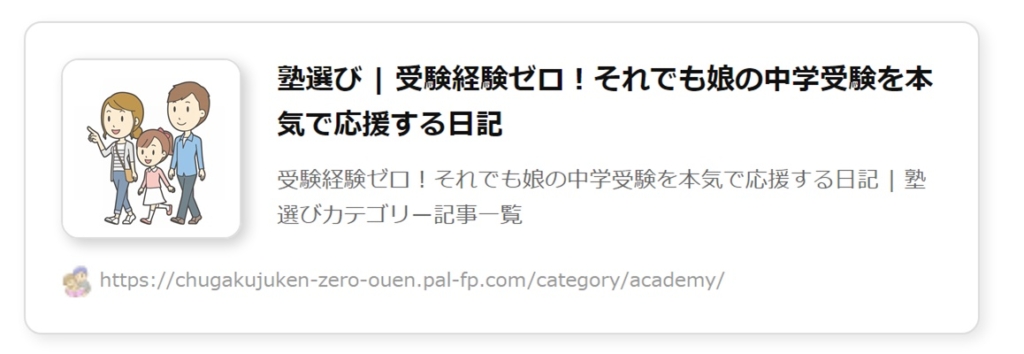早稲田アカデミーの特待生を徹底解説|A特待・B特待の仕組みと、小4〜小6で3年間維持したリアル体験談

\ この学習法が娘の成績を変えました! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537
中学受験を考え始めると、「授業料を少しでも抑えたい」という気持ちは多くのご家庭に共通するのではないでしょうか。わが家も例外ではなく、塾代の見積もりを初めて見たときは、正直なところ「こんなにかかるのか…」と固まってしまいました。一方で、塾によっては成績上位の子に授業料を免除する「特待生制度」があり、その中でも早稲田アカデミーの特待制度はとても仕組みがはっきりしていて、保護者の関心も高いと感じます。



うちの娘は、低学年のころから早稲田アカデミーから特待のお話をいただく機会があり、小4で入塾してから小6で卒業するまで、ずっとA特待を維持した経験があります。そのおかげで家計はかなり助かりましたが、その裏側には「テストで順位を取り続けるプレッシャー」も少なからずあったのではと思います。
この記事では、早稲田アカデミーの小学生向け特待生制度について、制度の仕組み・認定の基準・費用面のリアル、そして「我が家の場合はこうだった」という体験を交えながら、できるだけ具体的にまとめていきます。
早稲田アカデミーの特待生制度の全体像を整理しよう
特待生とは?授業料免除で何がどこまで安くなるのか
まず押さえておきたいのは、早稲田アカデミーの特待は「塾生の授業料を軽減する制度」であり、塾内制度だという点です。成績上位の子どもに対して、一定期間の授業料が全額、もしくは半額になる仕組みで、いわゆる「奨学金」や「中学校の学費免除」とは別物です。
対象になるのは、各種テストで優秀な成績をおさめた塾生・入塾希望者で、成績に基づいて塾側が一方的に「特待認定のお知らせ」を出すイメージに近いです(認定後、所定の手続きが必要なため、家庭が辞退することもできます)。
「授業料が安くなる」という言葉の響きだけを聞くと夢のようですが、どの費用が対象で、どの費用は対象外なのかを理解しておかないと、あとで「思ったほど安くなっていなかった」ということになりかねません。
A特待とB特待の違い(原則:全額無料か半額か)
早稲田アカデミーの小学生向け特待は、大きくA特待とB特待の2種類があります。
- A特待:原則として、半年間の授業料が全額免除
- B特待:原則として、半年間の授業料が半額免除
ここでポイントなのは、「授業料」だけが対象であることです。入塾金・年会費・教材費・テスト代・各種オプション講座の費用などは、基本的に別途必要になります。
また、特待の適用期間は前期(2〜7月)/後期(9〜1月)といった「半期単位」で設定されることが多く、テストの成績によって「次の半年をどうするか」が決まっていきます。
小学生向け特待の対象学年とコース
特待生制度は、小1〜小6まで、学年ごとに対象となるテストと条件が異なります。低学年では、いわゆる「中学受験コース」とは別の、小学生向けスーパーキッズコースでも特待認定のチャンスがあります。
- 小1〜小3:各種チャレンジテスト・冬期学力診断テスト
- 小4〜小6:中学受験コースの授業料が特待の対象になるのが一般的
わが家の場合、娘は低学年のころから早稲田アカデミー主催のテストで上位に入り、小2・小3の段階で既に特待相当の声がかかっていました。その段階で「将来中学受験を本格的にやるとしたら、この塾は魅力的だな」と考えるきっかけにもなりました。
特待でも「完全無料」にはならない費用項目
注意したいのは、特待を取っても「塾にかかるお金がゼロになるわけではない」ことです。
具体的には、次のような項目は、原則として特待の対象外です。
- 入塾金
- 年会費
- テキスト・教材費
- テスト代
- 春期講習・夏期講習・冬期講習などの講習費(※後述の例外あり)
一方で、NN土曜特訓・NN日曜講座については特待の適用対象となるのが大きな特徴です。特に土曜日のNN講座は、最大3講座までとっても全て特待対象になるため、志望校別対策に本格的に取り組みたいご家庭にとっては、家計の負担をかなり抑えることができます。
また、A特待・B特待ともに、春期講習または冬期講習の授業料が半額になる一方、夏期講習は特待適用外で全額自己負担という点も、あらかじめ知っておくと計画が立てやすいと思います。
いつ・どのテストで特待判定される?学年別の流れ
低学年(小1〜小3)のチャレンジテスト・学力診断テスト
低学年のうちは、「早稲田アカチャレンジテスト」や「冬期学力診断テスト」などが特待判定の主な舞台になります。
2020年ごろまでの例でいうと、
- 小2:チャレンジテスト上位で特待認定(1けたでもB特待の事例があり、A特待は5位以内を目指したい)
- 小3:サマーチャレンジテストや冬期学力診断テストで
- おおよそ1〜100位がA特待
- 101〜250位がB特待
といった基準が案内されていた時期もありました(その後、小3では1〜20位がA特待、21〜100位がB特待というように、より絞られた基準に変わっています)。
うちの娘は、小2のチャレンジテストと、小3の学力診断テストの両方で特待相当の成績を取ったことで、大きな自信につながるきっかけになりました。
小4以降は全国統一小学生テストと組分けテストが鍵
小4になると、全国統一小学生テスト(全統小)と四谷大塚の組分けテストが特待判定の中心になります。
- 全統小:全国規模で行われる無料テスト
- 組分けテスト:中学受験コースのクラス分けに使われるテスト
早稲田アカデミーでは、全統小・組分けの成績をもとに、前期・後期それぞれの特待A・Bを判定しているのが一般的です。全統小で一定の順位に入ると、早稲田アカデミーから「特待認定」の案内が届くイメージです。
なお、この基準は明確になっていて、決勝進出となる50以内でA特待、100位以内でB特待となっています。
組分けテストの特待判定に使われる順位の目安と「WinJr掲載順位」
5週間に1回受けることになる組分けテストは、7月と12月が特待判定の対象回となっています。そして、点数がばらつくことから、具体的な基準は点数ではなく順位で決まっています。
A特待を目指すならおおむね上位10位以内(できれば5位以内)、B特待なら30位以内(できれば10位以内)を目安にしておくと、安全圏に近づくという感覚があります。
A特待狙いの場合の点数の目安で言えば、550点満点で少なくとも500点はほしいところで、問題が易しく平均点が高くなる回では、520点あっても安心できないというイメージとなります。
また、組分けテストの場合は、「四谷大塚生も含めた順位」ではなく、「早稲田アカデミー在籍生だけを並べ替えた順位」が特待判定に使われます。実務的には、成績帳票そのものではなく、WinJrに掲載される「早稲田アカデミー塾生の内部順位」を参照していると考えてよさそうです。
ほぼ全ての家庭の例に漏れず、わが家も組分けテストがあるたびに、四谷大塚を含めた総合順位に加え、塾内順位(WinJr)も気にしていましたが、特に7月と12月はわずかにドキドキ感が高まったことを覚えています。
WinJrが公開されて塾内順位がわかるのは、四谷大塚のサイトで成績表を閲覧できるようになるだいぶ後になってしまうので、特待狙いの場合、その間の期間が少しもどかしくなります。体感的には、早稲アカ順位は成績表に書いてある四谷大塚などを含めた順位の半分くらいの順位になる印象です。
NN志望校別オープン模試でも特待のチャンス
小6になると、NN志望校別コースが本格的に始まりますが、ここでも特待のチャンスがあります。
- NN志望校別オープン模試
→ 志望校別コースごとに行われる公開模試
→ 成績上位者には、そのNNコースの授業料が免除になる特待が出ることがあります。
中学受験本番が近づくと、レギュラー授業+NN土曜特訓+NN日曜講座+各種模試と、どうしても費用が膨らんでいきます。ここでNNの特待が取れると、「今後一年間の家計の見通し」が大きく変わるご家庭も多いのではないかと感じます。
また、知人の話などを総合すると、ブログやSNSでときに話題となる「他塾生向けのNN個別」らしき特待は実在すると考えています。早稲アカ生の保護者としては思うところがありますが、これで実績を稼いで早稲アカが今以上に魅力的に認知されると、優秀な子もさらに集まるようになるのだと思います。
間接的に次世代の早稲アカ生の質が高まることになり、今の子たちは恩恵を受けられないかもですが、弟や妹がいるのであればプラスに働く・・・のかも?と考えることにして、深くは考えないようにしています。
なお、前述の通り、全国統一小学生テストか組分けテストで特待認定されると、NN志望校別コースも特待対象となります。NN土曜特訓+NN日曜講座で費用がかからないのはとても大きく、特待認定は4年生や5年生以上に、6年生で得られると家計への貢献は莫大となります。
\ 「読む力」は、家庭の手で育てられます。/
中学受験の国語で苦戦するお子さんは、実は「センス」ではなく「読む手順」を知らないだけです。授業だけでは身につかない読解の基礎を、家庭でどう支えればよいか――その具体的な方法をまとめた記事「親が変える。才能ではなく手順で伸ばす中学受験・国語の読解力」をnoteで公開しました。家庭での国語学習を変えたい方は、ぜひご覧ください。
https://note.com/zeropapa_juken/n/nd5ae81109d59
A特待・B特待を維持するための学習戦略
標準問題を落とさない「安定感」を最優先する
特待を狙うとなると、つい「難問を解けるようにしよう」と考えがちですが、実は一番大切なのは標準〜やや難レベルの問題を取りこぼさない安定感だと感じています。
全統小や組分けテストでは、満点を取る必要はなく、「ミスを最小限にして、解ける問題を確実に取りに行く」ことが上位安定の近道です。特に算数では、計算ミス・単位ミス・図の読み違いなど、ケアレスミスが積み重なると一気に順位が落ちてしまいます。
わが家では、「難問に時間をかける前に、まず標準問題の正答率を9割以上にする」という方針で、復習ノートを作り込んだり、間違えた問題の徹底的な理解を目指していました。
テストごとの出題傾向と対策の組み立て方
全統小と組分けテストでは、同じ「学力テスト」でも出題の雰囲気が少し違います。
- 全統小:文章量が多く、読解力や処理力が問われる総合問題が多め
- 組分けテスト:塾のカリキュラムに沿った到達度テストに近い問題構成
そのため、対策するのであれば、少し方法を変える必要があります。全統小に向けては、時間配分の練習や、国語の長文・算数の文章題の読み取りを意識して、組分けテストに向けては、間違えた問題を中心に塾テキストと類題演習の徹底復習を優先しました。
ただ、娘の場合、特待は結果論ではありました。全統小は範囲もよくわからず予シリ復習も効果的でなく、四谷大塚のホームページにある過去問を除いては実質的に対策のしようがありませんでした。組分けテストも、特待がかかっていようがいまいがいつも通り復習するだけでしたね。
他塾の特待との比較
中学受験の塾特待自体の考え方と、他塾との比較については、こちらの記事で詳しくまとめています。
https://chugakujuken-zero-ouen.pal-fp.com/academy/chugakujuken-tokutai-nerai/
成績アップだけに偏らないメンタルケア
特待を狙うと、どうしても「順位」や「偏差値」に目が行きがちです。しかし、子ども自身にとっては、「いつも成績で評価されている」と感じると、精神的な負担も大きくなります。
わが家では、「特待を取ること」そのものを目標にはせず、「今できることをしっかりやった結果としてついてきたらラッキー」くらいの温度感で伝えるようにしました。テストのたびに「何位?」ではなく、「どの問題ができるようになった?」を一緒に振り返るように努めたつもりです。
私自身、つい点数に一喜一憂してしまうタイプではありますが、親のほうも「特待、特待」と思い詰めすぎないことが大事だと感じています。
我が家の体験談:小4〜小6まで特待を維持して感じたこと
低学年から特待の声がかかり、塾選びにも影響した
先ほど少し触れましたが、娘は小2の終わりごろから、早稲田アカデミーのテストで特待に相当する成績を取るようになりました。
当時はまだ「本当に中学受験をするかどうか」決めた段階でした。塾側から「特待で授業を受けませんか」という案内をもらったことで、「この子は勉強が好きだし、せっかくならチャレンジさせてあげようかな」と、実際に低学年から通うことはありませんでしたが、前向きに考えるきっかけになりました。
小4以降、全統小と組分けでA特待をキープ
小4から本格的に通塾を始めてからは、全国統一小学生テストと組分けテストの両方で上位をキープし続けることが、結果としてA特待維持につながりました。
もちろん、毎回うまくいったわけではなく、算数で大きなミスをして順位を落とし、親子でがっくりした回もあります。それでも、「次でもう一度がんばればいいよ」と声をかけ続けることで、娘自身も、「特待が切れても、中学受験までの勉強が続かなくなるわけではない」と冷静に受け止められるようになっていったと思います。
家計がどれだけ助かったか、金額イメージ
金額については校舎やコースにもよりますが、中学受験コースの授業料が半年間ほぼ無料になるインパクトは相当大きいです。
ざっくりしたイメージですが、
- 通常の月謝 × 6か月分
- + NN土曜特訓・日曜講座の授業料(特待対象)
- + 春期か冬期の講習費の半額分
などを合計すると、年間で見ると数十万円単位、特に6年生では百万円レベルで負担が軽くなった感覚があります。もちろん、年会費やテキスト代・テスト代は別途かかりましたが、それでも「特待がなかった場合」と比べると家計の差はかなり大きかったと感じています。
なお、特待で減らすことができた塾の費用には到底およびませんが、中学受験が終わってから、長女にはパソコンなど好きなものを好きなだけ買い与えることにしましたね。
特待のプレッシャーと、あえて子どもにはどう伝えたか
一方で、特待が続くと、「落としたくない」というプレッシャーもついて回ります。
我が家では、娘には「特待だからがんばろう」ではなく、「今の勉強を続けていたら、結果として特待が続くかもしれないね」くらいの伝え方を意識しました。そうしておくと、テスト結果に一喜一憂しすぎず、「まずは中学受験全体を完走すること」が最優先だと、冷静に判断しやすかったです。
早稲田アカの特待を「目指すべき家庭」と「目指しすぎないほうがいい家庭」
特待を強く意識してもよいケース(学力・性格・家計)
早稲田アカの特待を比較的強く意識してもよいのは、次のようなケースだと感じます。
- 既に模試や塾内テストで上位常連になっている
- 子ども本人が「テストで順位を取るのが楽しい」と前向きに感じている
- 家計的に、授業料の全額または半額免除があると進学先や受講コースの選択肢が広がる
こうした場合は、無理にではなく「どうせ受けるテストなら、特待ラインもひとつの目標にしよう」くらいの位置づけで、特待を狙う価値があると思います。
特待よりも優先したい「距離・校舎の雰囲気・講師との相性」
一方で、特待条件だけを軸に塾を選ぶのはおすすめしません。
たとえ授業料が免除になっても、
- 通塾時間が長くて子どもが疲れ切っている
- 校舎の雰囲気が子どもに合わず、毎回の通塾がストレスになっている
- 講師との相性が悪く、授業が楽しめていない
といった状況では、成績を安定して伸ばすことはなかなか難しいと思います。
以前、塾選び全体の考え方については、別の記事でまとめていますので、「特待だけでなく、塾との相性も含めて考えたい」という方は、こちらもあわせて読んでいただくと整理しやすいかもしれません。
中学受験の塾選びと特待制度の位置づけについての詳しい考察
https://chugakujuken-zero-ouen.pal-fp.com/academy/chugakujuken-tokutai-nerai/
他塾や特待以外の費用対策とあわせて考える
特待制度は魅力的ですが、「取れるかどうかが分からないもの」に家計の前提を依存しすぎると、結果的に不安が増えてしまいます。
- 他塾も含めた費用の相場を把握する
- 通信教育やオンライン塾など、コストを抑えた併用パターンを検討する
- 受験年度に向けて、習い事やレジャー費の見直しも含めて家計を組み立てる
といった、特待に頼りすぎない費用対策を同時に考えておくと、心理的にもかなり楽になると感じます。
今後、特待認定は絞られていくと私が感じる理由
最後に、少し個人的な予想も書いておきます。
早稲田アカデミーは近年、合格実績・業績ともに好調で、ブランド力も年々高まっている印象があります。その結果、「特待で優秀層を集めなくても、自然に優秀な子が集まってくるフェーズ」に入りつつあると感じています。
実際、小3の特待基準が「上位100位まで→上位20位まで」といったかたちで絞り込まれた例を見ると、今後も特待認定の枠や基準が厳しくなる可能性は十分あると考えています。
だからこそ、保護者としては、「特待が取れたらうれしい」「取れなかったとしても中学受験の準備は淡々と続ける」というスタンスを持ちつつ、制度とうまく付き合っていくのが現実的なのかな、と思っています。
まとめ
早稲田アカデミーの特待制度は、仕組みが比較的わかりやすく、家計にも大きく影響する制度です。ただし、対象となるのはあくまで「授業料」であり、入塾金や諸経費、教材費、夏期講習費などは別途必要になる点には注意が必要です。
わが家の場合、娘が小4〜小6までA特待を維持したことで、数十万円単位で家計の負担が軽くなり、その分を志望校別講座や模試受験に回すことができたと感じています。一方で、特待を維持するためのプレッシャーは確かに存在し、「特待を取ること」よりも「中学受験を最後まで走り切ること」を優先する姿勢が何より大切だとも実感しました。
これから塾選びや特待制度について考えるご家庭には、「制度としての仕組み」「費用面のメリット」「子どもの性格や家庭の価値観」をバランスよく見ながら、「うちの子にとってベストな選択は何か?」をじっくり考えていただければと思います。早稲田アカデミーの特待生制度は、うまく活用できれば心強い追い風になってくれるはずです。
\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)