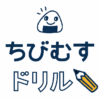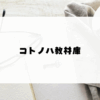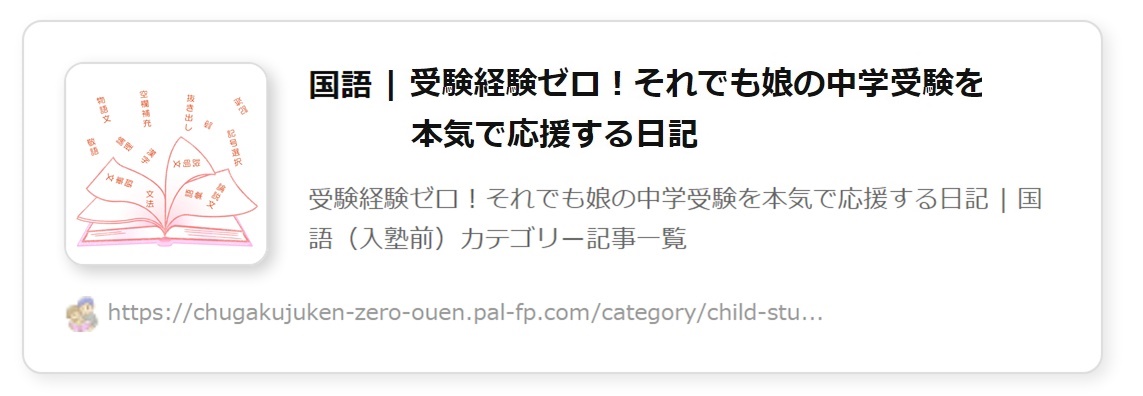小学生の語彙力はプリントで伸びる|無料サイト厳選・学年別の使い方・中学受験に効く実践法
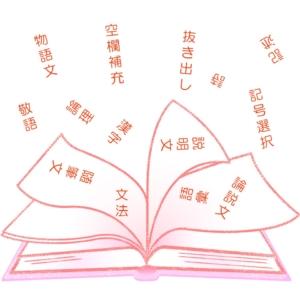
小学生の語彙力は、毎日の小さな積み重ねで着実に伸びます。なかでも「無料プリント」は始めやすく、家庭で再現性の高い学習法の1つになる思います。わが家でも最初は「ことばの意味」が曖昧で読解に苦戦していました。



この記事では、おすすめの無料語彙プリントサイトと、学年別の使い方、中学受験に向けた実践ステップまでまとめてご紹介します。もちろん、アプリや書籍も良いと思います。一方で、人によって好みのスタイルは異なるもの。何をやればよいかわからないときなど、まずは印刷してすぐ取り組めるプリントから土台を固めるのも有効と考えます。
小学生に「語彙力プリント」が効く理由
語彙は読解・記述の「地盤」になる
語彙が不足すると、設問の意図や本文の論理が取りにくくなります。反対に、基本語・抽象語・慣用句の理解が増えると、文章の構造が見えやすくなり、記述の骨格も作りやすいです。プリントは頻出語を網羅的に反復できる点が強みだと感じます。
学校+家庭で「露出頻度」を上げられる
授業で触れた語に家庭のプリントで再会すると、想起の間隔が程よく空き、エビングハウスの忘却曲線を超える形で記憶が残りやすくなります。1日1枚でも、露出頻度の積み上げが効きます。
覚える→使って定着する
プリントで意味・使い方を確認したら、家庭の会話で意図的に語を使うのがおすすめです。例えば夕食時に「今日の出来事を『具体的』に説明してみよう」のように、語の運用を促すと定着が早いです。私の場合は、例えば娘が「包括的って何?」と聞いてきたとき、忙しくても手を止めて説明するようにしてから伸びが違いました。
無料で使える語彙力プリントサイト(厳選)
ちびむすドリル(語彙・文法・作文が横断的)
「こそあど言葉」「故事成語」「文の成分」など、語彙と文法がセットで養えます。学年別・単元別で探しやすく、短い所要時間のプリントが多いのも日課化に向いています。中学受験の基礎固め期に相性が良いです。
プリントの森(類義語・対義語・ことわざが体系的)
「言いかえ」「語句の使い分け」「オノマトペ」など、語彙の幅を段階的に広げる構成。まとめDLができ、集中反復したい家庭に便利です。語感のズレを修正するのに重宝します。
学習プリント.com(網羅性と印刷のしやすさ)
学年別の国語プリントが幅広く、語彙・漢字・文法を横断可能。自宅プリンターはもちろん、コンビニ印刷に対応している点が忙しいご家庭にありがたいです。
にこばね(無料DL・要望対応の柔軟さ)
全部無料で、苦手つぶしに向いたプリントが揃います。利用者リクエストでプリントが増えることもあり、ピンポイントの穴埋めに使いやすいです。
ことのは教材庫/まめつぶワーク(専門性の高い言語教材)
言語聴覚士作成のプリントが含まれ、ことばの基礎~応用まで丁寧に段階設計。特性に配慮した教材もあり、つまずきが目立つ領域を無理なく補えます。
上記のような無料サイトは基礎〜応用を幅広くカバーしており、学年・単元・目的に応じて選べます。まずは1〜2サイトに絞って運用ルール(曜日・枚数・所要時間)を固定し、慣れたら範囲を広げると継続しやすいです。
学年別・到達別:プリント活用ロードマップ
低学年(小1〜小2):音と意味のつながりを作る
「しりとり」「なかまのことば」「反対語・類義語」など、遊び感覚で語のネットワークを広げます。音読→口頭で言いかえ→1行だけ書くの三段階にすると負担が軽いです。1日5〜10分を毎日積むのがコツです。
中学年(小3〜小4):用法・言いかえ・文脈理解へ
「こそあど」「接続詞」「慣用句」「ことわざ」を文脈付きで扱い、誤用の修正を進めます。週1回は「短文作成」で使う練習を入れると、暗記が運用に変わる実感が出ます。
高学年(小5〜小6):抽象語・論理語・記述の骨格づくり
「抽象語」「比喩」「論理接続(因果・対比)」を記述演習と接続します。語を指定して80〜120字で短記述を作ると、語彙→表現→採点基準まで一本線になります。入試直前は誤答しやすい語群の総点検を。
受験を見据えた「語彙プリント×家庭の会話」設計
家庭の会話で「運用の場」を増やす
その日扱った語を夕食の話題で必ず1回使うルールに。例えば「抽象的」「具体的」「要約」など入試頻出語は、生活の出来事に当てはめて話します。親の「モデル発話」がいちばん効きます。
辞書・類語辞典を「引いて終わりにしない」
意味を引いたら、自分の言葉で言いかえ→1文作成→親が微修正の流れに。辞書索引シールや付箋で再訪できる状態にして、間隔反復を作りましょう。
プリント×アプリのハイブリッド
毎日の主役は紙プリントでも書籍でもなんでもOK。スキマ時間にはアプリで確認テストを回すと定着率が上がります。アプリの全体像は、既出の「中学受験アプリ完全ガイド」で詳しく整理しています。
プリント運用の具体テクニック
週間メニューと「固定枠」
例えば、月〜金は各10分、土日は誤答だけ再演の15分。タイマーで計測し、取り掛かり5分以内を死守すると継続します。見える化のため、学習カレンダーにシールを貼るのも効果的。
直しノートは「最小限の労力」で
例えば、「誤答は赤で正解を書くだけ→翌日もう一度同じ問題」。長い反省は続きません。誤答タグ(付箋)で再登場を管理すると、弱点の回転数が上がります。
語彙カテゴリ別の回し方
特定の言葉を集中して覚えたいなら、「反対語」「類義語」「慣用句」「ことわざ」「抽象語」「論理語」などを曜日で固定。例:月=反対語、火=慣用句…のようにルーティン化すると迷いが消えます。
我が家の小さな工夫
私の場合は、娘が誤用した語をメモして「今日のことば」カードに書き出し、壁に貼りました。その語を1回は会話で使うルールを入れてみると、使用頻度が一気に増えました。
目的別・おすすめプリントの選び方
読解の根っこを強くしたい
反対語・類義語・接続詞を優先。文と文の関係が見えると、文章の骨格がつかめます。短文完成のプリントで運用に橋渡しを。
記述や要約を伸ばしたい
抽象語・評価語(例:適切・妥当・根拠・具体)を強化。条件文を使った短記述で「語の意味→使い方→採点」の連動を作ると、得点化しやすいです。
語感のズレ・誤用を直したい
誤用選択や文脈置換のプリントが近道。似た語のニュアンス違いを並べて学ぶと修正が早いです。
中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に
集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。
中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。
例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。
どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
個別指導・オンライン指導を検討している場合
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
家庭教師を検討している場合
一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。
講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。
各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。
中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】
無料の資料請求ページへ
![]()
確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。
ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。
少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。
まとめ
語彙力は「毎日10分の積み重ね」で必ず伸びると思っています。 無料の語彙プリントは、学年別・単元別に選べて反復に強いのが魅力です。
まずは2週間、1日1ページ・1枚から始めてみてはと思います。書籍やプリントなど、紙で土台を作り、会話で運用して、必要に応じて確認用アプリを添える。これが読解・記述に直結する最短ルートだと私は思います。
迷ったら、上で紹介した無料プリントサイトから「反対語/類義語」「慣用句」など頻出分野を選び、固定時間×固定枚数のルールで回していきましょう。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は参考記事です。