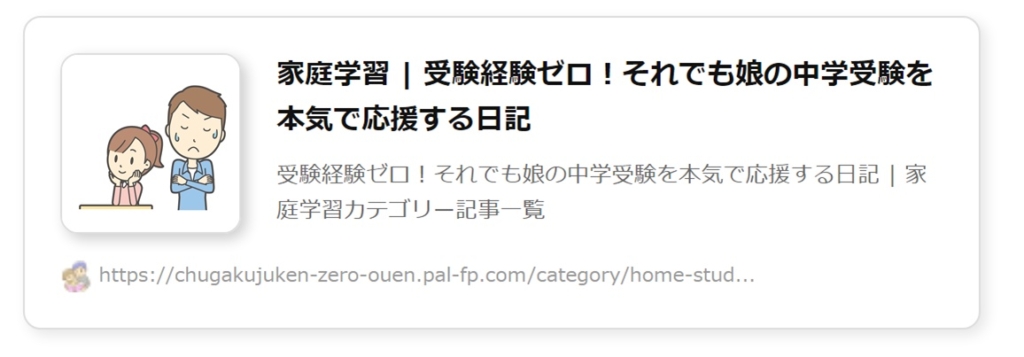中学受験の暗記は「何を」「どれだけ」?4教科ぜんぶの必須リストと効率暗記のコツ総まとめ

「暗記の量が見えないから不安」わが家もまさにここから始まりました。小学生の娘と計画を立てるとき、具体的に「何を覚えるのかが一覧で分かること」が安心につながると痛感しました。



本記事は、保護者目線で算数・国語・理科・社会の暗記すべき内容を網羅し、覚え方のコツまで一気にまとめます。ここで示す内容は一般的な出題頻度の高い暗記リストです。最新のテキスト・模試情報と併せてご活用ください。
なぜ暗記が必要なのか(まずは全体像)
得点の「土台」を素早く作るため
入試は思考力問題が増えていますが、基礎語句・公式の暗記が速いほど、考える時間が増えるのは間違いありません。暗記は「時間を生む投資」です。
ミス削減と自信形成につながる
覚えるべきものが反射で出る状態だと、計算・選択・穴埋めのケアレスミスが減り、模試での安定感が上がります。本人の自己効力感も上がりました。
家庭学習の計画が立てやすい
「何を・どの順に」やるかが見えると、1日15〜20分の「暗記タイム」を固定化できます。親の声かけも具体化しやすいです。
暗記の回し方(超要点だけ先取り)
「見える化ボード」と「今日の3枚」
科目別の暗記一覧ボード(A3)を壁に掲示。なかなか習慣化できない場合には、例えば、毎日「今日覚える3枚(カード)」だけ選ぶと負担が軽く、達成感が貯金になります。週末は5分テストすることで締めの復習も効果的と思います。
音読→復唱→書き出しの三段ブースター
耳(音読)→口(復唱)→手(書き出し)の順に3回転。特に理科用語や国語語彙は、声に出すほど定着が速いと感じました。なお、書き出しは時間がかかるので、高速回転させるには耳と口を中心とするのがよいですね。
1:3:1復習(当日→3日後→1週間後)
忘却曲線を踏まえ、同一セットを当日・3日後・1週間後に短時間で再テスト。正解でも1回は再確認するルールが効きます。
カード活用は「やり方」で差がつく
カードは自作でも市販でもOK。作り方・回し方のコツは別記事にまとめています。
教科別「暗記一覧」総リスト
算数|「定義・公式・定数・単位」を使える形で覚える
平方数・立方数/素数・約数・倍数の瞬時認識
2〜30までの平方数、2〜20の立方数、素数(2〜97)は暗記し、約数の数の出し方、最大公約数・最小公倍数は常連は覚えてしまい、それ以外も練習して反射で出るように。
割合・比・速さ・濃度の「型」と代表公式
基本ながら「くらべる量=もとにする量×割合」「道のり=速さ×時間」「食塩の重さ=食塩水×食塩の割合」は確実に。文章題の骨格等式は丸ごと暗記。歩合・百分率・小数の相互変換もカード化。
平面・立体の公式と「よく出る数値」
三角形・台形・ひし形・円の面積公式、柱体・錐体の表面積・体積。円周率は「3.14」「22/7」を場面で使い分けながら、九九のように「3.14の段」をまずは1~9まで暗記。立体切断・展開図は練習も丁寧に行いたいが、最終的には型名ごとに覚える。
単位・換算・規則性/場合の数の道具
長さ・面積・体積・時間・速さ・密度の換算。約分の近道(2,3,4,5,6,8,9,10の判定)、等差・等比的並び、表・樹形図の作り方を型→自力再現で固める。
国語|「漢字・語彙・文法・記述フォーム」を分けて覚える
配当漢字・同音異義語・送り仮名の原則
頻出漢字の読み書き、送り仮名(例:誤る/漏れる)の原則、同音異義語は例文つきで意味を暗記。自分の誤り集を回すのが効率的でした。
ことわざ・慣用句・四字熟語・外来語
「ことわざ・慣用句・四字熟語」は意味+用例で暗記し、同義・反対ペアで記憶を強化。カタカナ語は分野別(生活・IT・社会)に5語ずつ。特に重要なのは「和語」で、単語集に頼りすぎず、日頃の生活で1つずつ積み上げたいです。
品詞・文法・接続語/記述テンプレ
品詞判定・用言の活用・主述のねじれは短文で即答できるまで。接続語の機能(しかし/つまり/たとえば)を役割で暗記。記述は「結論→理由→具体例」のテンプレから入ると安定。
説明文・物語の頻出語と心情語
説明文は「要旨/対比/因果/抽象⇄具体」のシグナル語、物語は心情語(逡巡・葛藤・安堵 など)と原因語句の対応をカード化。耳→口→手の順で定着。
理科|「用語+数字+典型グラフ」を抱き合わせで覚える
生物:植物・動物・人体
花のつくり(がく・花弁・おしべ・めしべ)、受粉と受精、消化酵素(アミラーゼ等)と働き、循環・呼吸の名称。季節の生物は写真+出会う月で記憶。
地学:天体・気象・岩石
月齢と見え方、時刻・方位の関係、雲の種類・前線・等圧線の読み。火成岩の鉱物(石英・長石・黒雲母)と硬さ・粒の大きさの典型。
化学:気体・水溶液・状態変化
水素・酸素・二酸化炭素・アンモニアの発生法・集め方・性質。酸・アルカリと指示薬の色、溶解度曲線は形で記憶。融点・沸点など数値感覚も。
物理:光・音・電気・力
反射・屈折・焦点距離、音の三要素、直列/並列回路の法則、オームの法則、てこのつり合い(力×腕の長さ)、ばねは比例グラフとセット。
社会|「地理・歴史・公民・時事」を「セット回し」で覚える
地理:地形・産業・統計
超基本となる都道府県・県庁所在地・主要地形名は白地図で確実に。農産物・工業・観光はトップ3や特色を暗記。いつかは覚えることになる統計は最新傾向語(増加/減少/横ばい)も付記。
歴史:年号は「流れ」で
時代区分→出来事→人物→文化→遺産の順でカード化。年号は語呂+前後の因果で覚えると記述にも強い。
公民:制度名・用語・手続
三権分立・国会の立法手続・内閣の仕事・裁判の流れ、地方自治の二元代表制、選挙制度、憲法の三原則・人権の分類。組織図と条文風キーワードで長文穴埋めに強く。
時事:背景語まで押さえる
ニュース語は背景・利害関係・数値を一言メモにして、公民・地理とリンク。わが家は毎日のこども新聞を習慣化してもらい、直前期には複数の時事本で対策しました。
家庭での「運用術」をもう一歩だけ
今日の3枚→週末5分テスト→弱点カード再編
小さく始めて、必ず締める。 間違えたカードだけ残し、翌週の「今日の3枚」に再投入。弱点が目に見えるのが続く秘訣でした。
白紙再現で「本物の記憶」に
穴埋めだけで満点でも、白紙から書けるかで定着は別物。理科の図・社会の地図は自作ラフスケッチが最短でした。
ツールを正しく使う
再掲となりますが、カード運用の詳しい手順はこちらにまとめています。家庭での仕組み化に役立つはずです。
https://chugakujuken-zero-ouen.pal-fp.com/home-study/chugaku-juken-anki-card/
中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に
集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。
中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。
例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。
どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
個別指導・オンライン指導を検討している場合
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
家庭教師を検討している場合
一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。
講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。
各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。
中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】
無料の資料請求ページへ
![]()
確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。
ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。
少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。
まとめ
暗記は「闇雲に量をこなすこと」ではなく、何を・どの順に・どの型で覚えるかの設計図づくりが先です。わが家は一覧→ミニ目標→テスト→見直しのサイクルにしてからムダが減り、娘の表情が柔らかくなりました。まずは本記事のリストを壁に貼る。ここから始めれば、今日の勉強が「見えるタスク」に変わります。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)