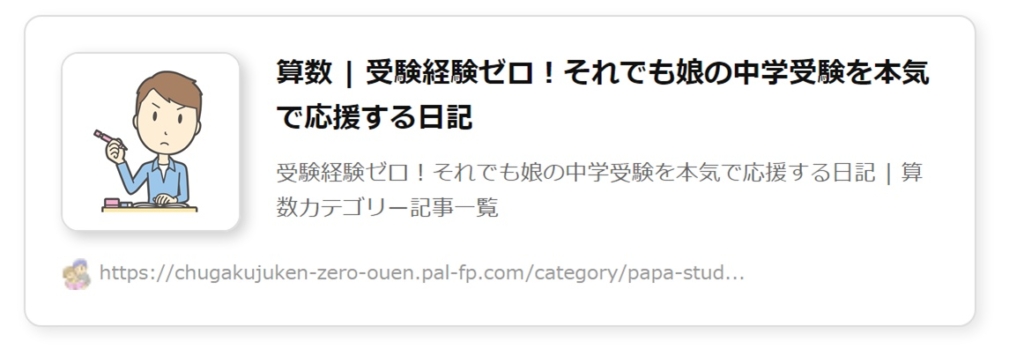中学受験に強い子が身につけている「計算力」と「速算力」──親ができる家庭での練習法

前回、私自身の計算知識をつけるために、「計算力を強くする~状況判断力と決断力を磨くために~」を使って勉強したことを紹介しました。
そちらで触れたとおり、下剋上受験で有名な桜井信一さんの著書である「桜井信一のわが子に教えたくなる 中学受験 算数・国語」、有名な中学受験漫画である「二月の勝者」の5巻で中学受験で開成をめざしている島津くんが同級生にアドバイスした内容の2つから、私には計算力がないということに気づくことができました。
今日は、2冊目、「計算の名人になれる速算術入門」です。

クリックでAmazonにジャンプします。
すでに絶版となっているようですが、レビューを見て、評価も良いので買いました。2014年に出版されたことになっていますが、それは再発行ということです。1974年に理工学社から発行された同書を、オーム社から再発行したもので、非常に歴史がある書籍となっています。その分、少々古めかしい印象を受ける構成や見出しとなっていて、どことなくそっけない感じがしますが、そこは大人パワーで我慢です。
一方、説明は先生であるBさんと生徒であろうAさんの会話形式で進んでいきます。中学受験の算数の教材では「秘伝の算数」が、会話形式ではないですが、語り口調でとてもわかりやすくなっていて評価が高いですね。計算や算数に馴染みがない私には、会話や語りの形式で説明されると、親しみやすいです。
計算に必要な速さと、正確な計算法は誰でも身につけたくなると思います。この本では、特に、日常の計算の中でよく使用されていて、また、実務的な考えが集められていますので、計算を簡略する方法論としては、優れた入門書であると言えそうです。
今回も、練習しつつ、パワポに1ページ1項目で結論、例題、問題をまとめたら、19ページになりました。前回と同様に、すべてが中学受験で役に立つとは思いませんが、自分の中での工夫のパターンが増えるのは価値があることだと思っています。
- 補数を使った減法(12345-6876=?)
- 補数を使った加減混合算(55+48-76+34-88+52=?)
- ちょうどの数に近い数との加法(246+198=?)
- ちょうどの数に近い数との減法(322-198=?)
- ある数に、5、25、125をかける(2432×50=?)
- ある数に、10、100、1000・・・に近い数をかける(5928×99=?)
- ある数に、200、300、400・・・に近い数をかける(687×398=?)
- ある数を、5、25、125でわる(312÷125=?)
- ある数を、10、100、1000・・・に近い数でわる(845624÷99=?)
- ある数を、 200、300、400・・・に近い数でわる(12345÷199=?)
- 九去法による検算:加法
- 九去法による検算:減法
- 九去法による検算:乗法
- 九去法による検算:除法
- 十等一和(62×68=?)
- 十和一等(26×86=?)
- 平方計算(93^2=?)
- 10台の数の2数の積(17×15=?)
前回同様、このまとめプリントは、まだ娘には見せていません。娘が算数を勉強しているときに、工夫が使えそうなのに使っていなければ、娘に教えることにしています。現時点で、娘が上記のなかで実戦で気づいて使うことができそうなのは、「1~9,18」あたりだと思います。
塾の授業を受けてみて、また、その復習や宿題に対応してみると、とにかく時間を確保することが大事であり、ますます効率よく勉強することが大事だと痛感させられました。計算は工夫できるところでは力技で解くことがないようにする必要がありますね。
 計算力を強くする:状況判断力と決断力を磨くために オーム社 価格:1,540円(税込、送料無料) Amazonへジャンプします |
ここからは、中学受験における「計算力」について考察していきます。
中学受験算数の土台となる力――それが「計算力」と「速算力」です。難関校の入試問題でも、複雑な文章題や図形問題を正確に解くためには、瞬時に正しい計算ができる力が欠かせません。
一方で、親御さんの中には「うちの子は考える力はあるけど、計算が遅い」「ケアレスミスが多い」という悩みを抱える方も多いはずです。
この記事では、中学受験に必要な計算力と速算力の本質をわかりやすく整理し、家庭でできる効果的な練習法を紹介します。また、低学年のうちから計算の土台を育てる方法や、親が一緒に学ぶ際のコツも具体的に解説します。
中学受験で「計算力」が合否を分ける理由
計算力とは「正確に・速く・理解して」行う力
中学受験の算数では、四則演算そのものが問われることは少なくても、すべての問題の裏側で計算力が必要です。計算力とは、単に答えを出すスピードではなく、数の仕組みを理解し、確実に処理できる力のこと。この力が不足していると、応用問題で時間を奪われ、考える前にタイムオーバーになってしまいます。
計算ミスが連鎖的に点数を奪う
1問のミスが次の問題に影響するのが算数の怖いところです。たとえ考え方が合っていても、計算の途中で1桁違えるだけで0点になることもあります。ミスを減らすためには、「丁寧な計算」よりも「正確に速い計算」の習慣を身につけることが重要です。
計算力がある子ほど「思考に集中」できる
計算を自動化できると、脳のリソースを考えることに使えます。たとえば速く正確に割り算ができる子は、文章題の条件を整理する時間を増やせます。「考える前に手が止まる子」と「手が自然に動く子」では、最終的な得点力に大きな差が生まれます。
👉 関連記事:
中学受験算数のテキスト選びと使い方|学年・レベル別に見る効果的な勉強法
「速算力」を鍛えると算数の時間が2倍に感じる理由
速算とは「正確さを犠牲にしないスピード」
速算というと「とにかく速く解く」イメージがありますが、正確さを前提としたスピードアップこそが本来の目的です。たとえば、「25×4=100」や「8×125=1000」など、数の性質を利用して瞬時に変換する感覚があると、入試本番で数分の時短になります。
速算の基本は「パターン化」と「暗算力」
速算力を鍛えるには、
- 整数・小数・分数の変換を瞬時にできること
- 計算の順番を変えても答えが同じことを理解していること
が大切です。
つまり、「同じ処理を何度も反復し、脳に最短経路を作る」トレーニングが速算の根本です。
速算練習のコツ──「毎日5分×3セット」
1回に長時間やるより、短く何度も反復するほうが効果的です。朝の10分、帰宅後の10分、寝る前の5分でもOK。「今日はここまでできた」と小さく区切って続けることで、無理なく習慣化できます。
家庭でできる「計算力」と「速算力」の鍛え方
① 簡単な計算こそ「本番の練習場」
多くの子は「もうできる」と感じる四則演算を軽視しますが、この基礎を完璧にすることで応用が伸びるのです。1桁どうしの掛け算・割り算・約分・倍数の感覚を「手で覚える」ように繰り返しましょう。百ます計算もおすすめですが、「速く」より「間違えない」を意識することが第一歩です。
② 計算過程を書きすぎない練習も必要
筆算のすべてを書く習慣は、スピードを下げる原因になります。もちろん省略しすぎは危険ですが、途中式を整理しながら書く訓練をすることで、計算の流れがスムーズになります。塾のテキストを使って「ここまでは暗算」「ここは式を書く」と分けて練習すると効果的です。
③ 「速算パターン」を親子でクイズ化
親子で「8×125=?」「9×11=?」といったクイズを出し合うのもおすすめです。速算のコツを共有することで、子どもは「計算=ゲーム」と捉え、自然とスピードが上がります。親が一緒に答えられる姿を見せると、子どもはさらに意欲的になります。
👉 関連記事:
中学受験を見据えて低学年で「やっておけばよかったこと」5選|後悔しない家庭学習のすすめ
速算を活かす「正確さ」の育て方
計算が速い子ほど「ミスを防ぐ習慣」がある
速算は速さを追うほど、うっかりミスが増える危険があります。これを防ぐには、「数字を声に出す」「単位を書く」「符号を確認する」の3つをセットで意識させること。慣れてくると、目だけでなく耳や手も使って確認できるようになります。
毎回の見直しで「自分のクセ」を見抜く
見直し練習では、ただ答えを再計算するのではなく、ミスの傾向を記録します。例えば「小数点のズレ」「繰り上がり忘れ」「符号ミス」などを分類しておくと、子ども自身が修正点を把握できます。「自分の間違いを分析できる子」は、伸びる速度も早いのです。
速算=暗算+構造理解
速算は暗算力の延長ではありません。本質は、「数の構造を理解して、最短経路で処理する力」です。「6×25×4=600」のように、順番を変えるだけで簡単になることを、体感として身につける練習をしましょう。
「親の学び直し」が子どもの算数力を変える
親が速算を体験すると、声かけが変わる
「なんでできないの?」ではなく、「ここを分けて考えると速いね」とプロセスを褒める声かけができるようになります。親が速算の考え方を理解すると、教え方が短くなり、子どもの混乱も減ります。特に小数・分数の変換や約分は、家庭で教えられる「親の武器」になります。
一緒に学ぶことで「勉強嫌い」を防ぐ
親が「今日は一緒にクイズやってみよう」と軽く声をかけるだけで、学習の空気が変わります。「勉強を命令される」のではなく、「一緒に挑戦する」という構図が、家庭の勉強時間を前向きにする最大のコツです。
まとめ:計算力と速算力は「中学受験の筋トレ」
計算力と速算力は、短期で劇的に伸びるものではありません。しかし、正確な基礎練習+毎日の短い反復を積み重ねることで、確実に差がつきます。
中学受験の算数は「頭のよさ」よりも、日々の小さな練習の積み上げが結果を左右する科目です。家庭で「速く正確に解ける楽しさ」を育てながら、親子で一緒に「数字を味方にする力」を磨いていきましょう。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。