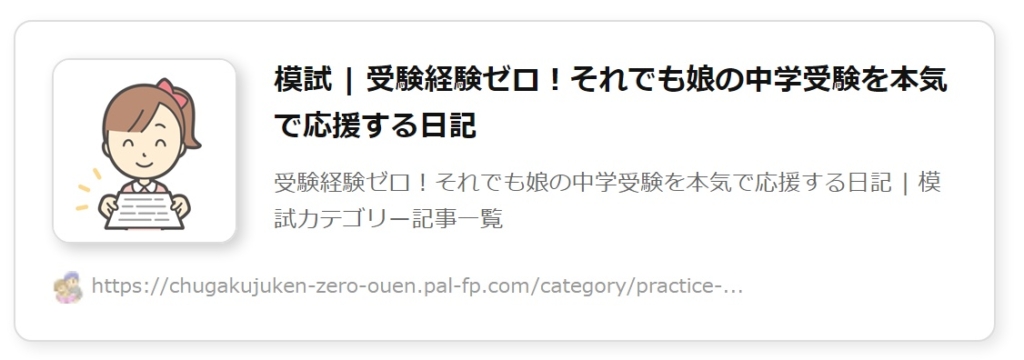偏差値上げたい!四谷大塚(早稲アカ)組分けテストの対策どうする?
\ この学習法が娘の成績を変えました! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537

概ね月に1回のペースで実施される、四谷大塚主催の「組分けテスト」。このテストは、早稲田アカデミー生も含めた多くの中学受験生が参加するため、「偏差値」や「成績の指標」としての影響力が非常に大きいものです。
四谷大塚の「週テスト」や、早稲アカの「カリキュラムテスト」は、頻度が高く1〜2週に1回のペースで実施されますが、それらに比べて組分けテストは出題範囲が広く、実力を問う内容になっています。だからこそ、ご家庭によっては特に力を入れて準備されるケースも多いのではないでしょうか。
実際、子どもの成績を上げたいと考えたとき、塾の授業内容や使用教材はもちろんですが、「どのクラスに所属しているか」で指導の質が変わることも少なくありません。そして、このクラス分けに大きく影響するのが組分けテスト。テストの成績次第でクラスが上がったり、下がったりするため、保護者の関心も自然と高まります。
となれば、目前に迫る組分けテストに向けて「どんな対策をするべきか?」という悩みが尽きないのも当然です。「偏差値が伸びない…」「前回より良い結果を出したい」そんな親御さんの思いは、私自身も何度も経験してきました。
一方で、「今回は完璧に対策できたはず!」と自信を持って送り出しても、いざ結果が返ってくると予想外の低スコアに愕然とする…そんな苦い経験も何度もあります。そしてまた「どうしたら成績を上げられるのか」「もっと効果的な勉強法はないのか」と、迷路のような思考にハマってしまうわけです。
実際、ネット上にも以下のような声が多く見られます:

悩み中

悩み中

悩み中
こうした疑問は、ごもっともです。ですが、私は「成績帯が違っても、やるべきことの本質は大きく変わらない」と考えています。
このブログ記事では、そんな保護者の方に向けて、中学受験の組分けテスト対策として、私自身が行っている方法を真面目に紹介します。特別な情報ではありません。娘の受験を支えるなかで試行錯誤を重ね、毎回のテストで微調整を加えながら積み上げてきた、ごく普通の方法です。
私の取り組みは、基本的には毎回「同じ型」をベースにしています。しかし、テスト範囲や娘の理解度に応じて、スケジュールや演習量を細かく調整しています。そして今のところ、娘はこのやり方で、安定した偏差値を維持し続けています。(追記:最終的に、最難関NN校を、NNオープン・そっくりテストとサピックスオープンの全てで80%判定を得て、合格、進学しています。)
さらに今回改めて考えてみたのは、「もし、娘が今とは異なる偏差値帯だったらどうするか?」という問いです。結論としては、たとえ偏差値が高くても低くても、やることの基本は変わらないという答えに至りました。むしろ、どの成績帯でも「復習」「苦手の洗い出し」「実践的な演習」をどう行うかが重要であり、それが組分けテストにおける本質的な「対策」だと強く感じています。
なお、組分けテストの各コースの基準点、いわゆるボーダーについては、別のページにまとめています。
こちらのページでは、2021年と2022年の4年生、5年生、6年生の四谷大塚S1組(2024年受験組のみ)、Sコース、Cコース、Bコース組分けテスト基準点ボーダーと得点率の推移を紹介しています。
組分けテストの対策する?しない?
「今」だけでなく「これから」を見据えた判断を
「組分けテスト対策って本当に必要なの?」という疑問は、中学受験に取り組む家庭なら一度は考えるテーマかもしれません。範囲が決まっているとはいえ、数週間単位で行われるこの模試に対して、そこまで時間を割くべきなのかと。
たとえば、「範囲のあるテストで一時的に偏差値を上げるよりも、長期的に使える基礎学力をしっかり身につけたい」と考えるご家庭もあるでしょう。限られた時間を今の範囲に注ぐより、普遍的な力に充てた方が有益なのでは?という考え方です。
また、私が愛読している『算数の戦略的勉強法』という書籍でも、算数においては「直近の単元をある程度犠牲にしてでも、先取りを重視する戦略がある」と紹介されています。実際、そういった方法で成績を伸ばしているお子さんもいるようで、一概に「それはダメ」と切り捨てることはできません。
とはいえ、組分けテストは決して軽視できない重要な模試です。塾のクラス分けやカリキュラムの設計に直結するため、結果次第で指導内容も変わることがあります。そして、このテストでは、単に「勉強量」や「先取り」をこなすだけでは結果に結びつきません。現在の理解度を復習でしっかり固めることが、偏差値を着実に上げるための鍵となります。
テスト結果に込められた「感情」と「やる気」:学びに変える親の関わり方
テストが終われば、子どもには必ず感情の波が訪れます。うれしい・悔しい・やるせない……そのすべてが、成長のきっかけになります。組分けテストの結果によって、子どもの心が揺れ動くのは当然のことです。親としては、その感情を丁寧に受け止め、次の行動に変換してあげることが「家庭でできる最大のサポート」だと私は考えています。
たとえ一時的なテストの話であっても、成績は悪いよりも良い方が、子どものモチベーションには確実につながります。点数が良ければ、「また頑張ろう!」という前向きな気持ちが自然と芽生え、それが継続的な学習の好循環へとつながっていくのです。
一方で、先取り学習を重視しすぎた結果、目の前の単元が「苦手」のまま放置されてしまうのは本末転倒です。私も娘の算数学習で先取りは積極的に取り入れてきましたが、「今の単元が不安定」と判断した場合は、即座に先取りをストップし、現状の理解の補強を最優先してきました。
やはり、しっかりと組分けテストの対策をして、実際に良い結果が出たときの成功体験には大きな意味があると思っています。良い結果は子どもにとって「自信」となり、さらなるチャレンジへの意欲となります。
逆に、「対策なんて必要ない」「結果は気にしなくていい」と口では言いながらも、実際に成績が悪かったときに子どもを責めてしまうような態度は、非常に危険です。子どもの努力や感情を否定してしまうと、やる気を失ってしまうどころか、学びそのものに消極的になってしまうこともあります。
苦手を放置せず、復習こそが最強の「組分けテスト対策」
組分けテストは、単なる模試ではありません。塾でのクラス分けや、志望校に向けた現在地の把握、今後の学習の方向性を考えるうえで、非常に重要な役割を担うテストです。
でも、組分けテストの意義はそれだけではありません。
たとえば、週テストやカリキュラムテストもそうですが、テストで思ったように点が取れないというのは、「今の学習範囲のどこかに理解不足や苦手単元が存在している」ことのシグナルです。つまり、点数の裏には、まだ身についていない知識や、曖昧な理解が残っているという事実が隠れています。
組分けテストで得点が伸びない理由は、突き詰めれば「苦手」の有無に尽きます。苦手な単元を見逃したままにしてしまうと、その後に待ち構えている応用単元で、より深刻なつまずきに繋がってしまうのです。だからこそ、テスト直後の「復習」は、単なる振り返りではなく、組分けテスト対策の中心に据えるべき重要なプロセスだと私は考えています。
その苦手、いつ克服しますか?「復習を先送り」にするリスク
テストが終われば、塾の授業はすぐに次の単元へと進んでいきます。テスト前の学習サイクルから一転して、また新たな知識が次々に流れ込んでくるわけです。そんな中で、テストで浮き彫りになった苦手を放置したままだと、それらが強化され、後々「応用問題」として大きな壁となって立ちはだかってきます。
そしてそれは、ただの点数の低下にとどまりません。子どもが「自分はできないんだ」と思い込んでしまったり、学習意欲そのものを失ってしまう可能性もあるのです。
この悪循環を断ち切るためにも、「組分けテストのための対策=事前準備」だけでなく、「組分けテストのための復習=事後の克服」までを一貫したセットと捉えるのが理想だと私は思っています。
理想は「事前復習 → テスト → 事後復習」:偏差値UPの王道
私の家庭では、組分けテスト前には必ず過去の単元を振り返る「事前復習」を取り入れています。直近の理解を定着させてから本番に臨むことで、テスト中の不安を減らし、得点力の底上げを狙っています。
それでも、やはりテストでは思わぬミスや理解不足が見つかるものです。だからこそ、テスト後の「解き直し」と「原因分析」も欠かしません。
具体的には、娘と一緒に以下のようなステップを踏んでいます:
-
点が取れなかった問題を分類(ケアレスミス・知識不足・理解違い)
-
特に繰り返しミスが出ている単元を「苦手リスト」に追加
-
数日以内に、重点的な復習プリントを自作し、短時間でも再確認
こうした復習ベースの「対策」が、偏差値を安定的に上げる一番の近道であることは、これまでの組分けテストの結果が証明してくれています。
組分けテスト算数の対策法
間違えた問題の「解き直し」が最大の鍵
算数の組分けテストで偏差値を安定させるには、過去に間違えた問題の「解き直し」をどれだけ丁寧にできるかが、最も重要なポイントになります。
多くのお子さんが、間違えた問題については塾の先生に質問したり、親に教わったり、解説を読んで理解しようとします。その場で理解したつもりになっても、実際のテストで解けるとは限らないというのが現実です。
本当に理解できているかどうかは、「自分で説明できるかどうか」で判断できます。頭の中でなんとなくわかったを卒業し、言葉にしてすらすら説明できるようになること。これが、定着の第一歩です。
そのうえで大切なのが、実際にもう一度手を動かして解き直すこと。解説を読んで終わりにせず、「自力で解けるようになるまで何度も繰り返す」ことが、偏差値アップへの王道です。
私自身、娘のために「復習ノート」を作っており、テストまでの時間と学習量のバランスを見ながら、どの問題を優先して解き直すかを考えています。たとえば、まったく歯が立たなかった難問よりも、「あと一歩で正解できそうだった問題」を優先して復習することで、時間対効果を最大化しています。
このように、自分の理解度に応じた優先順位を付けながら復習を進めることが、算数の組分けテスト対策における重要な勉強法です。
\ 毎月、新たに多くの方が復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a
「時間がかかった問題」は克服対象:得点に結びつく処理力を育てる
「やったー解けた!……けど15分かかった!」このような経験、誰しもあるのではないでしょうか。
たしかに正解できたのは素晴らしいことですが、制限時間のある組分けテスト本番では、得点につながりにくいのが現実です。時間をかけすぎた結果、他の問題に手が回らず、「本来取れたはずの点を落としてしまう」ことも少なくありません。
ですから、「解けたけど時間がかかった問題」を、いかにスムーズに解けるようにするかがポイントです。演習時には時間を測りながら問題に取り組み、「正確さ」と「スピード」の両立を意識する訓練を重ねています。
もちろん、「間違えた問題」の復習が最優先なのは変わりませんが、時間のある時にはこうした時間かかりすぎ問題にも取り組んでおくと、結果的にテスト全体の得点力が上がっていきます。
私の基本方針は、「できないことをできるようにする」「すでにできることは繰り返さない」。「なんとなくできる」を「確実に速くできる」に変えることが、組分けテストで点を取る最大の対策だと思っています。
「少し難しい問題」にチャレンジ:日常学習に「負荷」をかける意味
組分けテスト直前にいきなりレベルの高い問題に挑むのは非現実的ですが、日々の学習に少しだけ難しめの問題を混ぜておくことは、非常に効果的な取り組みです。
たとえば、「基本問題はほぼ解ける」という状態であれば、1問だけでも練習問題(標準〜応用レベル)に挑戦してみる。また、普段は練習問題をこなしているなら、1問だけでも実戦演習や難関校の過去問を使った演習にトライする。このような少しだけのチャレンジが、実力を底上げするブースターになるのです。
ずっと「基本問題まで」で学習してきた子が、「練習問題まで」こなせる子に組分けテストで勝つのは、かなり難しくなってきます。さらに、他教科の得点でクラスアップできたとしても、そのクラスで求められる算数レベルについていけない可能性があるのです。
だからこそ、クラスアップを目指すなら、今のレベルから少し背伸びした問題に日常的に触れておくことが重要です。「少し子どもにとって難しいかも?」と感じる問題でも、自力で考え抜く経験が、のちの応用力や得点力に直結します。
この取り組みは、偏差値をあと数ポイント上げたいとき、クラス昇格を狙いたいとき、どんな学力層にも有効な攻めの学習法になります。
組分けテスト国語の対策法
漢字・文法・言葉は「チリも積もれば」で点に変わる
国語の「漢字・文法・語彙(ことば)」の分野は、配点がそれほど高くないため軽視されがちですが、実は安定した得点源になりやすい重要ポイントです。特に文法は、入試での出題頻度が低いこともあってモチベーションが上がりにくい部分ですが、「チリも積もれば偏差値に反映される」タイプの得点項目です。
また、漢字や語彙は入試でも確実に問われる基本事項ですから、「わかってるつもり」で済ませるのではなく、「二度と忘れないレベル」まで徹底的に定着させる姿勢が求められます。
わが家では、漢字対策として「忘れたころにもう一度確認し、もし忘れていたらその場で書けるようにする」というサイクルを大事にしています。具体的には、「書けるかテスト」→「1回だけ書き直し」というシンプルな復習法を継続中。文法・語彙に関しても、毎週確認を行い、安定して得点できる状態を維持しています。
よくある「書けなかった漢字は10回書く」という方法は、時間対効果の面で効率が良いとは言えません。我が家ではどんなときも「1回書いて、時間をおいてもう一度確認する」という分散復習を基本としています。この方法は、短時間で高い定着率が得られ、組分けテストのように出題範囲が広く、短期集中型になりがちな試験にも有効です。
\ 毎日の漢字練習が「作業」から「成果」へ! /
「10回書けば覚えられる」から卒業しませんか?
我が家の実践記録と工夫を17,000字の大作にまとめ、さらに自作の「スーパー漢字復習ツール」もセットにした記事をnoteで公開しました。
「効率的な覚え方」「忘れにくい復習法」「プリント活用」を一つの記事に凝縮しています。ぜひ以下からご覧ください!
https://note.com/zeropapa_juken/n/n0df46d444fbf
読解のミスは「一般化」して攻略する:根拠とパターンを見抜く力
読解問題でありがちな失点パターンのひとつが、「理由は書けているけれど、それだけでは減点されてしまう」というものです。
たとえば、設問が「太郎くんが涙を流したのはなぜですか?」だったとき、子どもが「買ってもらう約束だったのに、ゲームを買ってもらえなかった。」と答えると、模範解答との間に感情の要素や根拠の一部が欠けているケースがよくあります。正解例としては、「テストの点が悪かったために、ゲームを買ってもらえず、悲しかったから。」など、具体的な理由と感情がセットになっているものが多いです。
ここで重要なのは、「この設問でどこを間違えたか」だけを理解するのではなく、どんな設問形式のときにどう答えるべきかという、読解の解き方を一般化して学ぶことです。
たとえば:
-
「理由を聞かれたら、~だからで終わらせる」
-
「心情を問われたら、出来事+気持ちの組み合わせで答える」
こうした読解解法の型を身につけることが、長期的な読解力・偏差値向上につながります。
授業前に読み返す「読解の教訓メモ」で、記憶と理解を定着させる
わが家では、週テストやカリキュラムテスト、演習授業のたびに、「どこで間違えたか」「どう答えるべきだったか」「次に同じミスを防ぐにはどうすべきか」といった「読解の振り返りノート」を娘と一緒に作っています。
このノートには、ただ模範解答を書き写すのではなく、「その問題から得た教訓」や「次に気をつけたいこと」を、自分の言葉でまとめるようにしています。そして、授業や演習の前にこれを読み返すことで、「あ、そうだった!この形の設問は「~から」で終わるんだった」といった形でミスの再発を防止できるようになりました。
たとえば私自身、「理由を聞かれたときは、気持ちも一緒に答えるって、前にも言ったよね?」「これ、何回目かな?」というセリフを何度言ったかわかりません(笑)。でも、こうした「積み上げ式の反省と振り返り」が読解問題への苦手意識を減らし、最終的には「得点源」として自信につながったと実感しています。
読解ミスの原因は「1問1問の技術」ではなく、「解き方の型」にある
読解力は、才能や語彙力以上に、「どんな設問でも使える『読み方』と『答え方』を持っているかどうか」で差がつきます。間違えた問題をその場限りで処理するのではなく、なぜ間違えたのかを「一般化された解法」で見直す習慣をつけることが、読解力を本物にしていく道だと感じています。
この方法は、国語が苦手だった娘が、今では算数と並ぶほど安定して得点できる科目になったことからも、その有効性を実感しています。
読解力は一朝一夕では身につきませんが、日々の反復とパターンの蓄積を通じて、確実に偏差値に反映される力です。組分けテストの対策としても、「読解を型で捉える」「ミスをパターン化して克服する」この2点を押さえておけば、着実な成果につながります。
理科・社会の組分けテスト対策法
「1問1答」の徹底で得点力アップ
中学受験の組分けテストにおいて、理科・社会は「知識の積み重ね」が問われる重要科目です。そのため、「1問1答形式」の暗記対策をどれだけ徹底できるかが、得点に直結します。
家庭学習では、クイズ形式で親が出題したり、単語カードを使ったりすることで、子供の集中力を切らさず、反復による記憶定着を図ることが可能です。
4年生の段階では、1問1答が完璧に仕上がっていれば、それだけで高得点を狙うことができます。一方、5年生になると、出題が複合化・難化してくるため、1問1答ができていないと致命的に点が取れなくなってしまう現実もあります。
いずれの学年においても、理科・社会の知識問題に対する基本的な「暗記力の強化」は、偏差値アップの土台となります。
「飽き」と「苦手」を超える工夫を
暗記が単調でつまらない、という声はよく聞かれます。特に理科・社会に苦手意識がある子や、興味の薄い単元に取り組むときほど、学習のモチベーション維持が難しくなりがちです。
さらに、頑張っても点が取れなかったときには、やる気が下がってしまうという「負のスパイラル」に入ることもあります。だからこそ、保護者が「楽しさ」や「達成感」を演出する工夫がとても大切です。
たとえば、出題形式をゲーム化してみたり、単語カードに色やイラストを加えて視覚的に覚えやすくしたりするのもおすすめ。クイズ番組のように家族で楽しみながら反復できれば、継続的な記憶に繋がります。
絶対に押さえたい教材ポイント
具体的には、四谷大塚の演習問題集であれば「まとめてみよう」、早稲田アカデミーの錬成問題集なら「トレーニング」のパートは、組分けテスト直前期の最優先事項です。
また、宿題やテスト演習で間違えた問題を的確に把握し、その後に復習・定着を図ることが極めて重要です。「解けなかった問題を今なら解けるか確認し、もしできなければもう一度やる」という姿勢が成績の安定化につながります。
特に社会は、学年が上がるにつれて漢字指定が厳しくなっていくため、「4年生からすでに漢字で書けて当然」という意識づけもしておくのが得策です。
「知識の繋がり」が思考力を育てる
理科・社会の組分けテストでは、「単なる暗記」では通用しない複数知識の連結を必要とする思考系問題も数多く出題されます。
たとえば社会で「マグロ」をテーマにした場合、
-
どの漁港でマグロが水揚げされているか?
-
複数の魚の絵からマグロを選ぶ
-
マグロ漁の方法(漁法)とは?
-
マグロは日本の近海でとれるか?
このように、一つひとつは基礎的な知識であっても、同時に複数の知識を問われると難易度が一気に上がります。
「知識をつなげて考える力=思考力」が求められるこの形式に対応するには、日常生活でのアウトプット習慣が効果的です。
たとえば、お寿司屋さんやスーパーでマグロを目にしたとき、「どこでとれる?」「どの漁法?」「どの魚?」とクイズ感覚で確認するのも非常に効果的。教科書・問題集の枠を超えて知識を生きたものにすることが、偏差値アップの鍵となります。
理科の計算問題を軽視しない!
算数ではたくさん演習していても、理科の計算はつい軽視されがちです。しかし、理科の計算問題も実は、組分けテストにおいて差がつきやすい重要パートです。
演習量が不足しがちな理科計算対策として、私は原田プリントを活用しています。この教材は超基礎的な問題から応用までを丁寧にカバーしており、「演習不足の穴」を補うのに最適です。
ただし、テスト直前に詰め込むよりも、単元を学んだその週に演習を入れる形で計画的に取り組むほうが効果的です。理想はカリキュラムテスト(カリテ)前までに終わらせることですが、現実的には「組分けテストまでの数週間」で無理なく演習を計画するのが良いでしょう。
中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に
集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。
中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。
例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。
どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
個別指導・オンライン指導を検討している場合
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
家庭教師を検討している場合
一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。
講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。
各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。
中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】
無料の資料請求ページへ
![]()
確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。
ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。
少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。
まとめ|中学受験の「組分けテスト対策」は復習と計画が鍵
本記事では、早稲田アカデミー生も受験する、四谷大塚の「組分けテスト」に向けた具体的な対策法について、我が家で取り組んでいる方法をベースにご紹介しました。
「対策」と言っても、私はむしろこのテストを苦手を見つけ出すための最高の復習の機会と捉え、計画的に準備することが本質的な対策であると考えています。
成績帯によって取り組む問題のレベルや重点を変えることはもちろんありますが、本質的なアプローチはどの偏差値層でも大きく変わらないのではないでしょうか。「組分けテスト対策の王道」は、学力の可視化と、そこから導かれる弱点の補強です。
組分けテストは、塾内でのクラス分けや今後のカリキュラムに直結する重要な試験です。だからこそ、子どもの成績を効率的に伸ばすためには、漫然とした学習ではなく、「何を、どの順序で、どれだけやるか」を明確にした対策が不可欠になります。
我が家では、どの教科についても共通の基本方針があります。
-
「できることはやらない」:時間を無駄にしない。
-
「できなかったことを、できるようにする」:復習重視。
-
「日々の学習に、少しだけ負荷のある問題を加える」:応用力の育成。
このように、中学受験の組分けテスト対策とは、苦手の洗い出しと克服、そして負荷を意識した復習学習の継続に他なりません。結果として、日々の学習が強固な基礎となり、テスト本番での成果に繋がります。
どの学年・成績帯でも実践可能で再現性のある方法ですので、少しでも皆さまのご家庭の対策の参考になればと思います。
\ 成績が伸び悩むときに読みたい実践ガイド。中学受験の「停滞期」を抜け出す重要ポイントを網羅! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。
このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。
偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。よろしければ、以下のリンクよりご覧ください。
https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)
以下は参考記事です。