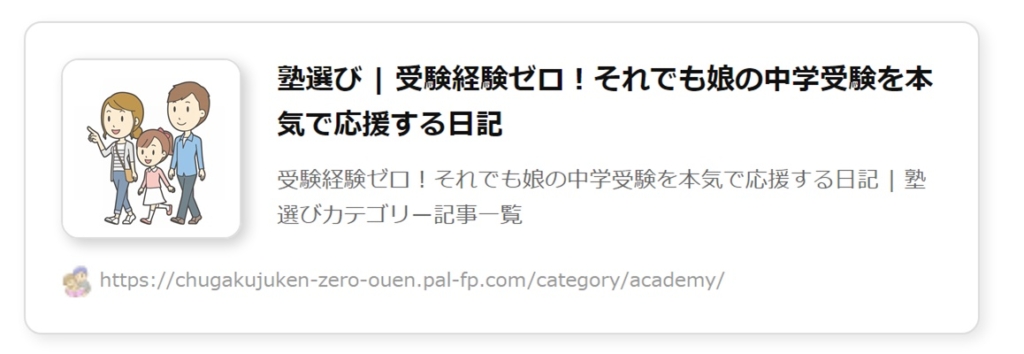中学受験の塾特待は狙うべき?サピックス・早稲アカ・日能研・四谷大塚の仕組みとリスクを保護者目線で徹底解説

\ この学習法が娘の成績を変えました! /
中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。
https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537
中学受験を考え始めると、真っ先に頭をよぎるのが「塾の授業料、最後まで払っていけるかな」というお金の不安ではないでしょうか。そこにちらちら見えてくるのが、「特待生」という言葉です。成績が良ければ、授業料が大幅に減ったり、免除になったりする制度。家計的には本当にありがたいですよね。
一方で、「特待狙いでがんばればお得」と単純に考えてしまうと、子どもへのプレッシャーが強くなりすぎたり、本来の志望校対策からブレてしまうリスクもあります。



私自身、娘の中学受験を考えたときに、サピックス・早稲田アカデミー・日能研・四谷大塚といった大手塾の特待制度をかなり真剣に調べました。というのも、長女は低学年のときから早稲田アカデミーと日能研から特待の声がかかったため、特待の観点も塾選びの対象になったからです。
そして、その後、実際に小4から早稲田アカデミーに通い始めてからは、全国統一小学生テストや組分けテストの成績によって小6で卒業するまでずっと特待Aを維持していたため、特待についての情報を自然と塾に直接聞いたり、同じく特待の資格を持つ子の保護者から情報を聞くことができました。
この記事では、塾の特待制度をどう捉え、実際に「狙うべきか」を判断するための視点を、保護者目線で整理していきます。サピックス・早稲田アカデミー・日能研・四谷大塚の4塾を中心に、それぞれの概要も網羅的にまとめますので、特待を検討されている方の参考になればうれしいです。
中学受験における「塾特待制度」とは何か
学校特待と塾特待は別物と考える
まず整理しておきたいのは、「中学校側の特待制度」と「塾側の特待制度」は別物だという点です。
中学校の特待は、入学金・授業料・施設費などが一部または全額免除になる制度で、プレテストや入試本番の成績をもとに決まることが多いです。
一方で、今回テーマにするのは通っている塾での授業料・講習費などが免除または割引になる特待制度です。中学受験に向けて長期間通うことを考えると、こちらも家計インパクトが非常に大きく、じっくり検討する価値があります。
特待生=授業料全額免除とは限らない
「特待生」と聞くと、全額無料というイメージを持たれるかもしれませんが、実際には、
- 授業料全額免除
- 授業料の半額免除
- 講習費のみ割引
- テキスト代やテスト代の免除
など、塾やコースによって内容はかなり違うのが現実です。
ですから、制度の名称だけで判断するのではなく、「どこまでの費用が、どの期間、どんな条件で免除になるのか」を具体的に確認することがとても大切だと思います。
どういう子が対象になるのか
塾の特待は、基本的には「成績優秀者への経済的支援」と「塾の看板となる生徒へのインセンティブ」という側面があります。
そのため、対象になるお子さんは、
- 通塾テスト・公開模試で継続して上位成績を取っている
- 上位クラスを安定してキープしている
- 場合によっては、志望校の合格実績につながりそうな層
であることが多いです。塾によっては、特待狙いを考えるなら一発のテストだけでなく、年間を通した位置づけも意識しておく必要があるようです。
メリット:経済的負担とモチベーションの両面
塾特待の最大のメリットは、やはり授業料や講習費の軽減による家計負担の減少です。
年間で見ると、四谷大塚・サピックス・日能研・早稲田アカデミーといった大手塾では、教材費や講習費を含めると100万円前後かかる学年も珍しくありません。そこから半額・全額が免除になるなら、家計としては非常に助かります。
また、「特待認定を維持したい」という気持ちが、お子さんにとって良い意味でのモチベーションになることもあります。「がんばった結果として認めてもらえた」という手応えは、子どもにとっても大きいです。
デメリット:プレッシャーと塾の方針への縛り
一方で、特待にはデメリットや注意点もあります。
- 特待維持のために、成績へのプレッシャーが強くなりすぎる
- 志望校対策よりも、「塾内順位」や「特待条件」を優先してしまいがち
- 他塾への転塾や、コース変更の自由度が下がる場合もある
親としても、「せっかく特待をもらっているのだから、やめるのはもったいない」と感じてしまい、本来取りたかった選択肢を取りにくくなることもあるのではと思います。
大手中学受験塾の特待制度の概要
サピックスの特待制度
サピックスについては、私の中では結論が出ていて、ネットではさまざまな情報が飛び交いますが、結論としては「サピックスには授業料免除の特待制度の仕組みはない」という理解で動くほうが、安全で計画が立てやすいと考えます。
サピックスの授業料や特待については、既に公開している以下の記事で、かなり掘り下げて解説しています。サピックスを検討されている方は、そちらも合わせて読んでみると、イメージがつかみやすいと思います。
→ サピックスの授業料や特待制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
サピックスの授業料は「免除」にできる?——特待制度の有無、他塾との違い、家計の現実的対策まで保護者目線で徹底解説
https://chugakujuken-zero-ouen.pal-fp.com/academy/sapix-tuition-exemption-guide/
早稲田アカデミーの特待制度
早稲田アカデミーは、特待制度の仕組みが比較的分かりやすく公開されている塾の一つです。
小4〜小6については、ざっくりいうと、
- 7月・12月の組分けテスト
- 年2回の全国統一小学生テスト
といった大きなテストの結果に基づき、時期によって前期・後期それぞれの授業料が全額になる特待A・半額免除になる特待Bが認定されます。
我が家の場合、長女が実際に小4から早稲田アカデミーに通い始めてから、ときには全国統一小学生テスト、ときには組分けテストの成績によって、小6で卒業するまでずっと特待Aを維持していたため経済的にとても助かりました。
さらに、NN志望校別オープン模試で一定の成績を収めると、NN志望校別コースの授業料が免除・割引になるパターンもあります。特に難関校志望のお子さんにとっては、ここで特待を得られるかどうかが、家計面でも大きな意味を持ちます。
なお、早稲田アカデミーでは、小1~小3向けの講座でも、テスト結果による特待認定があります。低学年から在籍していると、テストの雰囲気に慣れやすい一方で、「常に特待を目指して走り続ける」状態になってしまうケースもあります。
また、低学年向けの授業が、中学受験にとても役に立つとも限りません。我が家でも、娘がまだ低学年の頃に、早稲アカのテストで特待認定を受け、体験授業を受けたものの、わざわざ送り迎えして授業を受けるほどのものかなと感じ、通塾開始には至りませんでした。
低学年での特待は、低学年からの通塾を決めている方が、最終的には「特待が取れたらラッキー」くらいの温度感で十分ではと思っています。
なお、小1~小3の早稲田アカデミーの特待制度の具体的な基準については、以下の記事で詳しく整理されているので、関心のある方はそちらを参照されると理解しやすいと思います。
→ 早稲田アカデミー低学年の特待基準については、
「早稲田アカデミーの特待生基準とは?~小1・小2・小3編~」
https://chugakujuken-zero-ouen.pal-fp.com/practice-exam/20200808-wasedaacademy-summerchallengetest-tokutai/
で、具体的なスコアやテストの位置づけが詳しく解説されています。
日能研の特待(スカラシップ)制度
日能研には、「スカラシップ」といった名称で知られる特待制度があります。特徴的なのは、
- 1回のテスト結果だけでなく、一定期間の成績や学習態度などを総合的に評価する
- 成績優秀で、学習面でも模範となるような生徒を対象にしている
という点です。つまり、早稲田アカデミーのように「その日だけたまたま良かった」という一発勝負ではなく、年間を通した取り組みが重視される制度と言えます。
公式の案内によると、
- 新4年生(小3の2月から4年生になる学年)については、原則1年間を対象とするスカラシップ
- 新5年・新6年については、半期ごと(半年単位)での認定・更新
という形が基本になっているようです。スカラシップの内容はレベルによって違いますが、一般的には、
- 本科授業の授業料
- テスト費用
- 教材費
- 場合によっては講習費用
などが免除となります。
日能研は年間を通してテスト・講習がしっかり組まれている塾なので、フルで適用されると、家計へのインパクトは相当大きいと考えて良いと思います。
日能研の特待制度を視野に入れるなら、
- 「年間を通して安定した学習を続けられるか」
- テストごとのアップダウンより、長期的な積み上げ型の学習が合うタイプか
- 教室の雰囲気として、特待生への期待や周囲の目が強すぎないか
といった点を意識しておくと良いと思います。
私が保護者の立場で情報収集していたときも、一発勝負ではなく成績の安定が求められるのはとても魅力的に思いました。長女は成績の波が少なかったですが、それでもゼロではありませんでしたので。そのスタイルと、お子さんの性格が合うかどうかも、特待を狙う前に考えておきたいポイントです。
\ 実践者が続々と増え、150名を突破! /
中学受験算数では、間違えた問題や理解不足の問題を集めて分析・復習する 「復習ノート」「解き直しノート」が、 成績を伸ばすうえで非常に有効です。
これまでに150人以上の保護者の方が、私の算数復習ノートのnote記事を読んで、お子さんの算数の学習に応用していただいています。
私自身が、中学受験に本気で伴走する中で試行錯誤し、
効果を実感してきた
復習ノートの作り方・使い方・考え方のすべて
を、20,000字超の記録としてまとめた記事
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
ぜひこちらも参考にしてみてください。
四谷大塚の特待制度
四谷大塚は、「予習シリーズ」「組分けテスト」「合不合判定テスト」などで有名な塾です。
特待については、公式に細かい条件が一般公開されているわけではありませんが、
- 組分けテストや公開模試の成績上位者
- 全国統一小学生テストで非常に高い成績を収めた層
などを対象に、授業料やテスト費用を免除・割引する制度が設けられているようです。
保護者の体験談や情報サイトを見ると、四谷大塚の特待には、
- 授業料の全額免除
- 授業料の一部免除
といったパターンがあるようです。
四谷大塚が主催する全国統一小学生テストは、早稲田アカデミーの特待認定にも使われているテストです。
長女は全国統一小学生テストの決勝に何度も出場していますが、四谷大塚の方が他塾生の保護者向けに特待の案内を配っていました。このため、少なくとも全統小の決勝に進出すれば、早稲田アカデミーと同様に授業料全額免除の特待を得られることは間違いありません。
特待を「狙う」かどうかを決めるチェックポイント
家計のためにどこまで期待していいか
特待制度は、確かに家計の負担を大きく減らしてくれる可能性のある制度です。
しかし、現実には、
- 全員がもらえるわけではない
- 一度認定されても、成績によっては継続できない
- 塾や年度によって基準や内容が変更される可能性がある
という不確定要素を抱えています。
そのため、ライフプランとしては、「特待は気にせず塾を選び、取れたらラッキー」くらいに考えておくのが安全だと、個人的には感じています。
子どもの性格とプレッシャー
特待を狙うかどうかを考えるとき、一番大事なのはお子さんの性格だと思います。
- プレッシャーをバネにして伸びるタイプ
- 緊張が強く、成績や順位を意識しすぎるとメンタルを崩しやすいタイプ
では、同じ制度でも受け止め方がまったく違います。
私の場合、娘は「やると決めたら徹底的にやるけれど、結果を気にしすぎるところもある」タイプだったので、「特待のことは極力話題に出さない」ことを最初に決めました。もし結果として特待認定をもらえたら、そのときにどうするか考えればいい、と割り切ったほうが、親子ともに気持ちが楽でした。
なお、結果的に通塾期間の全てで長女は特待Aでしたので、経済的な貢献は著しく中学受験後には好きなものを好きなだけ買ってあげることにしました。
志望校対策とのバランス
塾特待を追いかけるあまり、志望校の対策が後回しになってしまうことは、できるだけ避けたいところです。
- 塾内テストでの順位
- 特待維持ラインの偏差値
ばかりを気にしすぎると、「志望校に必要な力」と「塾内で上位にいるための力」がズレていることもあるからです。
特に、志望校の出題傾向が塾のテキストと大きく異なる場合、6年生以降は塾の成績よりも志望校の過去問に寄せた勉強にシフトしなければならないケースも多いです。
その意味でも、特待制度はあくまで「おまけ」であり、主役はいつも「志望校合格」にあると考えておくと、判断がぶれにくいと思います。
我が家が考えた「現実的な落としどころ」
我が家では、娘の中学受験に向けて塾を選ぶ際、
- 特待制度は一応調べておく
- でも、塾選びの優先順位は
「学習スタイル」「先生との相性」「通いやすさ」「志望校との相性」
という方針にしました。
中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に
集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。
中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。
例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。
どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。
まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。
資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。
個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。
迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。
個別指導・オンライン指導を検討している場合
SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。
私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。
家庭教師を検討している場合
一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。
講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。
各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。
中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】
無料の資料請求ページへ
![]()
確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。
ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。
少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。
まとめ
塾の特待制度は、うまく活用できれば家計にとって非常に頼もしい仕組みです。一方で、子どもの精神的な負担や、志望校対策とのバランスを崩すリスクも抱えています。
大手4塾のうち、サピックス以外の早稲田アカデミー・日能研・四谷大塚はいずれも、何らかの形で成績優秀者向けの特待制度を設けており、授業料・講習費・テスト代などの免除や割引が行われています。ただし、内容や基準は年度によって異なり、変更されることもあります。
ですから、保護者としては、
- 「特待がなくても通えるか」をベースに家計を考える
- 特待は「取れたらありがたいボーナス」くらいの位置づけにする
- 子どもの性格や志望校との相性を最優先する
- 気になる塾については、必ず公式の資料や説明会で最新情報を確認する
といったスタンスで向き合うのが、結果的に親子にとっていちばん健全なのではないかと感じます。
特待を「狙うかどうか」の正解は、ご家庭ごとに違います。この記事が、ご家庭なりの方針を言葉にするきっかけになればうれしいです。
\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /
中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。
私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)
「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」
を、noteで公開しています。
以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。
Twitterで娘への日々の小さなサポートを紹介しています。
@zeropapa_juken を見る(X/Twitter)